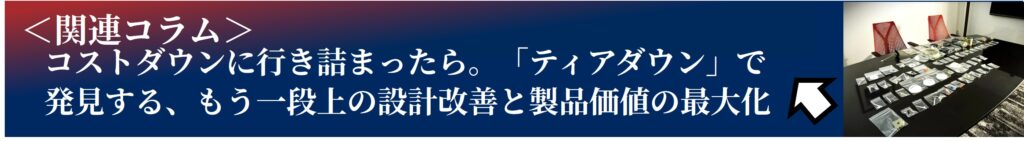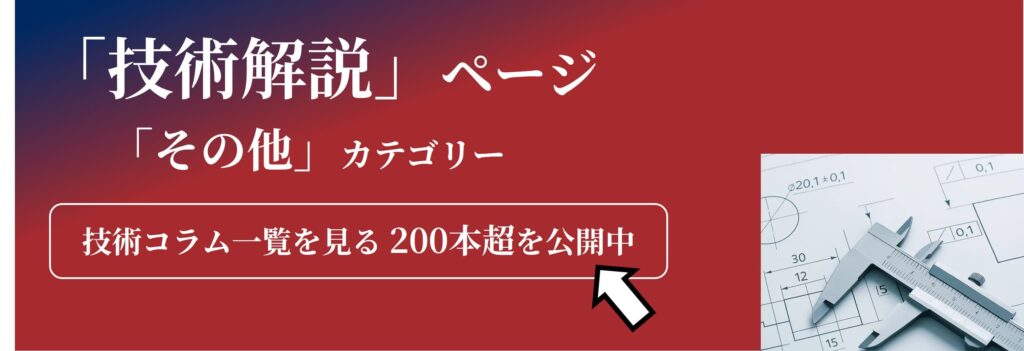成形不良・コスト高を未然に防ぐ!設計段階から始める“相談型見積”のすすめ

その見積依頼、本当に「最適」ですか?
射出成形の見積依頼。完成した図面と指定した材料を複数のメーカーに送り、価格だけで発注先を決めていないでしょうか?
一見、合理的ですが、この「価格比較」だけの方法では、品質、コスト、納期を最適化する絶好の機会を逃しているかもしれません。射出成形は、図面通りに作るだけの単純作業ではありません。材料、金型、成形条件が複雑に絡み合う製造のプロの知見を活かせば、設計段階では見えない課題を未然に防ぎ、製品の価値をさらに高めることが可能です。
本コラムでは、開発の早期段階から当社と協働する「相談型見積」というアプローチをご紹介します。図面完成前の「対話」が、いかにしてお客様の製品開発を成功に導くのか、そのメリットを解説します。
見積依頼のよくある誤解とその落とし穴
誤解①:「図面が完成してから相談すべき」
設計者の多くは、「完成図面がなければ相談してはいけない」、「未確定のまま話すのは失礼だ」と考えがちです。その姿勢自体は誠実ですが、実はこの“遠慮”が設計の最適化を阻んでいる場合があります。たとえば以下のような落とし穴が図面に潜んでいることがあります。
- 肉厚が不均一でヒケが出る
- リブの配置が偏っていて反りが発生する
- 抜き勾配が足りず離型できない
このような成形上の問題は、CADでは気づきにくく、製造現場で初めて発覚することも珍しくありません。図面確定後に成形性の問題が明らかになれば、金型設計の手戻りや開発スケジュールの遅延を招くリスクがあります。
誤解②:「材料は設計者が選ぶもの」
設計者が求める性能(耐熱性・剛性・耐薬品性など)に応じて材料を指定するのは当然のことです。しかし、「その材料が成形しやすいかどうか」や「コスト・入手性・生産性を加味して妥当かどうか」まで検証されていないケースも少なくありません。
たとえば、あるスーパーエンプラは耐熱性や寸法安定性に優れていますが、
- 粘度が高く流動性が悪いため薄肉や微細形状に届きにくい
- 高価で入手性に波があり、安定供給が難しい
- 成形温度が高く、金型の寿命や冷却時間に影響する
といったケースもなくもありません。こうした事情を知らずに材料を決めてしまうと、成形不良やコスト高、納期遅延の原因となる可能性もあります。
誤解③:「複数社で見積を取れば、安い会社がベスト」
図面と材料を統一して相見積もりを行い、価格比較する——これは発注側として当然の行動に思えるかもしれません。ですが、その“数字の裏側”まで考慮できているでしょうか?
- 後工程や検査工数が含まれていない
- 無理な成形条件で価格だけを合わせている
- 不良率を織り込んでおらず、供給安定性に乏しい
安価な見積の裏には、後で“見えないコスト”として跳ね返ってくるリスクが隠れているのです。価格だけを見てメーカーを選定するのは、品質・納期・安定性といった本質的な価値を軽視することになりかねません。
「相談型見積」が成功の鍵を握る3つの理由
図面完成後ではなく、設計構想の段階から成形メーカーに相談する。これが「相談型見積」です。従来の見積プロセスと何が違い、なぜ効果的なのか。その理由を3つに分けて解説します。
理由①:形状の最適化ができる
成形品の品質を安定させるには、製品形状と金型構造の整合性が欠かせません。たとえば以下のようなセオリーがあります。
- 肉厚はできるだけ均一にする
- R(丸み)をつけて樹脂の流れを滑らかにする
- 抜き勾配をつけて離型性を確保する
こうした原則はCAD上では見落とされがちです。設計段階で府中プラが関与できれば、ヒケや反り、ショートショットなどのリスクを事前に検出し、「歩留まりの高い形状」に修正する提案が可能です。たとえば、「このリブは強度を保ったまま肉抜き可能です」「ここはスライド構造にすると金型コストが抑えられます」など、金型設計や生産条件も加味した提案ができます。これにより、後工程での手戻りを防ぎ、開発リードタイム短縮にも貢献します。
理由②:材料選定の幅が広がる
必要な性能(耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性など)を満たす材料が、実は高額で納期が長い特殊材だった、というケースは少なくありません。ところが、当社の視点から見ると、次のような代替案が提案できることもあります。
- 近年登場した高性能な汎用エンプラで性能を満たせる
- グレードダウンしても使用条件下で問題ない
- 添加剤や充填材の違いによって成形性が向上する
当社は材料メーカーとの連携のもと、物性・コスト・納期を総合的に判断し、最適な材料を提案できます。「その材料、本当に必要ですか?」という問いから始まる提案は、品質と経済性の両立に直結します。
理由③:設計思想をくみ取った協働提案ができる
府中プラが最も大切にしているのは、“なぜこの設計になっているのか”という背景への理解です。「強度を確保したい」「嵌合性を保ちたい」「見栄えを損ねたくない」——設計者の意図を丁寧にくみ取ることで、その目的を果たす最適な形状や製造方法を一緒に検討できます。
このような協働によって、一方通行では生まれ得ない提案や改善策が現れます。これこそが「相談型見積」の本質であり、製品開発を成功させる最も堅実なアプローチだと考えています。
「相談型見積」による成功パターン例
リブ形状の見直しで反り不良を回避し、検査工数を削減
これまで機構部品で、厚肉リブによって反りが発生。設計意図をヒアリングしたうえで、肉厚を落として本数を増やす代替案を提案。これにより、反りやヒケが大幅に改善し、検査工数が大幅に減った。
材料変更により金型取り数が2倍に。製品単価が大幅に低減
高機能樹脂の流動性が悪く1個取り金型しか設計できなかった製品に対して、性能要件を満たす高流動グレードを提案。結果として2個取り金型が可能となり、生産効率が倍増。製品単価が大幅に低減された。
バリ発生を特殊グレードで解消。手作業工程をゼロに
結晶性樹脂を使用した摺動部品でバリが問題となっていたケースでは、密着性が高くバリの出にくい樹脂グレードを提案。手作業でのバリ取りが不要となり、リードタイムと工数が大幅に短縮された。
複合部品を一体化して組立工程をゼロに
ネジと接着剤で組み立てていた複合部品構成のユニットを1部品に統合。初期金型費は増たが、組立工数と部品点数、副資材コストがすべてゼロとなり、トータルで大幅なコストダウンになった。
さあ、「相談型見積」を始めよう!お問合せ時に共有いただきたい情報
ここまで読んで「まずは相談してみたい」と感じた方もいらっしゃるかと思います。では、当社にご相談いただく際、どんな情報を伝えればより良い提案ができるのでしょうか。
完璧な設計図や仕様書がなくても構いません。以下の4つのポイントを押さえていただければ、対話がスムーズに進み、提案の精度が格段に高まります。
① 仮図(ポンチ絵、ラフスケッチ、画像データでもOK)
最初から3D CADや詳細図面を用意する必要はありません。手書きでも、スマートフォンで撮影したスケッチでも構いません。全体の構成や機能、サイズ感が伝わるものであれば、製造のプロとして最適なアプローチを組み立てることが可能です。
② 使用環境・用途・要求特性
この情報が最も重要です。たとえば、次のような情報があると判断が的確になります。
- 「屋外で10年以上使用する外装部品」
- 「強アルカリの薬品と接触する機構部品」
- 「他部品と勘合するため寸法精度が重要」
- 「耐熱性と剛性を両立したい」
「何のために、どんな環境で使うのか」が分かると、適切な材料選定や成形仕様、金型構造の提案が可能になります。
③ 年間予定数量・量産スケジュール
数量とスケジュールの情報は、概算でも構いません。金型仕様や生産方式を判断する材料になります。
- 年間数百個なら、簡易型で初期投資を抑える
- 年間数万個なら、多数個取りで製品単価を最小化
- 開発スケジュールに合わせた段階的な量産移行の提案も可能
④ 検討中の材料と、その理由・背景
既に「この材料を使いたい」とお考えの場合は、ぜひその理由を教えてください。
- 「以前の製品で使って問題なかった」
- 「この薬品に対する耐性が必要」
- 「コスト重視でPPを選んだ」
といった背景が分かれば、同じ機能をより低コスト・短納期で実現できる代替材料を提案できるかもしれません。
もちろん、これらの情報がすべて揃っていなくても問題ありません。「こんなものを作りたいのですが…」という曖昧な段階からでも、府中プラは“対話”を通じて、必要な情報を引き出し、最適解をご提案します。
まとめ:図面完成前の“対話”が、開発の未来を変える
見積とは、単なる価格比較の手段ではありません。製品の品質とコスト、量産安定性を左右する「最初の設計レビューの機会」であるべきです。完成図面を前提とした価格勝負では、設計ミスに気づくタイミングも遅く、改善のチャンスを逃してしまいます。一方で、早期に相談をいただければ、府中プラの知見を活かした“先回りの提案”が可能になります。
製品開発において、設計者と成形メーカーが協働する「相談型見積」は、単なるコスト削減手法ではなく、“設計の質”そのものを引き上げるパートナーシップの形です。
「まずは話してみようか」——
その一歩が、貴社の製品をより信頼性の高い、競争力あるものへと導くきっかけになると、府中プラは信じています。