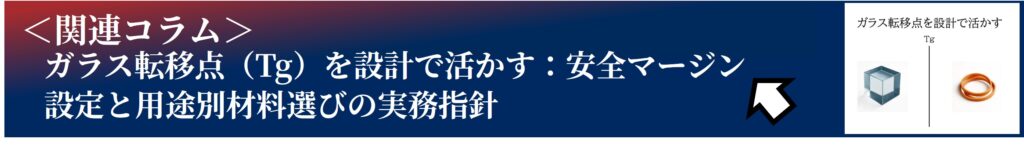ガラス転移点(Tg)を理解する:耐熱性・靭性・寸法安定性の設計指標とは ― HDTとの違いを押さえて、Tgを正しく活かす材料選定・設計判断の基礎 ―
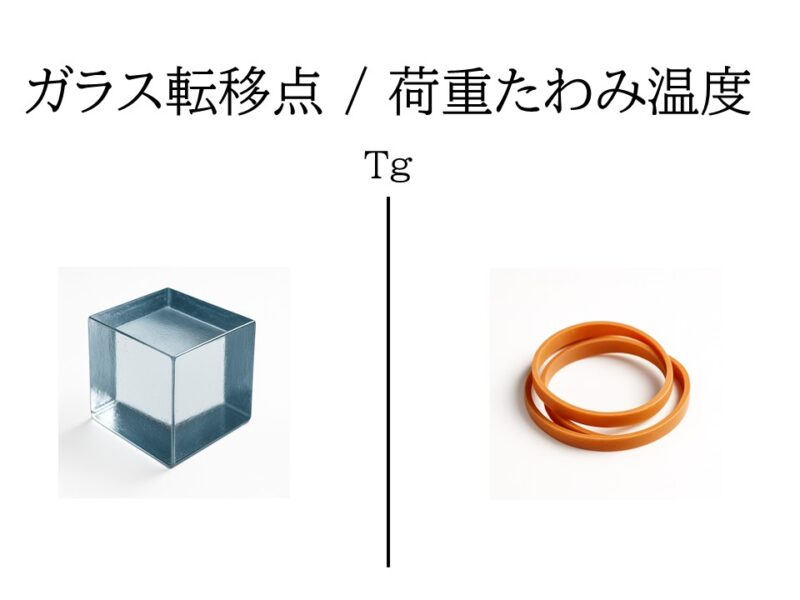
「TgとHDTはどう違うのか」、「どの耐熱指標を基準にすべきか」。これらは射出成形部品の設計現場で頻繁に聞かれる疑問です。特にガラス転移点(Tg)は、単なる耐熱温度の目安として漠然と捉えられていることが少なくありません。
しかし、Tgは材料の剛性、靭性、そして長期的な寸法安定性を支配する、極めて重要な物理的特性です。本稿では、Tgの本当の意味と役割を設計に活かしていただくことを目的に、その物理的な定義からHDTとの本質的な違い、製品特性への影響までを解説し、より確かな材料選定と設計判断に繋がる視点を府中プラが提供します。
ガラス転移点(Tg)とは何か?
すべての議論の基礎となる「ガラス転移点(Tg)」そのものについて、その定義と物理的な意味から解説します。
Tgとは、非晶性樹脂が、ある温度を境に物性を大きく変える転移温度を指します。具体的には、硬くてもろい「ガラス状態」から、柔らかく粘りのある「ゴム状態」へと変化する温度点です。
Tgよりも十分に低い温度域では、材料を構成する高分子鎖の動きはほとんど凍結されています。このため、材料は硬質で剛直なガラスのような挙動を示します。一方、温度が上昇してTgを超えると、分子鎖の主要な部分が動き出すことが可能になり、外力に対して柔軟に変形できるようになります。これにより、材料はゴムのようにしなやかな性質へと変化します。この物性の劇的な変化こそがガラス転移です。
では、結晶性樹脂の場合はどうでしょうか。結晶性樹脂は、分子鎖が規則正しく並んだ「結晶部分」と、ランダムに固まった「非晶部分」が混在した構造をしています。このため、結晶性樹脂にも非晶部分に対応するTgが存在します。ただし、結晶部分は融点(Tm)に達するまでその構造を維持し、材料全体の剛性を支える「骨格」の役割を果たします。したがって、結晶性樹脂の物性は、非晶部分のガラス転移と、結晶部分の融解という二つの熱的挙動を考慮して評価する必要があります。
HDTとの違いを明確に理解する
設計現場でTgと共によく参照されるのがHDT(荷重たわみ温度)です。この二つの指標は混同されがちですが、その意味は全く異なります。両者の違いを明確にすることが、適切な材料選定の第一歩です。
TgとHDTの違い(定義・意味)
Tgは、材料を構成する分子鎖の運動性が変化する、材料固有の物理的な転移温度です。その測定において外部から荷重はかけられていません。つまり、Tgは材料単体が持つ、無荷重下での熱的性質の指標と言えます。
一方、HDTは「Heat Deflection Temperature」または「Heat Distortion Temperature」の略で、JIS K 7191やASTM D648で規格化された試験方法によって測定されます。この試験では、規定寸法の試験片に曲げ荷重(一般的には1.80MPaまたは0.45MPa)をかけた状態で、一定速度で昇温していきます。そして、試験片のたわみ量が規定値(例:0.25mm)に達した時点の温度をHDTとして記録します。この測定方法から分かるように、HDTは一定荷重下で、材料がどのくらいの温度まで形状を維持できるかを示す、より実用的な変形のしやすさの指標です。
この違いがもたらす最も重要な結論は、HDTの値は「Tg」と「その温度域での剛性(弾性率)」という二つの要素によって決まるということです。Tgは材料が軟化を始める温度の目安ですが、実際にどれだけたわむかは、その時点での剛性の高さに依存します。剛性が高ければ、Tgを超えてもなかなか変形せず、結果としてHDTは高い値を示します。
TgとHDTが乖離する例
この「Tg」と「剛性」の複合的な関係は、具体的な樹脂の例を見ることで一層明確に理解できます。
代表的な非晶性樹脂であるPC(ポリカーボネート)のTgは約145℃です。ガラス状態での剛性が高いため、HDT(1.80MPa荷重)は約130℃となり、Tgと比較的近い値を示します。これは多くの非晶性樹脂に見られる典型的な傾向です。
次に、代表的な結晶性樹脂であるPA66(ポリアミド66)の例を見てみます。PA66のTgは約50℃と比較的低いですが、HDT(1.80MPa荷重)は、約200℃という非常に高い値を示します。この大きな乖離は、PA66が持つ「結晶構造」に起因します。Tgの50℃を超えて非晶部分がゴム状態に移行しても、融点(約265℃)まで安定な結晶部分が骨格として全体の剛性を維持するため、高い荷重下でも変形しにくいのです。
この二つの例は、「Tgが高い=耐熱性が高い」といった単純な判断が、いかに危険であるかを示唆しています。材料の耐熱性を評価するには、TgとHDT双方の意味を理解し、特に結晶性樹脂では結晶構造の寄与まで考慮に入れる必要があります。
Tgが支配する設計特性
Tgは単に軟化が始まる温度というだけでなく、製品の信頼性に直結する様々な特性の転換点となります。
寸法安定性とTg
精密機器のハウジングや光学部品など、高い寸法精度が長期間要求される用途では、Tgの理解が不可欠です。Tgより十分に低い温度域では、分子鎖の動きが抑制され、寸法は安定しています。しかし、使用温度がTgに近づくと、成形時に内部に固定された残留応力が解放され(応力緩和)、製品の反りや寸法変化を引き起こします。また、荷重下ではクリープ(時間経過による変形)が著しく進行します。長期的な寸法安定性が求められる設計では、想定される最大使用温度が材料のTgより十分に低いことが絶対条件となります。
衝撃特性とTg
Tgは、材料の靭性(粘り強さ)にも大きな影響を与えます。Tg以下のガラス状態では、材料は硬く、衝撃エネルギーを吸収しきれずに破壊する「脆性破壊」を起こしやすくなります。一方、Tgを超えるゴム状態では、分子鎖が柔軟に動いて衝撃エネルギーを効率的に吸収できるため、粘り強い「延性破壊」を示します。このため、低温環境で使用される部品には、その最低使用温度よりも低いTgを持つ材料が選定されるなど、靭性設計においてTgは重要な判断基準となります。例えば、低温環境での使用が想定される屋外用機器の筐体には、使用される最低温度よりも低いTgを持つ材料が選ばれます。ABS樹脂がその代表例で、ポリブタジエンゴム成分のTgが-80℃程度と非常に低いため、冬場の低温環境でも優れた耐衝撃性を維持できるのです。
使用温度範囲の目安としてのTg
HDTは短期的な耐熱性の目安ですが、応力緩和やクリープといった長期的な現象を評価するものではありません。長期にわたる信頼性を確保するためには、Tgを基準に考える必要があります。実務的な経験則として、無荷重または低荷重下での長期連続使用を想定する場合、その上限温度は「Tg-10℃~20℃」程度を目安とするのが一般的です。これは、長期的な寸法安定性まで考慮した耐熱設計を行う上での、非常に有効な出発点となります。
Tgを活かした材料選定と設計判断
これまで解説してきた知識を、具体的な材料選定や設計判断に活かす視点を整理します。
用途別:Tg重視の材料選定例
製品の用途によって、Tgをどう捉えるべきかは異なります。
精密部品(光学・電子部品)
カメラのレンズ鏡筒、光ピックアップ部品、各種コネクタなど、μmオーダーの寸法精度と長期的な安定性が求められる用途では、寸法安定性が最優先されます。この場合、選定方針は明確です。想定される使用温度範囲の最高温度よりも、十分に高いTgを持つ材料を選ぶことが絶対条件となります。具体的には、PEI(ポリエーテルイミド、Tg≈217℃)、PES(ポリエーテルサルホン、Tg≈225℃)、PPSU(ポリフェニルサルホン、Tg≈220℃)といった、Tgが200℃を超える非晶性のスーパーエンプラが有力な候補となります。これらの材料は、Tgが高いために広い温度範囲でガラス状態を維持し、優れた寸法安定性と低クリープ性を発揮します。
衝撃用途(屋外・低温環境)
一方、ヘルメットや電動工具のハウジング、寒冷地で使用される機器の筐体など、耐衝撃性が重視される用途では、異なる視点が必要です。ここでは、Tgの低さが有利に働くことがあります。前述の通り、使用温度がTgを下回ると材料は脆化しやすくなるため、想定される最低使用温度よりも低いTgを持つ材料を選ぶことが、靭性を確保する鍵となります。ABS樹脂や、PPにエラストマーを配合して低温靭性を改善した材料、各種エラストマーアロイなどがこのカテゴリーに該当します。
結晶性樹脂の総合的判断
ギアやベアリング、エンジンルーム内の部品など、機械的強度と耐熱性の両方が求められる用途では、結晶性樹脂が多用されます。この場合、Tgだけで材料を判断するのは誤りです。PA66の例で見たように、Tgが比較的低くても、結晶構造のおかげで高温まで高い剛性と強度を維持できます。したがって、結晶性樹脂を選定する際は、非晶部の挙動を示すTg、結晶の骨格が失われる融点(Tm)、そして機械的強度のレベルを左右する結晶化度の三つの指標を総合的に見て、使用条件に適しているかを判断する必要があります。
Tgが低すぎると起こるトラブル
設計者がTgの重要性を認識せず、使用温度に対して余裕のない材料を選んでしまうと、深刻なトラブルを招く恐れがあります。例えば、使用温度がTgに近づくと、応力緩和によって嵌合部の固定力が低下し、ガタつきや脱落が発生します。また、残留応力の解放による予期せぬ反りや変形も、製品の機能不全や信頼性低下に直結します。これらの不具合を未然に防ぐためにも、設計初期段階でのTgの正しい評価が不可欠です。
まとめ
府中プラが本稿を通してお伝えしたかった要点は、Tgが単なる耐熱指標ではなく、材料の機械特性や寸法安定性が劇的に変化する物理的な「転換点」であるということです。硬く脆いガラス状態から、柔らかく粘りのあるゴム状態への移行点を理解することが、プラスチックの挙動を予測する鍵となります。
また、Tgは無荷重下での材料固有の性質であり、荷重下での変形挙動を示すHDTとは役割が明確に異なります。この違いを認識し、Tgを寸法安定性、衝撃特性、長期信頼性の観点から正しく評価することが、過剰品質を排しつつ要求性能を満たす、優れた設計判断を可能にするのです。