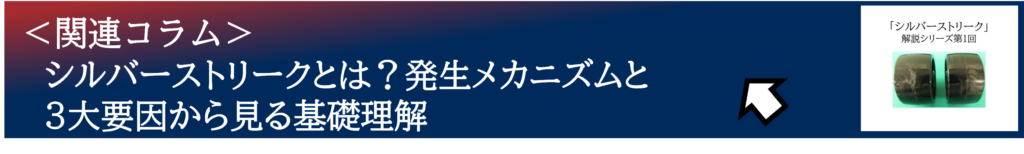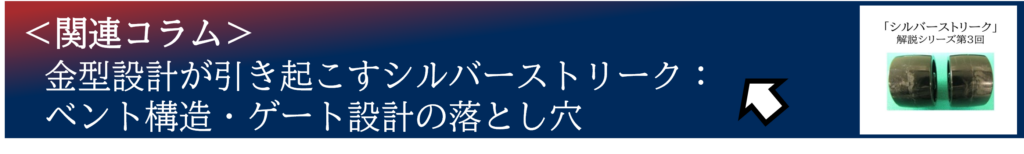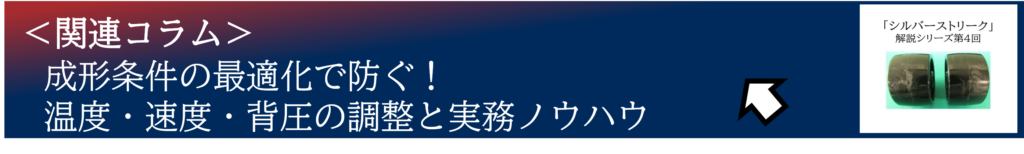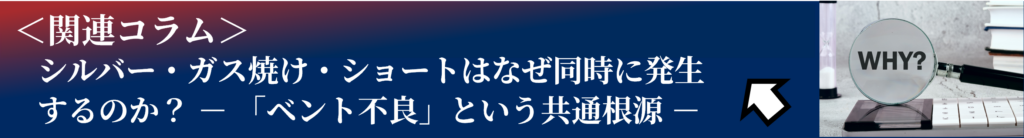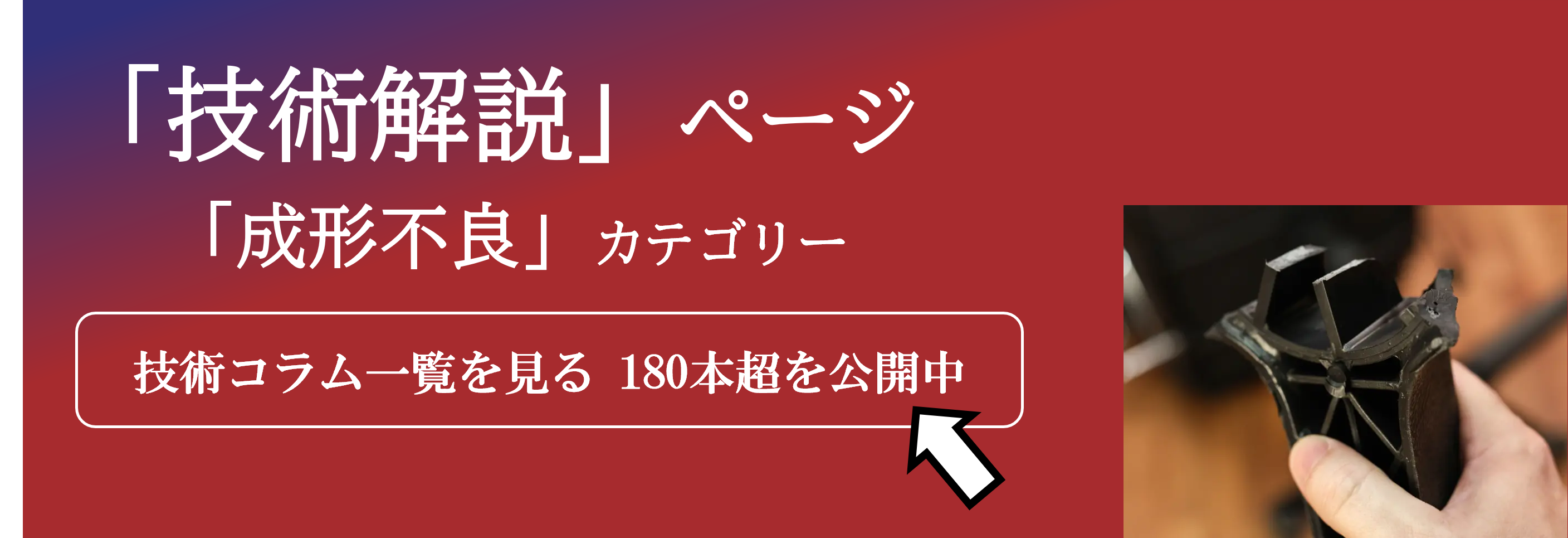シルバーストリークを成形条件から防ぐ!温度・圧力・計量設定の最適化ガイド

射出成形品の表面に現れる銀条、すなわちシルバーストリークは、その多くが成形条件を適切に設定することで大幅に抑制することが可能です。現場では、この不良が発生すると安易に「材料の乾燥不足」が原因と結論づけられる傾向がありますが、実際には日々の生産で設定される成形条件に起因するケースが非常に多いのが実情です。
府中プラは、安定した品質を確保するためには、現象の背後にある物理的な原理に基づき、成形条件を一つひとつ見直すことが不可欠であると考えます。本稿では、シルバーストリーク対策の第二弾として、バレル温度、射出速度、保圧、計量条件といった、製造現場の実務に直結する成形条件の最適化ポイントを具体的に解説します。
バレル温度と滞留時間の影響
シルバーストリークの直接的な原因であるガスは、樹脂の熱分解によっても発生します。その発生をコントロールする上で、樹脂がさらされる「温度」と「時間」の管理は最も基本的な項目です。
過熱によるガス発生メカニズム
射出成形機の加熱シリンダー内では、樹脂は溶融するために高温に熱せられますが、この温度が材料の許容範囲を超えて過剰になると、樹脂の分子構造が破壊される「熱分解」が始まります。この分解過程でガスが発生し、溶融樹脂内に混入することでシルバーストリークの直接的な原因となります。

特に、PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)やPEI(ポリエーテルイミド)、PPS(ポリフェニレンサルファイド)といったスーパーエンプラは、高い温度で成形されるため、わずかな温度のオーバーシュートでも熱分解が起こりやすく、厳密な温度管理が求められます。また、設定温度は適正でも、温度センサーやヒーターの故障によって局所的に過熱が発生している可能性も視野に入れる必要があります。
滞留による熱履歴の蓄積
樹脂が熱分解するか否かは、温度だけでなく、その温度にさらされている「滞留時間」にも大きく影響されます。成形サイクルが不安定であったり、トラブル対応などで成形機が加熱されたまま長時間停止したりすると、シリンダー内に滞留した樹脂は過剰な熱履歴を受けることになります。これにより、設定温度自体は適正範囲内であっても、熱分解が進行し、シルバーストリークが発生しやすくなります。
対策としては、長時間の停止が予測される場合には、シリンダー内の樹脂をパージした上で、低温帯域(例えば150℃~180℃)に設定温度を下げて待機することが有効です。また、ノズルからの樹脂漏れを防ぎつつ、シリンダー先端での樹脂の滞留を最小限に抑えるシャットオフノズルの採用も、滞留による熱分解を抑制する上で効果的な手段となります。
射出速度と射出圧力の設定
溶融樹脂を金型へ充填する際の速度と圧力のコントロールは、シルバーストリーク対策において非常に重要な要素です。
高速射出によるガス混入とせん断熱
射出速度を速くすると、生産サイクルタイムの短縮には貢献しますが、いくつかの要因でシルバーストリークのリスクを高めます。まず、ホッパー下部やスクリューから引き込まれた空気が、高速で流動する樹脂に巻き込まれやすくなります。さらに重要なのが「せん断発熱」です。溶融樹脂がゲートなどの狭い流路を高速で通過する際、樹脂内部の分子同士や、樹脂と金型表面との間に強い摩擦が生じ、そのエネルギーが熱に変わります。このせん断発熱によって樹脂温度が局所的に急上昇し、意図せず熱分解を引き起こすことがあります。この現象は、もともとの粘度が高い材料や、薄肉製品の成形で特に顕著になります。
低速射出時のデメリット
一方で、射出速度を単純に遅くすれば良いというわけではありません。速度が遅すぎると、樹脂が金型内で冷え固まるまでに充填が完了せず、ショートショットや、金型表面の転写不良によるフローマーク(流動痕)が発生することがあります。このフローマークが、シルバーストリークと誤認されるケースもあるため、注意が必要です。
対策:適切な射出速度プロファイルの導入
この相反する問題を解決するために有効なのが、射出工程を複数の区間に分け、それぞれで速度を変化させる「多段射出速度制御」です。例えば、最初は中速で充填を開始し、せん断発熱が問題となるゲート部を通過する直前で一度減速、ゲート通過後に再度加速し、充填末端で発生しやすいエアトラップを防ぐために最終的に減速する、といったプロファイルを設定します。このように、使用する樹脂の特性や製品形状に応じて、速度をきめ細かくコントロールすることが、シルバーストリークと他の不良の双方を抑制する鍵となります。
保圧・保圧切替の調整
射出工程が完了し、圧力制御に切り替わる保圧工程の管理も、ガスに起因する不良を防ぐ上で重要です。
保圧不足とガス残留
保圧の主な目的は、冷却固化に伴う樹脂の体積収縮を補い、ヒケやソリを防ぐことですが、もう一つ重要な役割があります。それは、金型キャビティ内の樹脂に圧力を加え続けることで、内部に残存したガスや揮発成分を圧縮し、製品表面に現れるのを防ぐ効果です。そのため、保圧の圧力が不足していたり、時間が短すぎたりすると、圧縮されなかったガスが製品表面に浮き出て、シルバーストリークとして顕在化することがあります。
保圧切替位置の誤設定
射出工程(速度制御)から保圧工程(圧力制御)に切り替えるタイミング、いわゆる「V-P切替位置」の設定も極めて重要です。この切替タイミングが遅すぎると、金型内が過剰に充填され、圧縮された空気が行き場を失い、シルバーストリークやバリの原因となります。逆に、切替タイミングが早すぎると、充填が完了する前に圧力が抜けてしまい、ヒケやガス残りが発生しやすくなります。
対策:V-P切替位置の最適化
V-P切替は、一般的に金型キャビティが95%~98%程度充填された時点で行うのが理想とされています。この最適なタイミングを見極めるためには、スクリューの前進位置や射出圧力波形を注意深く監視し、調整する必要があります。より高精度な管理を行うためには、金型内に圧力センサーを設置し、実際のキャビティ内圧に基づいてV-P切替を行う方法が非常に有効です。これにより、成形条件のわずかな変動に影響されず、常に安定した充填状態を再現できます。
計量条件・背圧・サックバックの見直し
次ショットの樹脂を可塑化・計量する工程での設定も、空気の巻き込みを防ぐ観点から見逃せません。
背圧不足による空気巻き込み
計量時、スクリューは回転しながら後退し、シリンダー先端に次ショット分の溶融樹脂を溜めていきます。このスクリューの後退に対してかける抵抗圧力が「背圧」です。背圧が低すぎると、スクリューの回転に対して樹脂の供給が追いつかず、スクリューの溝内に空気を抱き込んだまま樹脂が前方に送られてしまいます。この空気が「ガスだまり」となり、次ショットでのシルバーストリークの原因となります。研究報告では、背圧が低すぎる設定がスクリュー内部の空気抱き込みを助長し、そのまま成形中に気泡として製品表面へ現れることが示されており、適切な背圧管理が重要とされています[2]。
背圧過多の問題
対策として背圧を高く設定すれば、樹脂の混練が促進され、密度が高まるため空気の巻き込みは減少します。しかし、背圧を高くしすぎると、計量時間が長くなるだけでなく、スクリュー回転によるせん断発熱が増加し、樹脂の熱分解を助長するという別の問題を引き起こします。材料に応じて、安定した計量ができる範囲で、可能な限り低い背圧に設定することが理想です。
サックバックの設定不備
サックバックとは、計量完了後にスクリューをわずかに後退させ、ノズル先端の圧力を抜くことで樹脂の鼻タレを防ぐ操作です。このサックバック量が大きすぎると、減圧されたノズル先端から外気を吸い込んでしまい、これがシルバーストリークの直接的な原因となります。サックバックは、鼻タレが止まる最小限の量に設定することが鉄則であり、一般的にはスクリュー直径(D)の0.1倍~0.3倍程度(0.1D~0.3D)が目安とされます。
代表的な樹脂別の成形条件トラブル例
これまでの内容を踏まえ、代表的な樹脂で発生しやすい条件ミスとその対策を以下に示します。
| 材料 | よくある条件ミス | 推奨対策 |
| PA(ポリアミド) | 乾燥不足を補おうとする過度な高速射出。背圧が低く計量が不安定。 | 材料の十分な予備乾燥を徹底した上で、中速域での射出を基本とし、安定した計量が得られるよう背圧を適切に設定する。 |
| PC(ポリカーボネート) | 高温設定によるバレル内での過熱。シリンダー内での滞留時間が長い。 | メーカー推奨の温度プロファイルの中央値を基準とし、滞留時間が長くならないよう成形サイクルや機械選定を考慮する。 |
| PBT(ポリブチレンテレフタレート) | 結晶化が速いため、高速射出で充填しようとし、V-P切替が早すぎる。 | ゲート通過時のせん断発熱を避けるため減速プロファイルを設定し、ヒケが発生しないようV-P切替位置と保圧条件を慎重に再設定する。 |
成形条件の調整はシルバーストリーク対策において重要な要素ですが、条件単独での最適化には限界があります。
射出成形におけるシルバーストリークの原因と対策
では、成形条件を金型設計や材料特性とあわせて整理し、実務での判断軸を体系的に解説しています。
まとめ
シルバーストリークは、成形条件を体系的に見直し、最適化するだけでその多くを低減することが可能です。特に、射出速度のプロファイル設定、保圧への切替タイミング、そして計量時の背圧やサックバックといった条件は、しばしば見過ごされがちであり、原因を安易に材料や金型のせいにしてしまう前の重要な確認項目です。