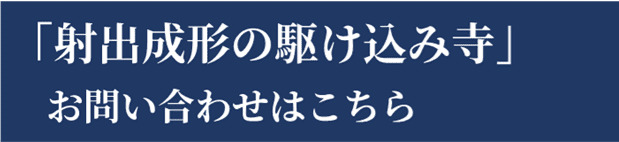ガラス転移点(Tg)を設計で活かす:安全マージン設定と用途別材料選びの実務指針
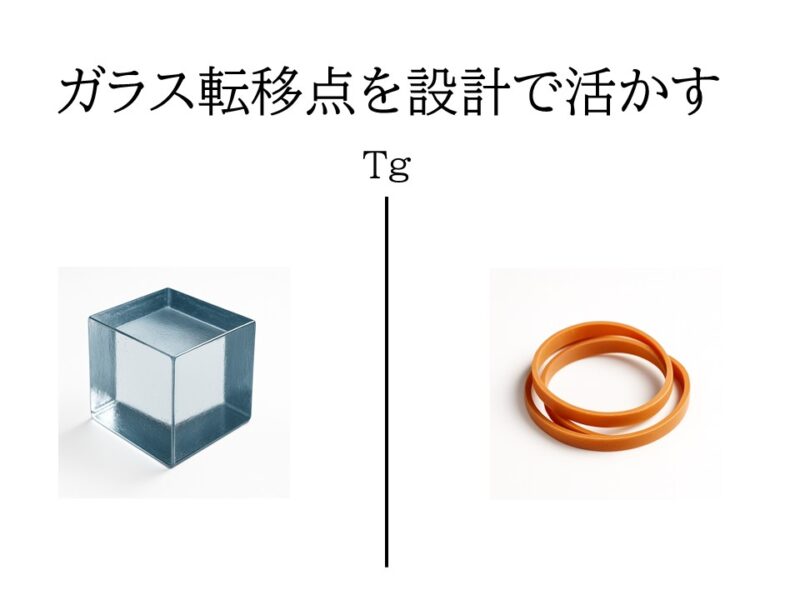
プラスチック部品の設計において、材料の耐熱性を評価する指標は数多く存在しますが、中でも「ガラス転移点(Tg)」は、設計トラブルの発生を未然に防ぐための重要な鍵となります。しかし、その数値だけを記憶し、特定の温度指標としてのみ捉えるだけでは不十分です。Tgの本質は、材料の物理状態が劇的に変化する「転移領域」を示すことにあり、その挙動を深く理解し、設計に反映させることが不可欠です。府中プラは、単なる数値の暗記ではなく、Tgを実務で「活かす」ための視点こそが、信頼性の高い製品開発に繋がると考えます。本コラムでは、実践的な安全マージンの設定、具体的な用途に応じた材料選定、そして失敗事例に至るまで、設計者が本当に知るべきTgの活用法を解説します。
設計における安全マージン設定の考え方
Tgを単なる上限温度ではなく、物性変化が始まる「領域」の入り口と捉え、適切な安全マージンを設定することが、長期的な信頼性を確保する上で極めて重要です。
Tg−10〜20℃を基準とする理由
実務的な経験則として、無荷重または低荷重下での長期使用温度上限は「Tg−10℃~20℃」を目安とすることが一般的です。これは、Tgに近づくにつれて、目に見えないレベルで高分子鎖の運動が活発化し、「応力緩和」や「クリープ」といった時間依存の変形が顕著になるためです。応力緩和とは、一定のひずみを与えた状態で応力が時間と共に低下する現象で、嵌合部の保持力低下などに直結します。クリープは、一定の荷重下でひずみが時間と共に増大する現象です。
Tgより十分に低い温度域ではこれらの現象は緩やかで安定していても、Tg近傍では急激に進行します。たとえ短時間では問題なくとも、長期間の使用で変形や機能不全に至るリスクが飛躍的に高まるのです。この10〜20℃というマージンは、こうした予測が難しい長期的リスクを回避するための、実用的な知見に基づくバッファと言えます。
荷重条件別マージン設定例
安全マージンは、部品にかかる荷重の大きさと種類によって調整する必要があります。
無荷重・低荷重下(例:外装カバー、表示パネル):主に成形時に発生した残留応力の解放による反りや歪みが懸念されます。この場合、「Tg−20℃」程度を目安とします。
中断続的な荷重下(例:スナップフィット、圧入嵌合部):応力緩和による嵌合力低下やガタつきを防ぐことが最重要課題です。マージンを大きくとり、「Tg−30℃」以上、あるいはそれ以上の余裕を持たせることが望ましい設計です。
継続的な高荷重下(例:ギア、軸受、構造部材):この領域ではTgだけでなく、クリープ特性や疲労特性そのものを評価する必要があります。Tgはあくまで初期的なスクリーニング指標とし、材料メーカーが提供する詳細な機械的データに基づいた設計が求められます。
温度軸上でのTg・HDT位置関係図
材料の耐熱性を考える上で、TgとHDT(荷重たわみ温度)の関係を理解することは重要です。非晶性樹脂と結晶性樹脂では、その関係性が大きく異なります。
非晶性樹脂(例:PC, PMMA):Tg近傍で急激に剛性が低下するため、HDTはTgより少し低い温度に位置します。HDTが短期的な耐熱変形温度の目安として機能しやすい傾向があります。
結晶性樹脂(例:PA66, POM):Tgを超えて非晶部分がゴム状態になっても、融点(Tm)まで存在する結晶部分が骨格として剛性を維持します。そのため、HDTはTgよりはるかに高い温度を示します。PA66ではTgが約50℃(乾燥時)に対し、HDTは200℃を超えることもあります。この場合、Tgは耐熱性の上限ではなく、吸湿による物性変化や、寸法安定性、衝撃特性が変化し始める温度として捉えるべきです。
用途別のTg活用型材料選び
製品の要求特性に応じて、Tgを基準とした材料戦略を立てることが有効です。ここでは、主要なエンプラのTgを比較しながら、用途に応じた材料選びの考え方を示します。
寸法安定性重視(高Tg材)

光学部品や精密機器の筐体など、温度変化に対する寸法安定性が最優先される用途では、使用温度範囲の最高温度よりも十分に高いTgを持つ材料の選定が絶対条件です。PEI(Tg≈217℃)、PES(Tg≈225℃)、PPSU(Tg≈220℃)といったTgが200℃を超える非晶性のスーパーエンプラは、広い温度域で硬質なガラス状態を維持するため、低クリープ性と高い寸法精度を発揮し、信頼性の高い設計を可能にします。
低温靭性重視(低Tg材)

寒冷地で使用される携帯端末や電動工具のハウジングなど、低温環境下での耐衝撃性が求められる場合、逆転の発想が求められます。使用温度が材料のTgを下回ると、材料は硬く脆くなる「低温脆化」を起こしやすくなります。そのため、想定される最低使用温度よりも低いTgを持つ材料が有利となります。例えば、ABS樹脂が低温でも粘り強さを保てるのは、ゴム成分であるポリブタジエンのTgが-80℃前後と非常に低いためです。この低温のTgが、冬場の屋外のような環境でも衝撃エネルギーを吸収する能力を付与しているのです。
結晶性樹脂のTgとTmを両立した判断

ギアや摺動部品、高温環境下で使用される機械部品など、強度、耐熱性、耐摩耗性が総合的に求められる用途では、結晶性樹脂が多用されます。この場合、非晶部分の挙動を示すTgと、結晶構造が失われる融点(Tm)の両方を考慮する必要があります。Tgを超えると剛性は若干低下しますが、Tmまでは結晶部分がその強度を支えます。したがって、「使用温度 < Tg」でなくとも、「Tg < 使用温度 < Tm」の範囲で実用可能なケースが多く、その温度域での剛性(弾性率)やクリープ特性を個別に評価することが重要になります。
主要エンプラTg比較と用途例
以下に主要なエンジニアリングプラスチックの代表的なTgと、その特性を活かした用途のマッピング例を示します。
| 材料名 | 代表的なTg(℃) | 位置づけ | 主な用途例 |
| PC (ポリカーボネート) | 約145-150 | 高Tg・高透明性・耐衝撃性 | 保護メガネ、ヘルメット、DVD基板 |
| 変性PPE (変性ポリフェニレンエーテル) | 約100-140 | 中〜高Tg・寸法安定性・低吸水性 | OA機器筐体、アダプターケース |
| PA66 (ポリアミド66) | 約50 | 低Tg・高Tm・強靭性・耐摩耗性 | 工業用ギア、高荷重コネクタ、ファスナー |
| POM (ポリアセタール) | 約-50 | 低Tg・高Tm・耐摩耗性・耐疲労性 | ギア、ベアリング、ローラー部品 |
| PET (ポリエチレンテレフタレート) | 約70-80 | 中Tg・高Tm・機械的強度・電気特性 | 容器、電気・電子部品 |
| PBT (ポリブチレンテレフタレート) | 約40-60 | 低Tg・高Tm・寸法安定性・電気特性 | コネクタ、スイッチ部品、リレーケース |
| PPS (ポリフェニレンサルファイド) | 約90-120 | 中Tg・高Tm・高耐熱・耐薬品性・難燃性 | ポンプ部品、インペラ、センサー部品 |
| PEI (ポリエーテルイミド) | 約217 | 超高Tg・高耐熱・難燃性・寸法安定性 | 航空機内装部品、医療機器部品、高周波コネクタ |
| PEEK (ポリエーテルエーテルケトン) | 約143 | 高Tg・超高Tm・最高レベルの耐熱・耐薬品性 | 半導体製造装置部品、分析機器部品、医療インプラント |
Tgを見誤った設計事例と対策
最後に、Tgの評価を誤ったために発生する典型的な不具合事例と、それを回避するための設計上のポイントを解説します。
嵌合力の低下
常温ではしっかり固定されていた圧入部品やスナップフィットが、高温になる機器の内部や、屋外に設置される装置内などに長時間置かれた後、ガタついたり外れたりする不具合は、Tgの理解不足に起因する典型例です。これは、部品を変形させて生じさせた反発力(応力)が、使用温度がTgに近づくことで急激に失われる「応力緩和」という現象が原因です。このトラブルを回避する設計判断のポイントは、設計段階で最大使用温度に対し、材料のTgが十分なマージン(例:30℃以上)を確保できる材料を選定することに尽きます。特に継続的な荷重がかかる嵌合部では、応力緩和特性データをメーカーに確認することが極めて有効な対策となります。
寸法狂い・反り
成形直後は問題なかった部品が、輸送中や使用中に、特に高温に晒された後で反ったり寸法が変化したりして、組み立て不良や機能不全を起こすことがあります。これは、成形時の不均一な冷却によって内部に蓄積された「残留応力」が、使用温度がTgに近づく、あるいは超えることで解放され、変形として現れるためです。これを防ぐには、使用温度がTgを超えない材料を選定することが大原則となります。もし、やむを得ずTg近傍で使用する場合は、成形後にアニール処理(熱処理)を行い事前に残留応力を除去・低減させる対策や、設計段階で肉厚を均一化し残留応力が発生しにくい形状とすることが重要です。
低温脆化
屋外の制御盤ボックスなどに汎用ABS樹脂を使用し、冬季の低温環境下で落下などの衝撃により容易に破損してしまうケースも、Tgの多面的な性質を見誤った例と言えます。材料の靭性は、その使用温度がTgを上回っているか下回っているかに大きく依存します。ABS樹脂の耐衝撃性を担うゴム成分のTgは非常に低いですが、それでも極寒冷地などそのTgに近づく環境下では衝撃エネルギーを吸収しきれずに脆性破壊を起こします。この回避策は、想定される最低使用温度を明確にし、その温度域でも十分な靭性を発揮できる材料(低温衝撃性に優れたPC/ABS、共重合PCなど)を選定することです。Tgは高温側だけでなく、低温側の靭性が変化する重要な指標でもあると認識し、両側面から物性を確認する設計習慣がトラブルを回避します。
まとめ
ガラス転移点(Tg)は、単一の耐熱温度を示す点ではなく、材料の長期的な挙動を予測するための重要な「予測指標」です。府中プラは、このTgという指標を正しく理解し、設計段階で適切な安全マージンを確保することが、市場でのトラブルを未然に防ぐ最善策であると考えます。
製品の用途や求められる性能に応じて、時には高いTgを、時には低いTgを戦略的に活用する視点が求められます。材料選びに迷った際は、本コラムで示したようなTg比較表を頭に描き、材料全体の特性を俯瞰することで、より的確な判断が可能になるでしょう。
関連コラム
>>ガラス転移点(Tg)を理解する:耐熱性・靭性・寸法安定性の設計指標とは
「その材料選定、本当に大丈夫ですか?」
Tgの理解不足による嵌合力低下・寸法狂い・低温脆化…
よくある設計トラブルの原因と回避策を凝縮。
今すぐ 「設計に効くガラス転移点(Tg)完全活用ガイド」 をダウンロード!
本コラムの内容は、射出成形における材料選定の参考情報として提供するものであり、特定の設計や製造条件下での性能や適合性を保証するものではありません。本コラムに記載された内容は、作成時点での情報に基づいていますが、その正確性や完全性についていかなる保証も行いません。また、予告なく内容を変更する場合があります。本コラムの情報により発生したいかなる損害(直接的、間接的を問わず)についても、弊社は一切の責任を負いかねます。最終的な材料選定や設計に関する判断は、必ずお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。具体的な材料選定については、当社までお問い合わせください。