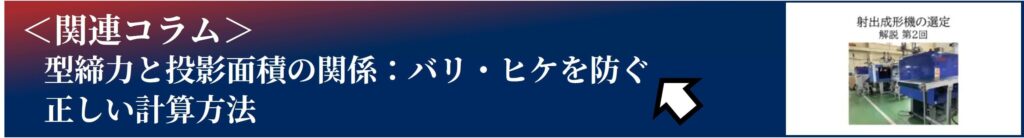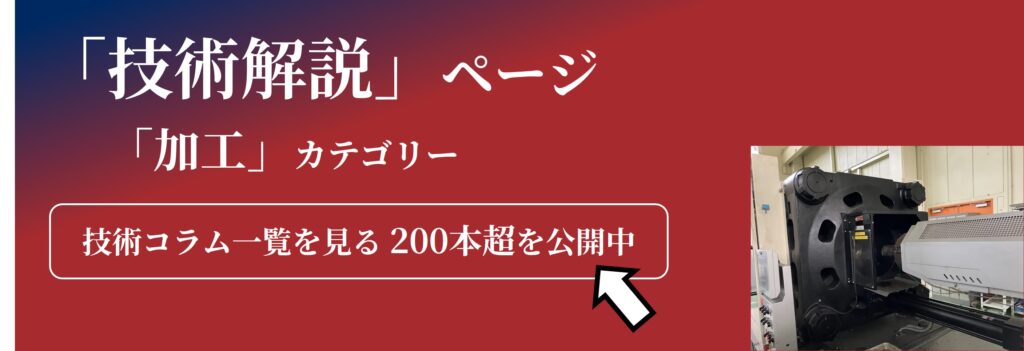成形機サイズの決め方:製品重量・投影面積・型寸法から総合判断する方法
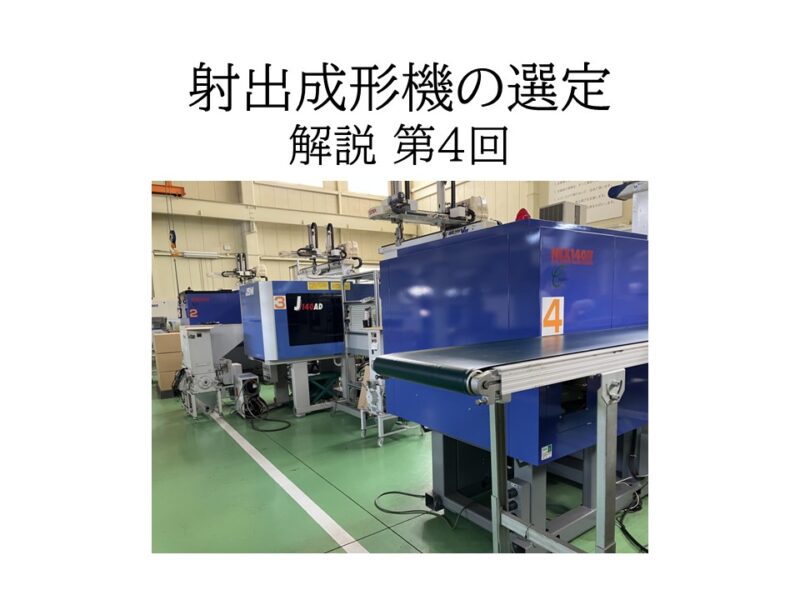
「射出成形機の選定」シリーズコラム第4回
射出成形機のサイズ選定は、製品設計や調達の段階で企業が頻繁に直面する重要な課題の一つです。この選定が適切でない場合、様々な問題が発生します。例えば、成形機が小さすぎれば、必要な型締力や射出容量が不足し、バリ、ショートショットといった成形不良や金型の破損リスクに直結します。一方で、必要以上に大きな成形機を選定してしまうと、設備投資コストの増大はもちろんのこと、運転時の電力消費量増加や材料の無駄な滞留による劣化など、ランニングコストの増大を招きます。
このように、成形機のサイズ選定は、製品の品質、生産効率、そしてコストパフォーマンスに大きな影響を与えるため、複数の指標を総合的に判断することが不可欠です。本コラムでは、射出成形機の適正サイズを決定するための、製品重量、投影面積、型寸法といった主要な要素を総合的に判断する方法について解説します。
成形機サイズ選定の基本的な考え方
射出成形機のサイズ選定において、単に成形機の「トン数」(型締力)だけで判断することは不十分です。最適な成形機を選定するためには、成形する製品の「製品重量」、金型が受ける「投影面積」から導かれる「型締力」、金型に充填される樹脂量である「ショットサイズ」、そして「金型の物理的な寸法」といった多岐にわたる要素をバランス良く確認し、総合的に判断する必要があります。
成形機の選定は、以下のステップで進めることで、見落としなく最適な判断を下すことができます。
1. 製品重量とランナー重量から必要ショットサイズを確認する。
2. 製品とランナーの投影面積から必要型締力を算出する。
3. 金型の物理的寸法が成形機に適合するかを確認する。
4. これらの情報を総合し、成形機を選定する。
製品重量とショットサイズの確認
射出成形機の選定において、まず考慮すべきは、成形する製品の重量と、それに付随するランナーの重量を合計した「必要ショットサイズ」です。この必要ショットサイズは、選定する成形機の「シリンダー容量」に対して適切な比率(一般的に60%〜80%が目安)に収まっているかを確認することが重要です。
必要ショットサイズ(g) = 製品重量(g) + ランナー重量(g)
ショットサイズ適合率(%) = (必要ショットサイズ ÷ シリンダー容量) × 100
もしショットサイズがシリンダー容量に対して不足している場合(例:60%を下回る)、シリンダー内での樹脂の滞留時間が長くなり、樹脂の熱劣化やガス焼け、変色といった不良が発生しやすくなります。逆に、必要ショットサイズがシリンダー容量に対して過大である場合(例:80%を上回る)、計量行程が不安定になったり、最悪の場合、金型への樹脂充填が不十分となる「ショートショット」が発生したりする可能性があります。ショットサイズの詳細な計算方法や不適合時に発生する不良については、「ショットサイズとシリンダー容量の決め方|不足で起きる不良と対策」の記事で詳しく解説しています。
投影面積と型締力の関係
次に重要なのは、成形品の「投影面積」から算出される「必要型締力」です。投影面積とは、射出方向から見た成形品とランナーの合計断面積であり、この面積に金型内部にかかる樹脂圧(型内圧)を乗じることで、金型が押し開こうとする力、すなわち必要な型締力を算出します。
必要型締力(t) = 投影面積(cm²) × 型内圧( kg/cm ²) / 1,000 × 安全率
選定する成形機のカタログスペックに記載されている型締力が、この算出された必要型締力に対して十分な余裕を持っているかをチェックする必要があります。型締力が不足すると、金型のパーティングラインから樹脂が漏れ出す「バリ」が発生し、製品の品質を損ないます。一方で、過剰な型締力は、金型への不必要な負荷やエネルギーの浪費につながる可能性があります。バリやヒケの防止といった観点から、適正な型締力の設定は極めて重要です。詳細な計算方法やトラブル対策については、「型締力と投影面積の関係|バリ・ヒケを防ぐ正しい計算方法」の記事で解説しています。
型寸法と成形機仕様の適合性
製品重量、ショットサイズ、型締力といった成形能力に関する指標だけでなく、金型の物理的な寸法が成形機の仕様に適合しているかを確認することも非常に重要です。

タイバー間隔:金型が成形機のタイバー(金型を取り付けるための支柱)間に物理的に収まるかを確認します。金型が大きすぎてタイバー間に収まらない場合、その成形機は使用できません。
型厚:金型の厚みが、成形機の型厚調整範囲(最小型厚〜最大型厚)に収まっているかを確認します。成形機は設定可能な金型の厚みに制限があります。
型開閉ストローク・エジェクタストローク:成形品を金型から取り出すために必要な金型の開く距離(型開閉ストローク)や、突き出しピンが移動する距離(エジェクタストローク)が、成形機の対応範囲内であるかを確認します。特に、深底容器のような成形品や、ロボットによる製品取り出しを行う場合には、十分なストロークが確保されていることが不可欠です。
特に大型金型や多数個取り金型を使用する場合、これらの型寸法の適合性は成形機選定の決定的な要因となります。
実務での総合判断ポイント
上記に挙げた各要素に加え、実務においては以下の点も総合的に考慮して判断を下すことが推奨されます。
材料特性による型内圧の違い:非晶性樹脂(例:PC、ABS、PS)と結晶性樹脂(例:PPS、PA、POM)では、流動性や固化特性が異なるため、必要とされる型内圧の目安も変動します。使用する材料の特性を理解し、適切な型内圧を見積もることが重要です。
成形機の過大選定による問題:必要以上に大きな成形機を選定すると、初期設備投資だけでなく、運転時の電力消費が増加し、単位製品あたりの成形コストが増大します。また、シリンダー容量が過大になることで樹脂の滞留時間が増え、劣化リスクも高まります。
将来的な拡張性:一方で、現在の生産計画にぎりぎりの成形機を選定しすぎると、将来的な金型変更(例:製品の大型化、多数個取り化)や、別の製品への対応が困難になるケースも考えられます。ある程度の余裕を持たせるか否かは、今後の事業計画と照らし合わせて判断すべきです。
部門間の連携:最適な成形機選定は、開発部門(製品・金型設計)、生産部門(成形条件・生産性)、調達部門(コスト・納期)といった関係各部門が情報を共有し、合意形成を行うことで実現されます。それぞれの立場からの視点を統合し、最もバランスの取れた判断基準を整理することが重要です。
まとめ
射出成形機のサイズ選定は、単一の指標に依存せず、「製品重量とショットサイズ」、「投影面積と型締力」、「型寸法と成形機仕様」という三つの主要な要素を総合的に判断して決定することが不可欠です。これらの複数条件を組み合わせて選定することで、成形不良の削減、金型寿命の延長、そして生産コストの最適化という多くのメリットを実現できます。本記事で解説した選定基準に加え、詳細な計算方法についてはシリーズコラム第3回「ショットサイズとシリンダー容量の決め方」、第2回「型締力と投影面積の関係」をご参照いただき、貴社の射出成形プロセス最適化にお役立てください。