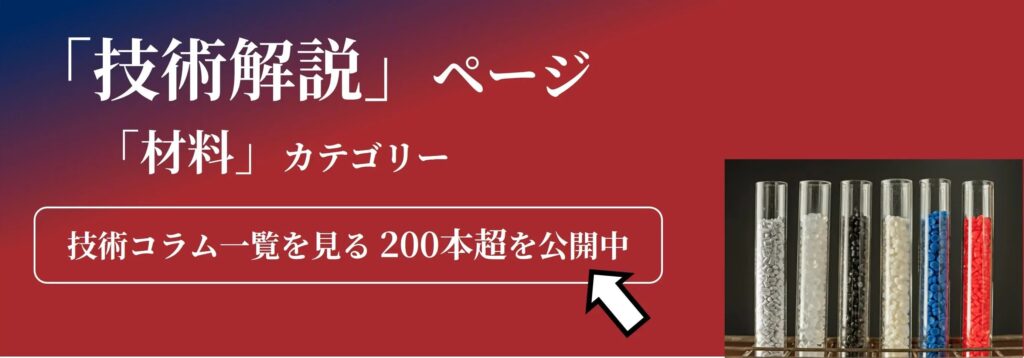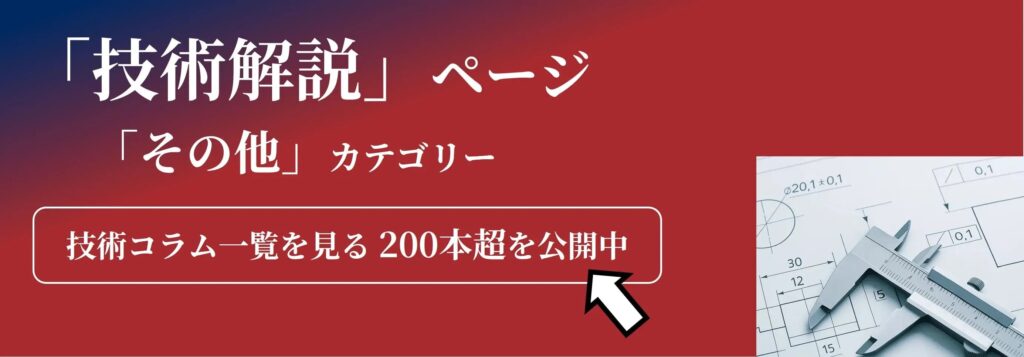射出成形摺動部品設計の『5大要素』─設計者が現場で押さえる摺動基礎
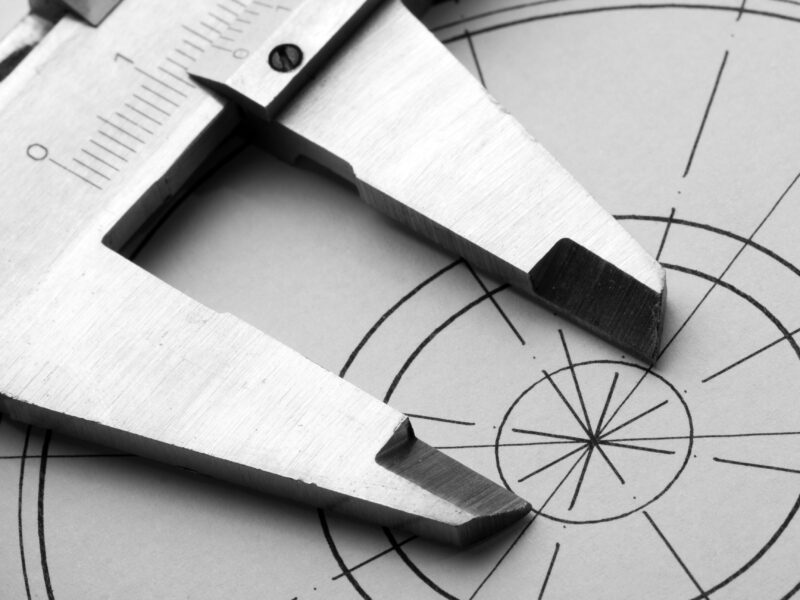
摺動部品の性能は、その寿命、発生する異音、必要とされるトルク、発熱量、さらには最終的なコストにまで直結します。射出成形によって作られる樹脂部品においてもこの点は同様であり、設計段階で摺動性を深く理解しておくことは、製品の信頼性や機能性を確保するために不可欠です。本コラムでは、まず基礎的な用語と現象を体系的に整理し、次回の評価試験法に関する理解へとつなげていきます。
摺動を支配する5要素
摺動現象は多岐にわたる因子によって支配されますが、府中プラでは特に重要な5つの要素に着目しています。これらの要素を理解することが、適切な設計への第一歩となります。
接触圧(面圧)
摺動面に加わる荷重は、接触する面積やその分布の違いによって圧力値が大きく変化します。設計意図に反する荷重集中が発生すると、局所的な摩耗の促進や早期の部品破壊につながる可能性があります。例えば、部品のミスアライメント(位置ずれ)や剛性不足は、接触する当たり位置を偏らせ、結果として摩擦係数や摩耗状態を悪化させる要因となります。均一な接触圧分布を実現する設計は、安定した摺動性能を維持するために極めて重要です。
速度
摺動する部品間の相対速度は、摩擦によって発生する熱量を決定づける主要な要因です。一般的に、高速域では潤滑油による油膜形成が効果的に機能しますが、エンプラを用いた摺動では、完全な流体潤滑状態に移行する例は少なく、ほとんどが境界潤滑の支配下にあります。速度が過度に高くなると、摩擦熱が急激に増加し、結果として溶着や損耗が急速に進行する危険性があります。そのため、使用環境における摺動速度を正確に把握し、材料が許容する範囲内で設計することが求められます。
相手材・粗さ
摺動相手材の表面粗さは、摺動挙動に顕著な影響を与えます。表面が粗すぎると、相手材の突起によって樹脂が削り取られる研磨摩耗が生じやすくなります。一方で、鏡面のように極端に平滑すぎると、潤滑油の保持性が失われ、スティックスリップ(摩擦面の固着と滑りの繰り返し)が誘発されることがあります。適切な表面粗さ、例えばRa値(平均粗さ)の範囲を特定し、それを設計要件として指定することが、部品の設計寿命を延長するための重要な鍵となります。
潤滑状態
摺動は、乾燥潤滑、境界潤滑、混合潤滑、流体潤滑の4つのモードで整理されます。射出成形された樹脂部品の場合、使用される領域の多くは境界潤滑から混合潤滑に分類されます。この領域では、樹脂自身の表面における転移膜の生成メカニズムや、樹脂中に配合されたフィラー(充填材)の種類と量が摺動特性に大きく作用します。適切な潤滑状態を維持するための設計、あるいは自己潤滑性の高い材料選定が、安定した性能に直結します。
環境
部品が使用される環境、具体的には温湿度や粉塵の有無は、摺動現象に大きな影響を及ぼします。例えば、ナイロンに代表される吸水性樹脂は、湿度によって摩擦係数や寸法が変動することが知られています。また、微細な粉塵が摺動面に堆積すると、二次的な研磨摩耗を助長する原因となります。さらに、薬品雰囲気下での使用を想定する場合には、樹脂材料の脆化も考慮に入れる必要があります。これらの環境因子を事前に評価し、適切な材料選定や設計対策を講じることが重要です。
基本用語の整理
摺動現象を理解し、設計に反映させるためには、関連する専門用語を正確に把握しておく必要があります。ここでは、特に重要な基本用語を簡潔に解説します。
摩擦係数 μ
摩擦係数には、静摩擦係数と動摩擦係数の2種類があります。静摩擦係数は、部品が動き始める際の初期抵抗、つまり「引っかかり」の度合いを示します。一方、動摩擦係数は、部品が一度動き出して定常状態に入った際の「滑らかさ」や「軽さ」に対応します。これら二つの係数を混同して解釈すると、起動時の特性と定常時の特性を誤って評価する可能性があります。両者の違いを理解し、それぞれの設計要件に応じて適切に評価することが重要です。
摩耗のタイプ
摩耗は、その発生メカニズムによっていくつかの主要なタイプに大別されます。
- 研磨摩耗: 相手材の硬い突起や摺動面に介在する異物によって、材料が削り取られる現象です。
- 凝着摩耗: 摺動面が局所的に接触し、熱や圧力によって一時的に溶着し、その後剥離を繰り返すことで材料が失われる現象です。
- 疲労摩耗: 繰り返し加わる応力によって、摺動面が疲労し、微細な粒子として剥離する現象です。
- フレッティング摩耗: 微小な振幅で繰り返し摺動運動が生じることにより、表面が破壊される現象です。
現場で観察される摩耗粉の色や形状は、どのタイプの摩耗が発生しているかを推定するための有効な手がかりとなります。
PV(面圧×速度)

PV値は、摺動面に加わる面圧と摺動速度の積で表される値であり、摺動系の限界設計指標として広く用いられます。このPV許容値を超えると、摺動部での発熱が急激に増大し、結果として溶着や焼付きといった深刻な問題に直結します。PPS(ポリフェニレンサルファイド)やPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)のような高耐熱性樹脂は、高いPV条件下でも性能を維持できる一方、汎用樹脂ではその限界値が小さい傾向にあります。適切な材料選定と設計によって、PV値を許容範囲内に収めることが重要です。
転移膜
特定の樹脂材料は、摺動中に相手材表面にごく薄い層を形成し、それが摩擦の低減に寄与することが知られています。この薄層を転移膜と呼びます。PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)やその改質樹脂、あるいはPEEKが、この転移膜形成能を持つ代表的な材料です。転移膜の発現は、使用環境条件や接触状態に強く依存するため、材料特性と使用条件の両面から検討する必要があります。この現象を理解し活用することで、自己潤滑性の高い摺動部品の設計が可能になります。
材料ごとの摺動特性
射出成形に用いられる主要な樹脂材料は、それぞれ独自の摺動特性を持っています。ここでは、府中プラでよく扱う材料の特性を簡潔にまとめます。
POM(ポリアセタール): 摩擦係数が低く、非常に安定している特徴があります。耐水性に優れており、水潤滑条件のような環境下でも比較的高い性能を発揮します。摩耗によって生じる摩耗粉は白色の粉状で、摺動部に残留しやすい傾向があります。
PA6/66/12/46(ポリアミド): 吸水性樹脂の代表格であり、吸水によって摩擦係数や寸法安定性が変動します。そのため、乾燥状態と湿潤状態での性能差への配慮が設計上必須となります。PA12やPA46は、他のポリアミドと比較して吸水による寸法変化が少なく、比較的安定した特性を示します。
PBT(ポリブチレンテレフタレート): 寸法安定性に優れているため、電装部品のギアなど、寸法精度が求められる用途に適しています。相手材の表面粗さを設計段階で適切に工夫することで、摺動寿命を効果的に向上させることが可能です。一方で、POMと比較すると融点は高いものの、ガラス転移点(Tg)が約40℃と常温域に近いため、非強化材で使用した場合には摺動挙動へ顕著な影響が現れるケースがあります。POMはTgが約-40℃と低く、かつ結晶化度が高いために常温領域での摺動特性が安定しやすいのに対し、PBTは条件によって性能変動が起こりやすい点に留意が必要です。
PPS/PEEK(ポリフェニレンサルファイド/ポリエーテルエーテルケトン): これらの高性能樹脂は、高温域や高PV条件といった過酷な環境下での使用に耐えることができます。相手材への表面処理と組み合わせることで、さらに優れた摺動性能を発揮する設計が有効に作用する場合もあります。
設計で“まず効く”チェックポイント
摺動部品の設計において、府中プラが特に重視する、効果的かつ実践的なチェックポイントを提示します。
面圧分散: 摺動面にかかる荷重を一点に集中させない設計は極めて重要です。接触幅の最適化、曲率の調整、リブの配置などを工夫することで、荷重を効果的に拡散し、局所的な高面圧による摩耗や破損のリスクを回避します。これにより、部品全体の耐久性を向上させることが可能です。
相手材粗さの指定: 摺動相手材の表面粗さは、摩耗と摩擦に大きな影響を与えます。適度なRa値を選定することでティックスリップの発生を抑制する効果が期待できます。過度な平滑化や粗化は避けるべきです。
デブリ排出: 摺動によって発生する摩耗粉(デブリ)が摺動面に堆積すると、それが研磨剤として作用し、摩耗を加速度的に進行させる原因となります。デブリが自然に排出されるような逃げ形状を設けることや、溝加工を施して粉詰まりを防ぐ設計は、長期的な安定稼働に貢献します。
剛性とクリアランス: 部品の剛性不足は、摺動面の不均一な接触や変形を引き起こし、スティックスリップを誘発する可能性があります。また、過度なクリアランス変動も同様の問題を引き起こします。必要最小限の剛性を確保し、かつ適切なクリアランス設計を行うことで、安定した摺動性能を維持できます。
成形条件由来の差: 射出成形条件は、樹脂部品の物性に影響を与え、それが摺動挙動にも波及します。例えば、結晶化度や分子配向の違いは、摩擦特性に影響を及ぼすことがあります。また、離型剤の残渣が摺動面に残留している場合、それが摩擦係数や摩耗挙動を変動させる要因となることもあります。成形条件を安定させ、設計意図通りの摺動性能を確保することが重要です。
まとめ
摺動性を深く理解するためには、単に数値的なデータに頼るだけでなく、基礎的な用語と現象を、実際に部品設計に影響を与える因子として体系的に整理することが不可欠です。面圧、速度、相手材粗さ、潤滑状態、そして環境という5つの要素が互いに複雑に作用し、摩擦係数や摩耗のメカニズムを決定します。これらの因果関係が見えるようになれば、経験や勘に頼るだけでなく、より科学的な視点から設計方針を立てることが可能となります。次回は、評価試験の適切な使い分けと、そこから得られる実データを設計判断へと転換するための具体的な視点について考察します。