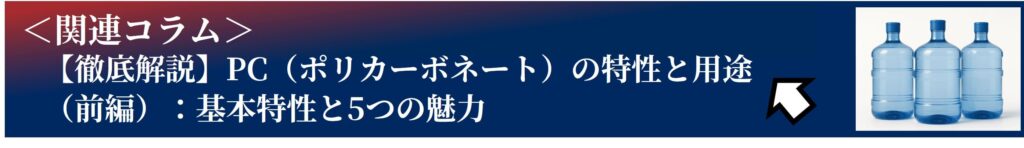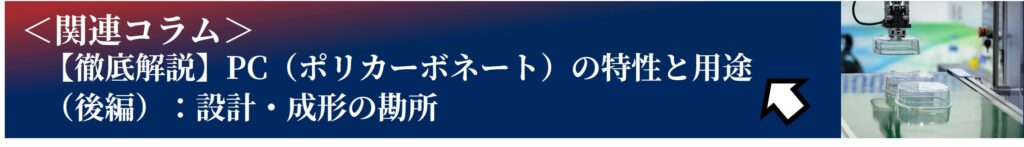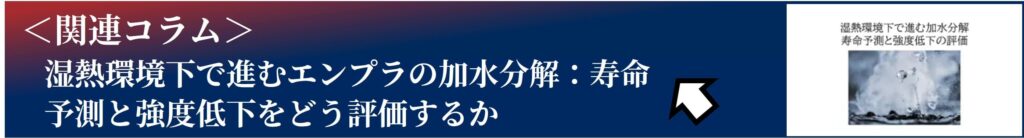PBT・PC・PAが加水分解で劣化する原因と防止策:設計・成形・材料選定の実践ガイド
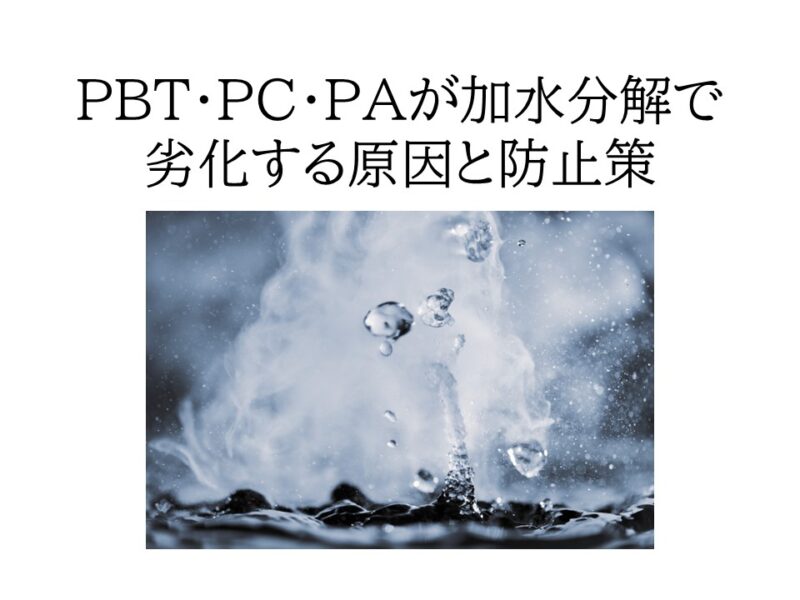
吸水と加水分解は異なる現象ですが、設計現場では加水分解による製品の破損トラブルが後を絶ちません。特に、PBT、PC、PAは耐熱性や機械特性に優れる一方で、加水分解の影響を受けやすい代表的な樹脂として知られています。
本コラムでは、これら3種類の樹脂における加水分解の進行メカニズムと、製品が破損する前に加水分解を防ぐための設計指針および材料選定のポイントについて解説します。
加水分解の原因とは?吸水との違いと劣化メカニズム
加水分解とは、水分子がポリマーの主鎖を切断し、それによって分子量が低下することで樹脂が脆くなり、最終的には破断に至る化学反応です。この反応は主に高温かつ高湿の条件下で進行し、特に80℃前後から反応速度が顕著になりやすい傾向があります。
吸水は水分子が樹脂内部に物理的に取り込まれる現象であり、乾燥によって元の状態に戻せる可逆的な変化です。しかし、加水分解は一度分子結合が切断されると元に戻らない不可逆的な化学変化であり、乾燥させても劣化が回復することはありません。
設計上のリスクとしては、温水が循環する機器の部品、医療分野でのオートクレーブ滅菌を受ける部品、屋外での使用により湿熱にさらされる部品など、湿熱ストレスの高い環境下で製品の寿命を大きく左右する要因となります。
PBT・PC・PAの加水分解特性を比較:分子構造と劣化しやすさの違い
各材料の分子構造の違いが、加水分解に対する感受性を決定します。
| 材料 | 主鎖構造 | 加水分解しやすさ | 特徴 |
| PBT | エステル結合 | 高 | 高温水や蒸気で急速に分解し、脆化や破断に直結します。 |
| PC | カーボネート結合 | 中 | アルカリ環境や熱水下で分解が進み、透明性や衝撃強度が低下します。 |
| PA | アミド結合 | 低~中 | 水素結合により構造が保持されますが、高温水下では連鎖切断が進行します。 |
PBT:ポリブチレンテレフタレート(PBT)は、その分子鎖中に多数のエステル結合を持っています。このエステル結合が水分子の攻撃を受けやすく、加水分解が起こりやすい特性を持っています。一度加水分解が始まると、加水分解で生成する末端基がさらなる加水分解を助長しやすい(自己促進的)傾向が知られています。このため、PBTは高温水や蒸気の環境下で特に急速な劣化を示し、製品の脆化や破断に直接つながるリスクが高いです。
PC:ポリカーボネート(PC)の主鎖にはカーボネート結合が含まれています。PCはPBTほどではないものの、アルカリ性の洗浄液や高温の熱水にさらされると加水分解が進行する傾向があります。特に、医療機器などで用いられるオートクレーブ滅菌のように、高温高圧の蒸気に繰り返しさらされる環境では、透明性の低下(黄変)や衝撃強度の著しい低下が問題となります。透明性が製品の機能に直結する用途では、この黄変は大きな品質問題となります。
PA:ポリアミド(PA)はアミド結合を主鎖に持ち、分子間に形成される強固な水素結合によってその構造が保持されています。PAの吸水は、分子間に水分子が入り込み、分子鎖間の結合を弱めることで可塑化(柔軟化)を引き起こします。この現象は可逆的であり、乾燥させることで元の硬さに戻ります。しかし、120℃を超えるような高温水環境下では、アミド結合そのものが水分子によって切断され、分子鎖が恒久的に短くなります。これにより樹脂の強度が不可逆的に低下し、製品の寿命が著しく短縮されます。
このように、同じエンプラと総称される樹脂であっても、その分子構造におけるどの結合が水分子の攻撃を受けやすいかによって、加水分解による劣化の度合いや進行メカニズム、そして最終的な製品寿命が大きく異なります。材料を選定する際には、使用環境における水との相互作用を分子レベルで理解することが不可欠です。
使用環境別の加水分解トラブル事例(温水・滅菌・流体制御部品)

加水分解によるトラブルは、使用環境の特性と密接に関連しています。
温水ポンプ/給湯器部品(PBT):温水ポンプや給湯器の部品にPBTが使用された場合、数年という比較的短い期間で亀裂や破断に至るトラブルを耳にすることがあります。PBTは吸水率が比較的低い特性を持つため、「水に強い」と誤解されがちです。しかし、前述の通り、高温の水環境下ではエステル結合が急速に加水分解を受け、たとえ吸水量が少なくても分子量の低下が進行し、脆化してしまう典型的な事例です。

医療機器(PC):医療機器、特に繰り返し滅菌処理が必要な器具にポリカーボネート(PC)が用いられる場合、オートクレーブ滅菌(一般的に121℃、20分間の飽和水蒸気処理)を数十回繰り返すことで、脆化や黄変といった劣化が生じます。PCは耐衝撃性に優れるため、医療分野で広く使われますが、オートクレーブ滅菌の回数管理が製品の安全性と機能維持のために不可欠となります。滅菌回数が増えるほど、加水分解による劣化が進行し、最終的には破損に至るリスクが高まります。

流体継手/バルブ(PA66):流体を扱う継手やバルブの部品にポリアミド66(PA66)が使用される場合、吸水による寸法変化だけでなく、高温水にさらされることで加水分解が同時に進行することがあります。PAは吸水によって寸法が膨潤する特性がありますが、100℃超の加圧熱水または120℃級の高温蒸気環境下では、条件によってアミド結合の切断が進むことがあります。この物理的変化と化学的劣化の複合作用により、寸法精度が低下し、液漏れなどのリーク不良を引き起こすことがあります。
これらの事例に共通するのは、まず吸水が先行し、樹脂内部に水分が滞留することです。その状態で高温や応力といった条件が加わることで、加水分解へと進行します。つまり、「物理的な吸水」と「化学的な劣化」は連鎖的に発生する現象であり、これらを個別の事象として捉えるのではなく、互いに関連し合う一連のプロセスとして総合的に評価することが重要です。吸水率が低いからといって、加水分解のリスクがないとは限らない点を理解する必要があります。
加水分解を加速させる3条件:成形残留水分・高温高湿・応力集中
加水分解を加速させる主要な要因は、成形時の材料の状態、使用環境、そして製品に加わる応力の三つです。これらが複合的に作用することで、劣化が突発的に進行することがあります。
成形時の水分残留

プラスチックペレットが水分を含んだ状態で加熱・溶融されると、成形加工中に既に加水分解が始まってしまいます。これは、溶融状態のポリマーが水分子と反応しやすいためです。成形前に適切な乾燥処理を施さないと、製品が市場に出る前から劣化が進行している状態となり、初期不良や早期の破損につながるリスクが高まります。
対策として、府中プラではPBTであれば120℃で4時間、PCであれば120℃で3時間、PAであれば80℃で5時間程度の事前乾燥を目安としています。これらの乾燥条件は、材料メーカーの推奨する乾燥条件を参考に、材料の特性や要求される製品品質に応じて調整する必要があります。
高温高湿環境
加水分解の反応速度は、温度と湿度に大きく依存します。特に60℃から90℃の温度域では、常温と比較して反応速度が桁違いに加速することが多く、場合によっては十倍以上となることもあります。高い湿度が加わることで、水分子がポリマー主鎖に接近しやすくなり、反応がより一層促進されます。
設計の初期段階で、製品が使用される温度と湿度を想定し、加水分解のリスクを評価することが不可欠です。例えば、屋外で使用される製品や、温水・蒸気にさらされる環境下では、耐加水分解性に優れた材料を選定するか、あるいは加水分解を抑制する構造設計を考慮する必要があります。
残留応力・応力集中部位
成形時に発生する残留応力や、リブの根元、ボスの基部、急激な肉厚変化部などの応力集中部位は、加水分解による化学的劣化を著しく促進します。これは、応力が加わっている部位ではポリマー鎖間の結合が緩み、水分子が侵入しやすくなるためです。また、ケミカルアタック(環境応力亀裂、ESC)との相乗効果により、非常に短期間で製品が破損に至るケースもあります。
設計段階で、成形時の残留応力を低減するようなゲート位置や冷却条件の検討、および応力集中を避けるためのフィレット(R形状)の適切な設定が重要です。特に、繰り返し荷重や振動が加わる部位では、応力集中による加水分解リスクを低減するための工夫が不可欠です。
これら3つの条件、すなわち「成形時の水分残留」、「高温高湿環境」、「残留応力・応力集中」が同時に、または複合的に重なり合うと、“加水分解の臨界点”を超え、製品が突発的な破断に至る可能性が非常に高まります。この臨界点を超える前に、各条件への対策を講じることが、長期信頼性の確保には不可欠です。
加水分解を防ぐ対策まとめ:材料選定・設計・成形条件の最適化
加水分解による劣化を防ぐためには、材料選定、設計上の工夫、そして成形・使用管理の三つの側面から総合的にアプローチすることが重要です。
材料選定
加水分解のリスクを低減するための第一歩は、適切な材料を選定することです。

耐加水分解グレードの選定:各樹脂メーカーからは、加水分解安定剤が添加されたPBT、加水分解に強い特性を持つPC、半芳香族PA(PA6T、PA9Tなど)といった、耐加水分解性能を向上させた特殊グレードが提供されています。これらを優先的に検討することで、使用環境下での製品寿命を延ばすことが期待できます。
上位代替候補の検討:高温高湿環境下での要求性能が特に厳しい場合は、PPS(ポリフェニレンサルファイド)、LCP(液晶ポリマー)、PEI(ポリエーテルイミド)、PES(ポリエーテルサルホン)といった、より耐熱性・耐薬品性に優れたスーパーエンプラを上位代替候補として検討します。これらの材料は、一般的に加水分解に対する耐性が高く、苛酷な環境下での使用に適しています。
設計上の工夫
製品の形状や構造を工夫することも、加水分解対策として非常に有効です。
水が滞留しない形状:製品内部や表面に水が滞留する箇所があると、その部分で加水分解が促進されます。水や結露がスムーズに排出されるような排水構造、あるいはエア抜き構造を設けることで、水分が滞留するリスクを低減します。
防湿設計:外部からの水分侵入を物理的に遮断する設計も重要です。パッキンを一体化させた構造や、Oリングを適切に設置することで、製品内部への湿気の侵入を防ぎ、加水分解の発生を抑制します。
応力集中を避ける:前述の通り、応力集中部位は加水分解を加速させます。リブやボスの基部には十分なフィレットを設け、急激な肉厚変化を避けるなど、応力集中を緩和する設計を心がけます。これにより、加水分解による亀裂発生のリスクを低減できます。
成形・使用管理
成形工程から製品の使用段階に至るまで、適切な管理を行うことが加水分解対策の最終的な鍵となります。
乾燥の徹底とホッパー内再吸湿防止:成形前のペレット乾燥は加水分解対策の基本です。指定された条件で十分に乾燥させるだけでなく、乾燥後のペレットが再吸湿するのを防ぐために吸引式の搬送システムを採用するなど、府中プラでは適切な管理を行っています。
成形直後の急冷・高湿保管の回避:成形直後の製品を急激に冷却したり、高湿な環境で保管したりすると、残留応力が発生しやすくなったり、早期に吸水が進んだりする可能性があります。適切な冷却速度と、湿度が管理された環境での保管を心がけることが重要です。
まとめ
加水分解は、製品の内部で静かに進行し、ある日突然、脆化や破断という形で顕在化する「見えない分子レベルの破壊」です。PBT、PC、PAは、いずれも優れた特性を持つ一方で、湿熱環境下での劣化が顕著な代表的な材料であることを府中プラは認識しています。
この加水分解の防止には、成形前の乾燥の徹底、適切な構造設計、そして加水分解に強い材料選定という三つの柱が不可欠です。特に、「吸水性が低い=水に強い、安全である」という誤解を捨て去り、製品が使用される環境の温度、湿度、さらには部品にかかる応力を総合的に評価することが極めて重要です。材料の特性を深く理解し、「劣化を起こさないための設計思想」を持つことが不可欠だと考えています。