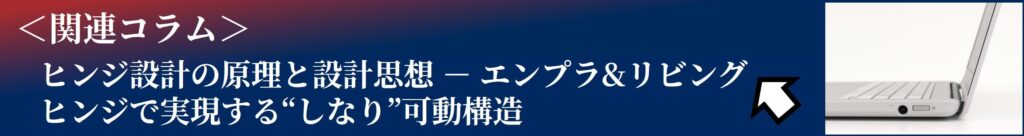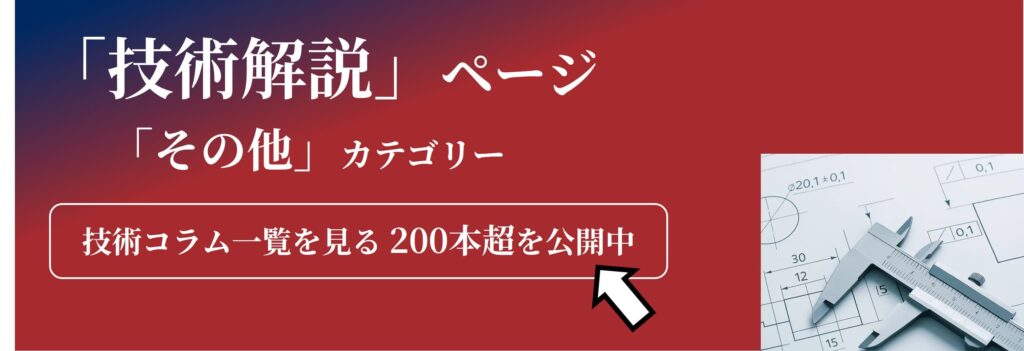金属ヒンジを置き換える高剛性エンプラ設計 - 軽量・一体化・コスト削減

これまでのコラムでは、可動部としてのヒンジ設計に焦点を当て、「柔軟に動かす」ための構造と材料の考え方を紹介いたしました。本コラムでは視点を転じ、ヒンジを支える構造側(固定部・支持部)の設計を取り上げます。近年、金属ヒンジや金属フレームといった構造部材をエンプラで代替する動きが加速しています。高剛性エンプラの進化により、かつては金属でしか実現できなかった構造部を樹脂で一体化できるようになり、製品の軽量化・コスト低減・組立性向上に大きく寄与しています。本コラムでは、その設計思想と適用部品の考え方を府中プラの視点から解説いたします。
金属代替が進む背景

樹脂による金属代替は、単なる材料の置き換えではなく、設計思想そのものの転換として進化を続けています。この動きが加速する背景には、以下の3つの主要な要因があります。
軽量化と操作性の向上
樹脂は金属の約1/3〜1/5という低い比重を持ちます。構造部を樹脂化することで、製品全体の質量を大幅に削減できるため、携帯性や取り扱いやすさが向上します。例えば、開閉機構や操作部の重心が改善され、よりスムーズで軽い操作感を実現できます。これは、家電製品、医療機器、産業機器など、幅広い分野において製品のユーザビリティ向上に直結する重要なメリットです。
一体化によるコスト削減

金属部品を使用する場合、通常はネジ止め、圧入、リベットなどの組立工程が必要です。これに対し、高剛性エンプラを活用して構造部を一体成形化することで、これらの組立工程を大幅に削減できます。部品点数が減ることで、部品管理や調達に関わるコストが低減されるだけでなく、組立工数の削減は製造全体の効率化とコストダウンに大きく貢献します。複雑な形状の部品も一体で成形できるため、設計の簡素化にもつながります。
高い設計自由度
エンプラは三次元形状の自由度が非常に高く、多様なデザインや機能を持たせた構造を一体で成形しやすい点が特徴です。例えば、ヒンジ、ボス、フレーム、補強リブなどの複数の機能を単一の部品として一体化させることができます。これにより、製品の小型化や省スペース化を実現しながら、より高度な機能を持たせることが可能になります。
高剛性エンプラ設計の考え方 ─ 強度よりも安定性
金属と樹脂では、剛性を確保する原理が根本的に異なります。金属が「強度の絶対値」で構造を支えるのに対し、樹脂は「応力分布と寸法安定性」で機能を成立させるという設計思想の転換が不可欠です。
応力を集中させない設計
金属の場合、部材の断面積を増やすことで強度を確保するという発想が一般的です。しかし、樹脂でこれを単純に模倣すると、肉厚の増加は成形収縮の不均一さや応力集中を招きやすくなります。樹脂の設計では、応力経路を滑らかに設計し、局所に力が集中しない構造を追求することが基本です。例えば、鋭利な角を避け、大きな曲率半径Rを付与することや、肉厚が急変する箇所に根元部のテーパー形状を設けることは、応力分散に非常に有効です。これにより、材料の持つ靭性を最大限に活かし、破損リスクを低減します。
成形時の流動方向を考慮
ガラス繊維などの強化材や樹脂分子鎖の配向方向は、構造物の剛性に大きく影響します。射出成形では、樹脂が金型内を流動する際にせん断応力を受けて分子が流動方向に配向し、強化繊維も流動方向に沿って配向する傾向があります。この配向方向が荷重の作用方向と一致するように設計することで、ねじりや曲げに対する耐性を効果的に高めることができます。ゲート位置の最適化や金型内の流動解析を通じて、構造部の強化したい方向に分子配向が揃うようにコントロールすることが重要です。
寸法安定性の確保
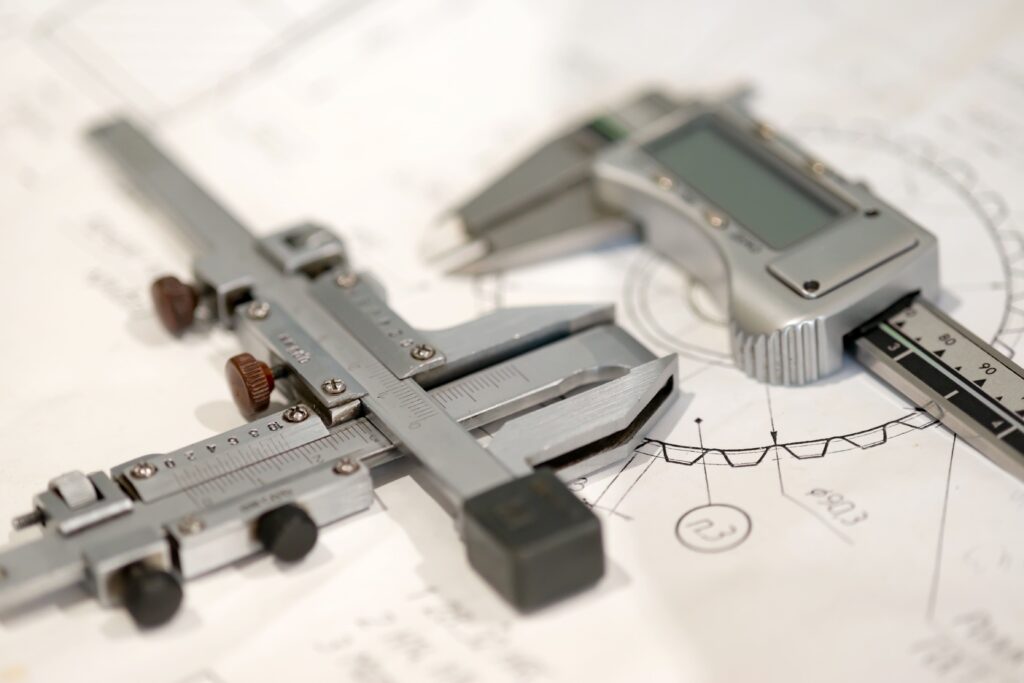
高剛性エンプラ、特に結晶性樹脂や強化材を多く含む樹脂は、成形後の反りや収縮が比較的大きく発生しやすいという特性があります。これらの変形は、製品の組立精度や機能に直接影響を及ぼすため、金型設計時に流動バランスや金型温度管理を最適化し、均一な冷却を実現することが不可欠です。金属代替設計においては、「強くする」という観点だけでなく、「成形後の変形を最小限に抑え、寸法安定性を確保する」という観点が、金属部品と同等の性能を実現する上でより重要になります。府中プラでは、こうした樹脂特有の挙動を考慮した総合的な設計アプローチを提供いたします。
材料選定の方向性
金属を樹脂で置き換える場合、要求性能に応じて適切な高剛性タイプのエンプラが選定されます。府中プラでは、以下の特徴を持つ材料に着目しています。
寸法安定性
金属代替で特に重要となるのが寸法安定性です。高剛性エンプラは、金属部品が使用されるような環境下でも、締結部や支点部において長期にわたり安定した性能を保持できる特性を持つ必要があります。例えば、高いガラス転移温度(非晶性樹脂)や融点(結晶性樹脂)を持ち、熱による変形や劣化が少ない材料が選ばれます。
吸水による寸法変化の抑制
高剛性エンプラは、吸水による寸法変化が小さいことも重要な選定基準です。PA等、吸水性のある材料では、湿度変化によって寸法が変動し、組立不良や、ヒンジなどの可動部の動作不良、残留応力の増大につながることがあります。そのため、繰り返し荷重がかかる部位や、高湿環境下での使用を想定する場合は、吸水率の低い材料を選定することが安定稼働に不可欠です。
ガラス繊維強化タイプの採用

金属代替を目的とする高剛性設計では、ガラス繊維や炭素繊維などの強化材を充填したエンプラが積極的に採用されます。これらの強化材は、樹脂の剛性、強度、耐熱性を飛躍的に向上させ、金属部品に匹敵する機械的特性を実現します。特に、ねじ保持力やクリープ特性(長期荷重下での変形抵抗)の向上に効果的です。このような材料は、従来の汎用エンプラでは難しかった「支持」、「締結」、「フレーム保持」といった構造的役割を担うことができるため、製品設計の可能性を大きく広げます。
樹脂化が進む代表的な構造部
高剛性エンプラの適用は、製品の様々な構造部で実用化が進んでいます。
ヒンジ支点部
金属軸やピン、ベアリングといった金属部品を排除し、筐体と一体でヒンジの支点部を成形する設計です。これにより、大幅な軽量化と組立工数の削減が実現できます。また、樹脂同士の摺動や弾性変形を利用するため、金属特有の作動音を低減し、静音性向上にも貢献します。
ねじ止めボス部
射出成形のみで高剛性かつ高強度のねじ止めボス部を形成する設計です。特にガラス繊維強化エンプラを用いることで、金属部品に匹敵するねじ保持力を実現し、部品点数と組立工程の削減に寄与します。
支持フレーム・補強リブ部
従来アルミダイカストや板金で構成されていた支持フレームや補強リブを、高剛性エンプラで代替し、射出一体化する設計です。これにより、部品点数を削減しつつ、複雑な形状を一度に成形できるため、設計自由度が向上します。
機構カバー・筐体部
複数の金属部品や汎用樹脂パーツを溶着や接着で結合していた機構カバーや筐体部を、高剛性エンプラで一体成形する設計です。外観と内部の機能を一体化することで、製品の剛性を高めつつ、組立性の向上とコスト削減を実現します。
これらの設計はいずれも、「部分的な金属代替」から、「構造全体の樹脂化」へと設計思想が進化していることを示しています。
まとめ
ヒンジや筐体を支える構造部をエンプラで設計することは、単なる軽量化手段ではなく、設計の合理化と一体化の象徴です。その成功の鍵は、応力を集中させない形状設計、寸法安定性を重視した金型・成形設計、材料特性を理解した部位ごとの使い分けを組み合わせることにあります。これにより、エンプラは金属を補うだけでなく、より高い自由度とコスト効率を実現できます。金属代替が可能なエンプラの種類は多数ございます。ご要望に沿った材料のご提案をいたしますので、ぜひ府中プラまでお気軽にご相談ください。るために、「肉厚」、「R」、「流動方向」、「材料靭性」の4要素を総合的に最適化することが不可欠であると考えます。これにより、白化・割れ・疲労破壊を防ぎ、長寿命な可動構造を実現することが可能です。府中プラは、成形条件と設計を一体で考える“ひずみ制御設計”の実践を通じて、お客様の製品における壊れないヒンジの量産化を支援しています。