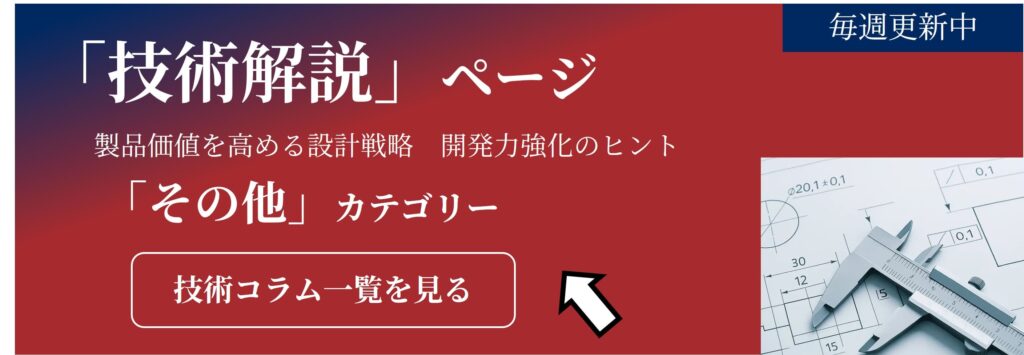反りを許容する設計 ― 反り(ソリ)ゼロを目指さない平面設計
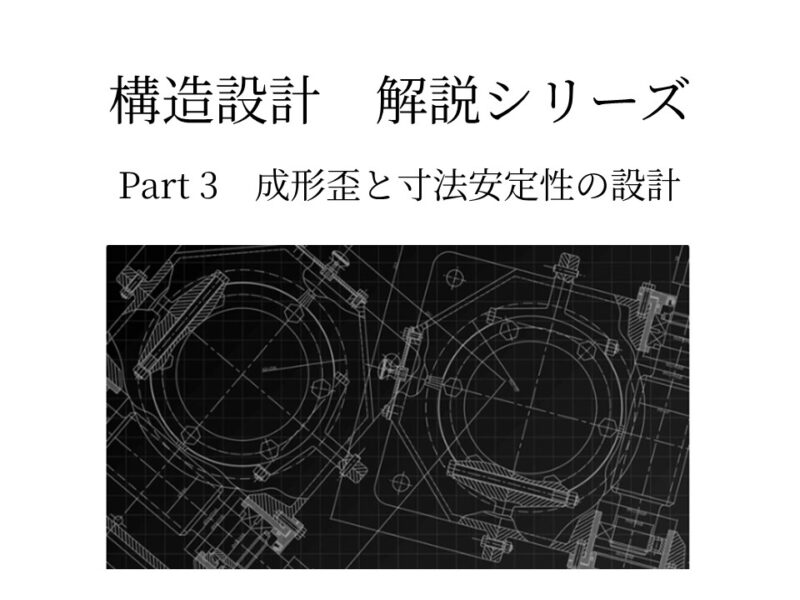
シリーズコラム第10回
射出成形部品における「反り」は、設計者を長らく悩ませてきた典型的な成形歪の一つです。現場で金型条件をいくら調整しても、反りが完全に消えることはありません。なぜなら、反りは成形上の「欠陥」ではなく、樹脂が冷却・固化する過程で生じる自然な収縮差が、形として現れた「現象」だからです。本コラムでは、“反りをゼロにする”という従来の発想から離れ、発生する反りを前提として許容し、制御下に置くための設計思想を解説します。目的は、「見た目の完璧な平面」ではなく、「機能として成立する平面」の実現にあります。
なぜ反りはなくならないのか ― 材料と構造の宿命
反りの発生は、射出成形という工法と材料の特性がもつ宿命とも言えます。その根本原因は、製品内外に存在する「非対称性」に集約されます。
反りの根本原因は「非対称」
反りは、部品内部で起こる収縮や応力の分布が、製品の左右や上下で均一でない場合に生じます。この不均一、すなわち非対称性を生む代表的な要因には以下のようなものがあります。
- 肉厚差による冷却速度差: 厚い部分は遅く、薄い部分は速く冷えるため、収縮のタイミングがずれて歪みが発生します。
- ゲート位置の偏り: 樹脂の充填経路が非対称になることで、流動末端までの圧力や温度の分布が不均一になります。
- ガラス繊維の配向異方性: 繊維強化樹脂では、繊維が流動方向に並ぶため、流れの方向と直交方向で収縮率が大きく異なり、反りを引き起こします。
- 金型温度の不均一: 金型の冷却回路の配置などにより、キャビティとコアで温度差が生じると、製品の表裏で収縮差が発生します。

このように、製品の形状、材料の特性、そして金型の構造に何らかの非対称性が存在する限り、反りの発生は避けられません。完全な平面を目指すことは、物理的に不可能と言えるのです。
結晶性樹脂は反りやすく、非晶性は反りにくい
材料の特性も反りの発生度合いに大きく影響します。
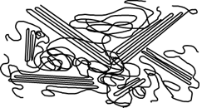
- 結晶性樹脂(PA、PBT、PPSなど): 溶融状態から固化する際に分子が規則正しく並ぶ「結晶化」が起こり、大きな体積収縮を伴います。このため分子配向と結晶化収縮の影響が相まって、反りが顕著に現れる傾向があります。
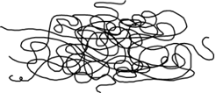
- 非晶性樹脂(PC、PMMAなど): 冷却時の収縮は比較的小さいですが、応力緩和が遅いため、発生した残留応力が解放されずに表面に蓄積しやすい性質を持ちます。
設計の初期段階で、使用する材料が「反りが出やすい性質か」、また「発生した反りが弾性変形の範囲内で元に戻るか(弾性復元性)」を理解しておくことが、適切な設計判断の前提となります。
反りを“なくす”ではなく“制御する”発想
反りをゼロにできない以上、私たちは発想を転換する必要があります。それは、反りを力で抑え込むのではなく、その発生を予測し、設計によって制御するという考え方です。
対称化だけでは限界がある
反り対策として「製品形状を左右対称にする」「ゲートを中央に配置する」といった手法がよく挙げられます。これらは反りを悪化させないための有効な基本原則ですが、反りの“発生を制御する”ための決定的な手段にはなり得ません。前述の通り、完璧に対称な成形プロセスは存在せず、これらの対策を施しても微小な反りは必ず発生します。重要なのは、「どの方向に」「どの程度」反るかを設計段階である程度予測し、その変形を許容できる設計に落とし込むことです。
許容設計とは「反りを吸収する構造を作る」こと
反りは、製品を変形させようとする“動く力”です。この力を剛性の高い構造で無理に止めようとすると、エネルギーの逃げ場がなくなり、内部応力として蓄積され、最終的には割れや意図しない歪みを誘発します。そこで、反りの力を吸収し、解放するための構造を意図的に設ける「許容設計」が有効となります。
- 反り方向の分散: 大面積のパネルにおいて、補強リブを単純な格子状に配置すると一方向への反りを助長することがあります。リブを斜め方向や非対称に配置することで、反りの方向を分散させ、全体としての平面度を保ちます。
- 応力の解放: フランジ部を全周にわたって完全に固定すると、収縮による応力が集中します。締結箇所の一部を浮かせ構造(ルーズな固定)にすることで、応力の逃げ道を作ります。
- 収縮差の局所化: ボスの周辺は肉厚が変化し、収縮差が大きくなる箇所です。ボス周囲に微小なスリット(逃げ)を入れることで、その影響が製品全体に波及するのを防ぎ、影響を局所にとどめます。
これらはすべて、発生する力を無理に抑えるのではなく、巧みに解放し、製品全体への影響を最小化するための設計思想です。
機能基準での「平面性」評価
製品に求められる「平面」が、必ずしも幾何学的な平坦さを意味するとは限りません。多くの場合、重要なのは“機能面での接触性”や“組付け性”です。例えば、機器のカバーやハウジングは、部品全体が完全に平らでなくとも、勘合部やシール面、ネジ位置といった機能上重要な部分の寸法や位置関係が安定していれば、製品としての役割を果たします。したがって、設計の出発点は、図面上の厳しい平面度公差を追求することではなく、「製品機能としてどこを基準面とするか」、「どの程度の反りであれば許容できるか」を機能要求から逆算して定義することにあります。
反りを予測・制御する設計の具体指針
反りを制御するための、より具体的な設計アプローチをいくつか紹介します。
ゲート配置で収縮方向を“決める”
反りは、樹脂の流動方向に対して直交する方向に最も発生しやすい性質があります。この性質を利用し、ゲート位置を工夫することで、反りが発生する方向をある程度コントロールできます。例えば、長方形の製品であれば、中央付近にゲートを配置して流動経路を均等化することで、反りの方向を予測しやすくなります。複数ゲートを用いる場合は、樹脂が合流するウェルドラインの発生位置と、予測される反り方向との関係性を考慮して配置を決定することが重要です。
肉厚設計で収縮差を抑える
製品全体の肉厚を均一にすることは、反り対策の最も基本的なアプローチです。部分的に厚肉部が避けられない場合は、その裏面を肉盗みすることで、見かけ上の肉厚を均一化し、冷却の均一性を保ちます。特にガラス繊維強化樹脂などの高剛性材料では、反りを抑えるためにリブを高くしすぎると、かえってリブと本体との冷却時間差が増大し、反りを助長することがあります。リブ高さを必要最小限に抑えることも、収縮差を減らす有効な手段です。これらの調整は、反りの絶対量を減らすこと以上に、反りが発生する方向性を安定化させ、量産時の品質を揃える上で大きな効果を発揮します。
結晶性樹脂では“金型温度差”を設計で吸収
PBTやPA66といった結晶性樹脂は、金型のわずかな温度差にも敏感に反応し、顕著な反りとして現れます。金型の冷却経路を完全に均一にすることは現実的に難しいため、ある程度の温度差が生じることを前提とし、それを吸収できる形状を設計に組み込むことが現実的な対策となります。
- 事前反りの付与: 予測される反り方向とは逆向きに、あらかじめ製品形状に微小なR(反り)を付けておく手法です。これにより、成形後の収縮による反りと相殺させ、結果的に平面に近づけます。
- 形状による吸収: 製品の機能に影響しない範囲に、反りを吸収するためのスリットや段差を意図的に組み込み、変形をその部分に集中させて全体への影響を緩和します。
このように、成形条件のばらつきをゼロにできないことを前提とし、その影響を“形で逃がす”のが、量産を見据えた賢明な設計です。
設計段階で確認すべき反りリスク
反りを許容する設計アプローチでは、「どの程度の反りなら機能を損なわないか」という基準を、設計者自身が明確に持っておくことが何よりも重要です。設計レビューの際には、以下の点を自問自答することが求められます。
- 製品の機能上重要な面(機能面)と、意匠的な面(外観面)を分けて評価しているか?
- 固定箇所の拘束が過剰になり、収縮の逃げ場を奪っていないか?
- 補強リブの配置が、樹脂の自然な収縮方向を妨げるレイアウトになっていないか?
- 樹脂の流動方向に対して、特に反りが出やすいと予測される部位を把握しているか?
- 万が一、想定以上に反りが出た場合に、金型修正で対応できる余地を設計に残しているか?

これらの項目を設計の初期段階で明確にしておくことで、金型完成後のトライ・修正の回数を最小限に抑えることができます。
まとめ
反りは、成形プロセスから「消す対象」ではなく、その発生を前提として「設計で制御する対象」です。許容設計とは、避けられない反りを受け入れつつ、製品の機能上、何ら問題を生じさせない安定した構造をつくり込むことに他なりません。完璧な平面を追い求めるのではなく、“反りを想定した安定構造”を設計することで、量産における安定性と品質の再現性を両立させることが可能になります。
府中プラは、長年の成形現場で培った知見をもとに、反りを力で抑えるのではなく“設計で制御する”という発想を提案しています。