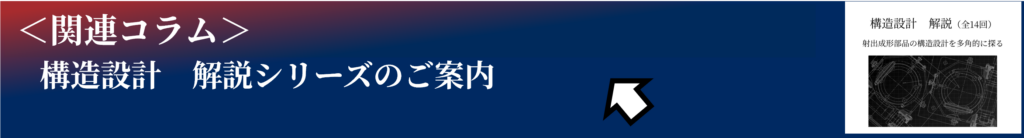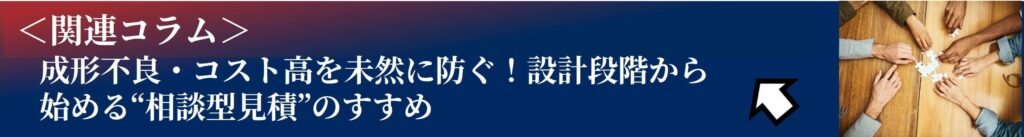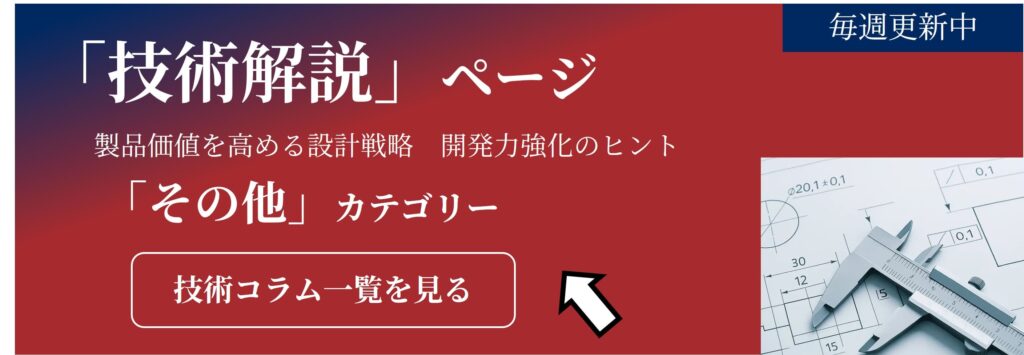リブ設計から“荷重経路設計”へ - 応力を逃がす構造発想
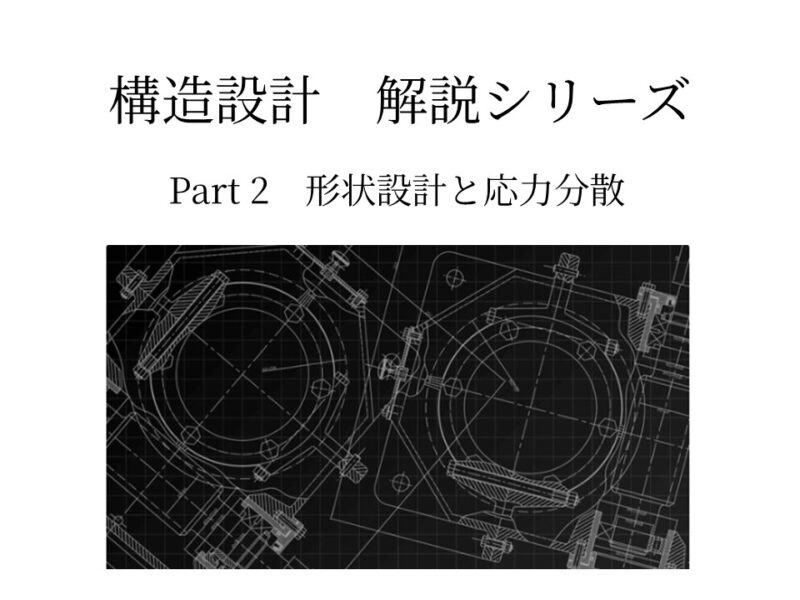
シリーズコラム第4回
「変形を抑えるためにリブを追加したのに、期待したほど効果が出ない」。これは、樹脂部品の設計において頻繁に遭遇する課題です。その背景には、金属の設計感覚のまま、樹脂特有の構造特性を見過ごしているケースが多くあります。樹脂は、金属に比べて弾性率が低く、粘弾性という時間と共に変形する性質を持つため、応力が集中する「線」で支える構造では、長期的にたわみや変形を抑制しきれません。
本コラムの目的は、リブの数や太さといった局所的な視点から脱却し、「部品に加えられた荷重が、どこを通り、どのように支持点へ伝わるのか」という「荷重経路」の視点から設計全体を捉え直すための考え方を提示することです。
荷重経路という概念の基礎
荷重経路とは、荷重の入力点から支持点(固定部や嵌合部など)まで、応力が連続して伝わる道筋のことを指します。この道筋が明確で、途切れることなくスムーズに流れる構造であれば、部品は効率よく荷重を分散・伝達でき、変形を小さく抑えることができます。
この応力伝達の効率は、断面形状に大きく左右されます。例えば、板をコの字に曲げただけの「開放断面」は、ねじりや曲げの力に対して弱く、力が断面の外へ逃げてしまいがちです。一方、コの字の開口部を塞いで四角い箱状にした「閉断面」は、力が断面内部を循環するように伝わるため、極めて高い剛性を発揮します。
樹脂部品は、成形時の流動性や冷却収縮の影響で、内部に応力や分子の配向が残りやすいという特徴があります。そのため、荷重経路が不明確な設計では、これらの内部的な要因と外部からの荷重が複合的に作用し、予測しない変形を引き起こすことがあります。明確な荷重経路を設計することは、樹脂部品の性能を安定させるための根幹と言えます。
変形を招く設計の典型パターン
効果の薄い設計や、かえって問題を悪化させる設計には、荷重経路が分断・寸断されているという共通点があります。

- リブが支持構造に繋がらず、荷重が途中で滞留する構造
最も多い失敗例が、荷重がかかる部分の近くに配置したものの、壁やボスといった支持構造まで到達していない「行き止まりリブ」です。この構造では、伝わってきた応力がリブの先端で行き場を失い、滞留してしまいます。結果として、変形抑制効果が低いだけでなく、応力集中によって破壊の起点となるリスクを高めます。
- 開口部が応力の逃げ場となり、局所的なたわみを生むケース
筐体の操作パネル用の穴や、部品を軽量化するための肉抜き穴といった開口部は、それ自体が荷重経路を遮断する大きな障害物です。開口部の周囲に適切な補強がないと、力が開口部を迂回する際に経路が乱れ、周辺部に応力が集中してたわみやねじれの原因となります。
- ボス周辺で荷重が点集中し、面に拡散できない構造
ネジで締結するボスは、その軸力によって高い圧縮荷重を受け続けます。ボス単体の強度だけを考え、その周囲の構造との繋がりを考慮しない設計では、ボスにかかった「点」の荷重が周囲の「面」へ効率よく拡散されません。結果として、ボス周辺だけが局所的に沈み込むような変形(クリープ)や、座面の陥没を引き起こします。
荷重経路を最適化する設計の考え方
変形を招くパターンを回避し、堅牢な構造を実現するには、意図的に力の通り道を設計するという発想が不可欠です。

- 製品の「外周・開口周囲」を連続させて荷重を面で受ける発想
まず基本となるのが、部品の外周や開口部の周りを、切れ目のないリブでぐるりと囲い、「フレーム(枠)」を形成することです。これにより、部品のどの部分に力が加わっても、その力はまず強固なフレームに伝達され、面全体で受け止めることができます。荷重経路を部品の輪郭に沿って連続させることで、局部的な変形を防ぎます。
- 荷重源と支持点を結ぶ「直線・斜線の経路」を構造として形成する
力は、最短距離を伝わる性質があります。荷重が加わる点と、それを支える支持点を、直線や斜線のリブで結ぶことは、最も効率的な補強方法の一つです。建築物における「筋交い」のように、曲げの力を、引張りと圧縮という単純な力の伝達に置き換えることで、少ない材料で飛躍的に剛性を高めることができます。
- 点荷重を面へ、面からフレームへと連続的に伝える構造
ボスにかかるような「点」の荷重は、段階的に分散させる思想が有効です。まずボスの周囲に薄い円盤状の「面」を設け、点で受けた荷重を面に広げます。次に、その面から放射状のリブを伸ばし、前述の「フレーム」へと接続します。これにより、「点→面→フレーム」という連続した荷重経路が形成され、応力集中を効果的に緩和できます。
- 半閉断面を閉断面に近づけることで、ねじれ・たわみを抑える考え方
コの字型のチャンネル形状など、断面が開いている構造はねじりに非常に弱いです。この開口部を塞ぐように、一定間隔でブリッジ状のリブを渡すことで、構造を「閉断面」に近づけることができます。完全に閉じた箱にしなくとも、格子状に補強するだけで、断面形状が維持され、ねじりやたわみに対する抵抗力は大幅に向上します。
ケース別の設計アプローチ
これらの考え方は、具体的な製品形状に応じて柔軟に適用されます。
- 大型カバーや開口のある筐体でのたわみ対策
まず、筐体の外周と開口部の周囲に「連続したフレーム」を形成します。次に、広い面のたわみを抑制するため、フレーム間を渡るように長手方向や短手方向に「ブリッジ」となるリブを配置します。これにより、面全体が格子状の構造となり、どの方向からの荷重に対しても安定した剛性を発揮します。
- ボスの荷重を樹脂面からフレームへ伝える構造化
締結力が高いボスでは、「点→面→フレーム」の原則を徹底します。特にボスが筐体の壁面から離れた位置にある場合は、ボスから最寄りの壁面(フレーム)まで、力を最短で伝えるためのリブを必ず複数本、放射状に配置します。行き止まりのリブは避け、すべての補強が支持構造に繋がるように設計します。
- 細長い板状部品の面外変形を抑える荷重経路設計
細長い板は、短手方向に容易に曲がってしまいます。これを防ぐには、長手方向の両端に全長にわたるフランジ(L字状の壁)を設け、断面をコの字型にします。さらに、そのコの字の開口部を補強するため、一定間隔でブリッジ状のリブを追加し、「はしご状」の構造にすることで、ねじれと曲げの両方に対する剛性を確保します。
- 高剛性樹脂(GF強化材・PPS・PEEKなど)における経路設計の違い
ガラス繊維(GF)で強化された材料やスーパーエンプラは、弾性率が非常に高い一方で、伸びが小さく破壊しやすい(脆い)傾向があります。そのため、応力集中に対してより敏感です。これらの材料では、荷重経路の角を滑らかなRで繋ぐ、応力集中源となりうるシャープエッジを徹底的に排除するなど、応力をいかにスムーズに流すかという配慮が、非強化材以上に重要になります。また、GF強化材では、繊維の配向方向と主要な荷重経路の方向を一致させることで、材料の性能を最大限に引き出すことができます。
設計と量産性の両立
優れた荷重経路を設計しても、それが安定して量産できなければ意味がありません。剛性設計と量産性は、常にセットで考える必要があります。
- 荷重経路を形成する構造が量産時の反りやヒケに与える影響
荷重経路を形成するために追加したリブは、局部的な肉厚部となり、ヒケや反りの原因になり得ます。特に、太く高いリブが非対称に配置されると、冷却収縮の差が大きくなり、製品全体を大きく歪ませる可能性があります。
- 成形性を損なわない範囲での荷重経路設計の実践ポイント
荷重経路を形成するリブの厚みは、接続する母材肉厚の50~60%以下に抑えるのが原則です。また、連続したフレーム構造を設ける際は、樹脂の流れを分断したり、空気の逃げ場をなくしたりしないよう、部分的に肉盗みを設けるなどの配慮が必要です。抜き勾配を確保することは言うまでもありません。
- 「剛性×成形性×量産安定性」を同時に満たす設計の優先順位
設計においては、まず製品に求められる機能(許容たわみ量など)を満足させるための荷重経路を構想します。次に、その経路を、ヒケや反りを最小限に抑える形状(適切なリブ厚やR)で実現します。最後に、金型からの離型性や樹脂の充填性を確認し、微調整を行います。この「機能→構造→量産」の順で検討を進めることが、三者をバランスさせるための鍵です。
まとめ
樹脂部品の強度設計において、主役はリブの数や太さではありません。部品内部を流れる「力の通り道」そのものです。設計の初期段階から、荷重がどこを通り、どう流れるかを意識し、その経路を意図的に形成するという発想に転換することが重要です。
荷重経路を最適化する設計は、闇雲にリブを追加する設計とは異なり、より少ない材料で、より高い剛性を実現できる可能性を秘めています。本コラムで提示した考え方が、今後の部品設計における一つの指針となり、より合理的で信頼性の高い製品開発の一助となれば幸いです。