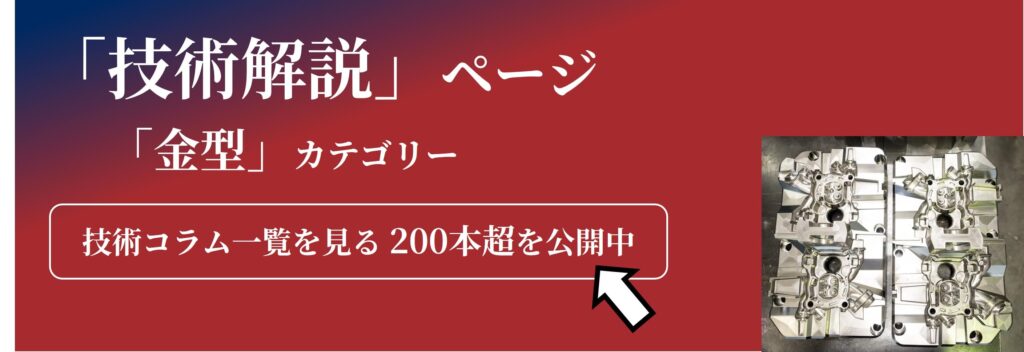安く見える金型が高くつく本当の理由:金型設計力の差が量産後のコストと品質を左右する

射出成形部品の調達・開発購買ご担当者様へ。同じ図面、同じ材料で相見積もりを取った際、提示される金型費用や製品単価に大きな差が出て、どのサプライヤーを評価すべきか悩んだ経験はありませんか?
多くの調達担当者は、公平性を期すために「図面と材料を固定し、価格で比較する」手法を取ります。しかし、その価格差の背景にある「金型設計力」という技術的な要因を見過ごしてしまうと、かえってトータルコストを増大させるリスクを招きかねません。
本コラムは、既存の「設計者向けのコラム」と分けて、調達担当者の視点で書いてみたいと思います。「なぜ価格に差が生まれるのか」という疑問を起点に、コストと品質を左右する「金型設計」の重要性を解き明かし、サプライヤーの“見えない実力”を評価するための具体的な着眼点を解説します。
「製品単価」に隠れる金型のコスト影響力
調達担当者として注目すべきは、金型費という初期投資だけではありません。金型の設計思想は、量産開始後の「製品単価」や「見えないコスト」に継続的に影響を与えます。
サイクルタイムと製品単価
効率的な冷却水管の配置や、製品をスムーズに取り出せる構造を持つ金型は、1ショットあたりの成形時間(サイクルタイム)を短縮します。これは時間あたりの生産量を増やし、製品単価の低減に直結します。見積もりが安くても、サイクルタイムの長い非効率な金型では、量産が進むほどコスト競争力を失います。
歩留まりと廃棄コスト
寸法が安定しない、ヒケ(表面の凹み)やソリが頻発する…。こうした品質不良は、金型内の樹脂の流れや圧力の伝わり方を考慮した設計が不十分な場合に起こりがちです。低い歩留まりは、材料の無駄や選別工数を生み、調達担当者が管理するコストを確実に圧迫します。
メンテナンス性とTCO(総所有コスト)
「安い金型」は、耐久性の低い鋼材を使っていたり、摩耗しやすい部分の交換が考慮されていなかったりする場合があります。頻繁なメンテナンスによる生産停止は、納期遅延だけでなく、取引先からの信頼性の低下や機会損失といったリスクと追加コストに直結します。長期的な視点(TCO)で見た場合、初期費用が多少高くとも、メンテナンス性に優れた堅牢な金型の方が、結果的にコストを抑えられるのです。
「安い見積=正しい金型設計」ではない、という事実は、調達担当者こそが強く認識すべき重要なポイントです。
見積書に現れない「金型設計」の差とは
では、価格差の源泉となる「金型設計」の違いとは何でしょうか。調達担当者が知っておくべき、代表的なポイントを3つご紹介します。
取り数(キャビティ数)の最適化
1回の成形で何個の製品を作るか(取り数)は、金型費と製品単価のバランスを決定づけます。年間の生産計画に対し、過剰な取り数で高い金型を提案してはいないか。逆に、製品単価を下げるチャンスがあるのに、安全策で少ない取り数しか提案できないのか。企業の生産計画まで踏み込んで最適な取り数を提案できるかは、成形メーカーの技術対応力を示すバロメーターです。
ゲート・ランナー設計と品質安定性
ゲートやランナーの設計は、製品の寸法安定性や外観品質を左右します。特に多数個取りの場合、全ての製品に均等に樹脂を充填する設計(バランスの良いランナー)がされているかは、歩留まりに直結します。この部分の設計ノウハウが、成形メーカー間の品質の差となって現れます。
アンダーカット処理と金型構造の最適化
製品にアンダーカット(金型がそのままでは抜けない凹凸)があると、「スライド」という複雑な可動機構が必要になり、金型費、サイクルタイム、故障リスクのすべてを押し上げます。製品の機能を損なわない範囲で形状変更を提案し、このスライド構造を回避できる成形メーカーは、VE提案能力が高いと言えます。価格だけを比べると、この「構造を簡略化する」という最も効果的なコストダウンの機会を失いかねません。
「一律見積り」がVE提案の機会を奪う
完成図面と指定材料をベースとした一律の見積依頼は、公平なようでいて、実は調達部門にとって大きな機会損失を生んでいます。
仕様が確定している場合、成形メーカーは「いかに安く作るか」という価格競争にしか参加できず、「そもそも、もっと良い作り方はないか」というVE提案の余地がありません。
例えば、「この部分の寸法精度は、実はそこまで厳しくなくても良い」といった設計の背景情報が共有されないままでは、成形メーカーは過剰品質で高コストな金型を提案せざるを得ません。調達担当者が主導する価格比較が、結果として、より本質的なコストダウンの機会を奪ってしまうのです。
このジレンマを解消するのが、「相談型見積」です。設計意図や背景を共有し、成形メーカーを「コスト削減のパートナー」として巻き込むことで、彼らの専門知識を最大限に引き出すことができます。
サプライヤーの「金型設計力」を測る、調達担当者のための質問術
サプライヤーの提案力を評価するために、見積もり時に以下の質問を投げかけてみてください。価格の根拠を問うことで、その成形メーカーの技術レベルや思考の深さが見えてきます。
「この取り数(キャビティ数)でご提案いただいた、コスト上の根拠を教えてください」
→ これにより、当社の生産計画を理解し、金型費と製品単価のトータルコストで最適化を考えているかが分かります。
「このゲート位置は、品質安定性の観点からどのようなメリットがありますか?」
→ これにより、外観や寸法精度といった品質要件への配慮、つまり「ただ作る」以上の付加価値を意識しているかが分かります。
「このスライド構造をなくすための、製品形状に関するVE提案は可能ですか?」
→ これにより、受動的に図面通り作るだけでなく、金型構造を簡素化してコストとリスクを低減しようとする能動的な姿勢があるかが分かります。
「この金型仕様で、想定されるメンテナンス計画と長期的なコストについて教えてください」
→ これにより、初期費用だけでなく、TCO(総所有コスト)や安定供給まで見据えた提案ができる、信頼性の高いパートナーかを見極められます。
府中プラは、こうした調達担当者の皆様からの問いに、明確な根拠をもってお答えすることをお約束します。図面完成前の構想段階からご相談いただくことで、設計・調達・製造の間に立つ“橋渡し役”として、QCDの最適化を支援します。
まとめ
射出成形品の見積りは、単なる価格比較の場ではありません。サプライヤーの技術力と、自社の製品価値を最大化する「最初のVE提案の機会」です。
表面的な価格でサプライヤーを選定する従来のやり方から、「金型設計力があるか?」、「設計に介在し、TCOを削減する提案ができるか?」という新しい評価軸へシフトすることが、これからの調達担当者には求められます。
そのためには、仕様が固まる前の“早めの相談”が何よりの鍵となります。次のサプライヤー選定の際には、ぜひ価格の裏にある「技術的な対話」を試みてください。それこそが、貴社のコスト競争力を本質的に高めるための、最も確実な一歩となるはずです。