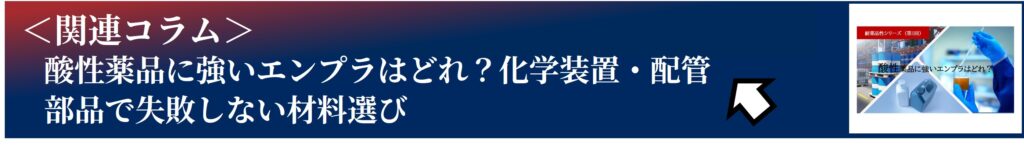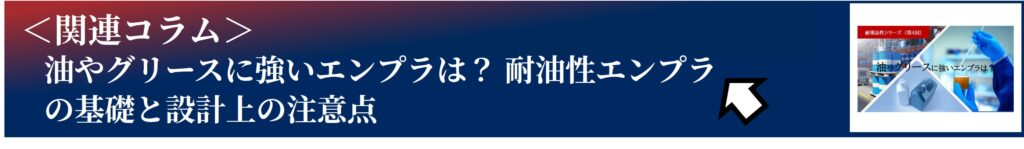有機溶剤に強いエンプラはどれ?膨潤・クラックを防ぐエンプラの選び方

有機溶剤は、洗浄、溶解、希釈といった目的で工業分野のあらゆる場面で利用されています。しかし、プラスチック部品にとって、有機溶剤は最も注意すべき薬品の一つです。溶剤との相性を誤ると、部品の膨潤による寸法変化や、突然のクラック(ひび割れ)による破壊を引き起こし、装置全体の機能不全につながる可能性があります。耐薬品性シリーズ第3回の本コラムでは、有機溶剤の基礎から、耐性を持つエンプラの選び方、そしてトラブルを未然に防ぐ設計の要点までを解説します。
そもそも有機溶剤とは?
まず、プラスチック部品の設計において注意すべき「有機溶剤」がどのようなものかを確認しましょう。
有機溶剤の定義と役割
有機溶剤とは、「他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称」です。水に溶けにくい油脂や樹脂などを溶かすことができるため、工業プロセスにおいて、部品の脱脂洗浄、塗料や接着剤の希釈、化学反応の媒体など、非常に幅広い用途で使われています。
プラスチック設計で注意すべき代表的な有機溶剤
ひと口に有機溶剤と言っても、その種類は多岐にわたります。プラスチックの劣化に大きく関わる代表的な有機溶剤の系統と具体例を以下に示します。
- アルコール系:IPA(イソプロピルアルコール)、メタノール、エタノールなど。
電子部品の洗浄や消毒で多用されます。
- ケトン系:アセトン、MEK(メチルエチルケトン)など。
非常に強力な溶解力を持ち、樹脂や塗料の溶解、接着剤の成分として使われます。
- 芳香族炭化水素系:トルエン、キシレン、ベンゼンなど。
塗料やインキの溶剤、化学原料として広く使用されます。
- 脂肪族炭化水素系:ヘキサン、ヘプタンなど。
油脂の抽出や洗浄、ゴム工業などで使われます。
- エステル系:酢酸エチル、酢酸ブチルなど。
塗料や接着剤の溶剤として一般的です。
- 塩素(ハロゲン)系:ジクロロメタン(塩化メチレン)、トリクロロエチレンなど。
強力な脱脂洗浄能力を持ちますが、環境や人体への影響から規制が進んでいます。
これらの溶剤、またはこれらを含む混合液に部品が触れる可能性がある場合、材料選定には細心の注意が必要です。
なぜ有機溶剤は樹脂を劣化させるのか?
有機溶剤によるプラスチックの劣化は、主に「膨潤・溶解」と「環境応力割れ」の2つのメカニズムで進行します。
膨潤・溶解
プラスチックの分子構造は、ポリマー(高分子)の鎖が絡み合って形成されています。ここに有機溶剤が接触すると、溶剤の分子がポリマー鎖の隙間に侵入し、絡み合いを緩めてしまいます。これが「膨潤」です。膨潤した部品は寸法が変化し、機械的強度が著しく低下します。さらに溶剤との親和性が高い場合、ポリマー鎖が完全にバラバラになり、溶けてしまう「溶解」に至ります。
環境応力割れ(ESC: Environmental Stress Cracking)
これは、部品にかかる応力(外部からの荷重や成形時の残留応力)と、特定の有機溶剤が組み合わさることで発生する現象です。単独では問題ないレベルの応力や溶剤であっても、両者が同時に作用すると、微小な亀裂(クラック)が発生・成長し、最終的に突然の破壊に至ります。特に、PCやPMMAのような非晶性プラスチックで顕著に見られます。
有機溶剤が使われる代表的な用途
耐有機溶剤性が求められる部品は、精密機器や製造装置の中に数多く存在します。

- 検査機器・分析装置:液体クロマトグラフィー(HPLC)などの分析装置では、移動相としてアセトニトリルやメタノールといった有機溶剤が使用されます。流路を構成するチューブやコネクタ、シール部品には、これらの溶剤に対する高い耐性が求められます。
- 洗浄装置:半導体ウェハーや精密部品の洗浄工程では、IPAや各種洗浄用溶剤が使用されます。カセットやキャリア、ノズルといった部品は、繰り返し溶剤にさらされるため、膨潤やクラックが許されません。
- 塗装・接着工程の周辺部品:塗料や接着剤には、トルエンやアセトンなどの溶剤が含まれています。これらを貯蔵する容器や供給ラインの部品、塗装マスク、固定治具などは、溶剤による劣化が少ない材料でなければなりません。
有機溶剤に強いエンプラと選定のポイント
有機溶剤に対する耐性は、プラスチックの化学構造と分子の集合状態(結晶性か非晶性か)に大きく依存します。
耐性に優れる「結晶性」スーパーエンプラ
分子が規則正しく並んだ「結晶部分」を持つ結晶性プラスチックは、分子が緻密に詰まっているため、溶剤分子が内部に侵入しにくく、高い耐溶剤性を示します。
LCP(液晶ポリマー)、PPS(ポリフェニレンサルファイド)、PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。これらは結晶性のスーパーエンプラの代表格です。非常に安定した化学構造と高い結晶性を併せ持ち、ケトン系や芳香族系といった強力な溶剤を含む、ほとんどの有機溶剤に対して優れた耐性を示します。
安定した化学構造を持つ「非晶性」スーパーエンプラ
分子がランダムに集合した非晶性プラスチックは、一般に溶剤が侵入しやすく耐溶剤性に劣りますが、一部のスーパーエンプラは例外です。
PES(ポリエーテルサルホン)、PPSU(ポリフェニルサルホン)。これらの材料は非晶性でありながら、その強固な分子構造により、多くの有機溶剤に対して良好な耐性を示します。ただし、ケトン系や塩素系など、一部の強力な溶剤には侵される可能性があるため、事前の確認が重要です。
フッ素系樹脂という選択肢
PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、PTFE(四フッ化エチレン樹脂)。フッ素樹脂は炭素とフッ素の非常に強固な結合により、有機溶剤を含むほぼ全ての薬品に対して極めて高い耐性を示します。特にPTFEは最強クラスの耐性を持ちますが、射出成形ができないため、複雑形状にはPVDFが選択されます。
有機溶剤環境で特に注意が必要な材料
PC(ポリカーボネート)、PMMA(アクリル樹脂)。これらは代表的な非晶性プラスチックであり、分子の隙間が大きいため有機溶剤の影響を非常に受けやすい材料です。特にPCはアルコール類で、PMMAはアルコールやケトン類で容易に環境応力割れ(ESC)を起こします。透明性が必要な場合でも、これらの溶剤に接触する可能性がある用途での使用は、原則として避けるべきです。
応力+溶剤が招く「環境応力割れ」のリスクと回避法
有機溶剤が関わる環境での部品破損の多くは、この環境応力割れ(ESC)が原因です。トラブルを回避するには、材料選定だけでなく、設計と成形の両面からのアプローチが不可欠です。
設計段階での対策
応力集中はESCの最大の引き金です。部品の鋭い角(シャープエッジ)や、肉厚が急激に変化する箇所に応力は集中します。これを避けるため、①角部には可能な限り大きなR(丸み)を付ける、②肉厚はできるだけ均一にする、③リブの根元を滑らかにする、といった設計上の配慮が極めて重要です。
成形段階での対策
成形品には、冷却・固化する過程で必ず「残留応力」が発生します。この残留応力が大きいと、外部から力がかかっていなくてもESCのリスクが高まります。府中プラでは、金型設計(ゲート位置の最適化など)や成形条件(樹脂温度、金型温度、保圧など)を精密にコントロールすることで、この残留応力を最小限に抑え、部品の耐薬品性を最大限に引き出します。
まとめ
有機溶剤に対する部品の耐久性は、「材質だけで決まるものではない」という点が最も重要です。同じ材料を使っても、部品の形状や成形条件によって、その性能は大きく変わります。
選定を成功させるための実務ポイントは、使用する溶剤の種類・濃度・温度・接触時間に加え、部品にかかる応力(外部荷重と残留応力)までを考慮した総合的な評価を行うことです。データシートの耐薬品性評価だけで安易に判断せず、実際の使用環境を想定した上で材料と設計を決定する必要があります。
最適な材料選定や、応力対策を施した設計に不安がある場合は、ぜひ府中プラにご相談ください。豊富な知見と成形技術に基づき、お客様の課題解決を強力にサポートいたします。