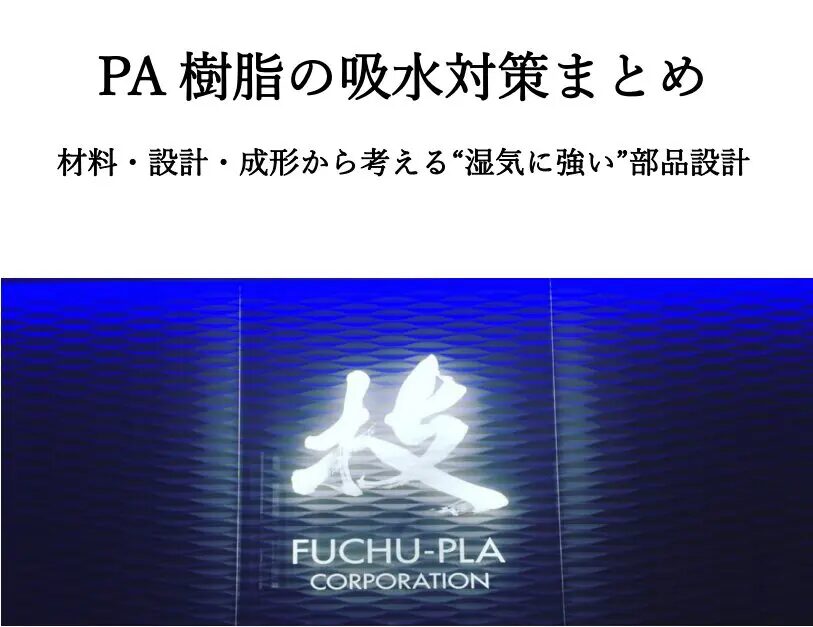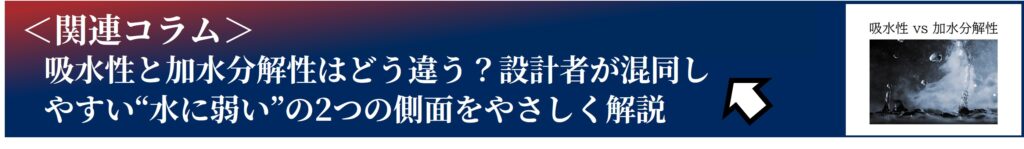高湿度・水回りで使えるのはこのエンプラ! 吸水性比較と正しい設計・材料選定
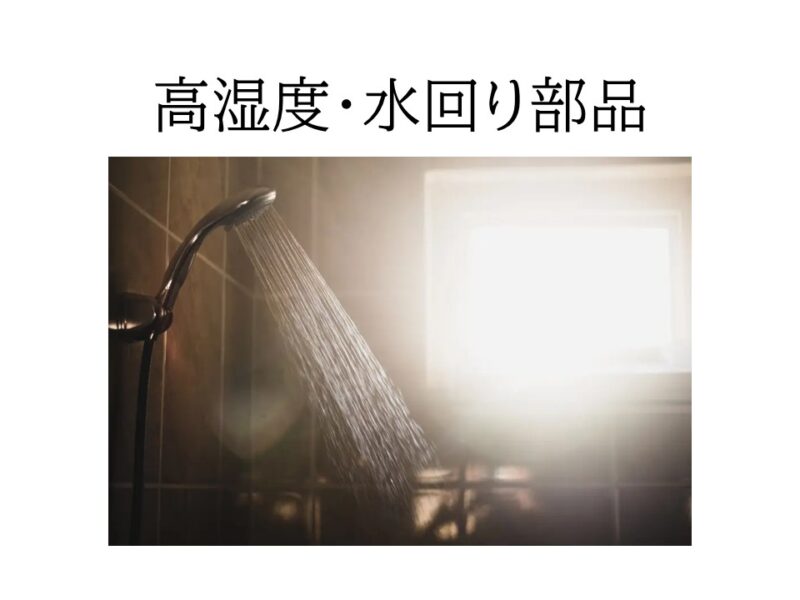
プラスチックは軽量で加工性に優れ、金属からの代替として様々な製品に利用されています。しかし、浴室や厨房、屋外などの高湿度環境や、液体を扱う分析装置、医療機器など、水に触れる環境下では、材料の「吸水」が原因で思わぬトラブルを引き起こすことがあります。寸法変化による嵌合不良、強度の低下、反りやねじれの発生は、製品の品質と信頼性を著しく損なう要因となります。
本コラムでは、府中プラが、高湿度・水回り環境での使用を想定したエンプラ選定の要点について、吸水特性に着目して解説します。用途に応じた最適な材料選びで、設計段階からのトラブル防止を実現しましょう。
主要エンプラの吸水率比較

プラスチックの吸水とは、材料が周囲の水分を内部に取り込む現象です。吸水率は、材料の種類、温度、湿度、接触時間によって変化します。吸水したプラスチックは、水分子がポリマー鎖の間に入り込むことで膨潤し、寸法が変化します。さらに、水分子が可塑剤のように働くことで、剛性や引張強さが低下する一方、靭性(粘り強さ)が向上するなど、機械的物性も大きく変動します。
ここでは、代表的なエンプラの吸水率を比較し、それぞれの特徴を見ていきましょう。なお、吸水率はグレードや測定条件(例:23℃水中浸漬24時間後)により変動するため、以下の数値は一般的な傾向を示す目安です。
| 材料名 | 略称 | 吸水率(23℃, 24h)の目安 | 特徴・注意点 |
| ポリアミド6 | PA6 | 1.3~1.9 % | 吸水率が非常に高い。吸水により柔軟性・靭性は向上するが、剛性低下と寸法変化が大きい。 |
| ポリアミド66 | PA66 | 1.0~1.5 % | PA6よりは低いが、エンプラの中では高吸水。PA6と同様、物性・寸法変化に注意が必要。 |
| ポリブチレンテレフタレート | PBT | 0.2~0.3 % | PAに比べ吸水率は低い。ただし、高温多湿下では加水分解による物性低下に注意が必要。 |
| ポリアセタール | POM | 0.2~0.25 % | 吸水率が低く、寸法安定性に優れる。機械的物性のバランスが良く、摺動部品に多用される。 |
| ポリカーボネート | PC | 0.15~0.2 % | 吸水率は低いが、PBT同様、高温多湿下での加水分解に注意。透明性が特徴。 |
| 変性ポリフェニレンエーテル | mPPE | 0.06~0.07 % | 吸水率が極めて低く、寸法安定性が非常に高い。加水分解にも強く、電気特性も良好。 |
| ポリフェニレンサルファイド | PPS | 0.01~0.02 % | 吸水率はほぼゼロに近く、極めて高い寸法安定性を持つ。耐熱性、耐薬品性にも優れる。 |
| 液晶ポリマー | LCP | 0.01~0.02 % | PPS同様、吸水率はほぼゼロ。成形時の流動性が高く、薄肉・精密成形に適する。 |
高吸水性樹脂:ポリアミド(PA6, PA66)
ポリアミド(ナイロン)は、その分子構造に親水性のアミド基を持つため、エンプラの中で最も吸水率が高い材料です。吸水による寸法変化率が大きく、例えばPA66のギアが湿度変化で膨張し、歯車のあそびが詰まって動作不良を起こすことがあります。一方で、吸水すると靭性が向上するため、乾燥状態では脆い製品が、適度に吸湿することで粘り強くなるという側面もあります。高湿度環境でPAを使用する場合は、吸湿平衡状態での寸法と物性を前提とした設計が不可欠です。
低吸水性樹脂:POM、mPPE、PPS、LCP
これに対し、POM、mPPE、PPS、LCPなどは吸水率が非常に低く、高湿度環境下でも寸法や物性の変化が僅かです。特にPPSとLCPは吸水率が0.02%以下と極めて低く、最高の寸法安定性を誇ります。mPPEも0.1%を下回る低吸水率で、かつ加水分解への耐性も高いことから、温水が関わるポンプ部品や水回りの筐体などに広く採用されています。
湿度による寸法変化とねじれ・反りの事例
吸水による寸法変化は、部品の精度を損なうだけでなく、反りやねじれといった外観不良の直接的な原因となります。特に、肉厚が不均一な部品や、広い面積を持つ筐体などで問題が顕在化しやすくなります。
事例1:分析装置の精密ギア
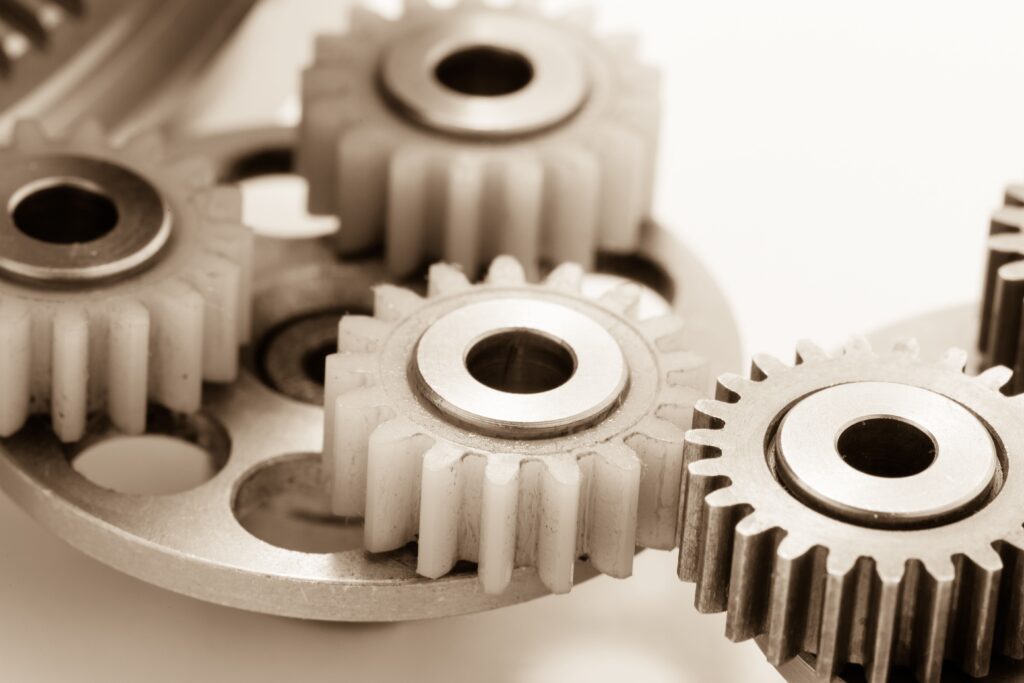
液体サンプルを扱う分析装置では、送液ポンプやサンプルステージの駆動部に精密なギアが使われます。ここに高吸水性のPA製ギアを使用した場合、装置内の湿度や洗浄液の影響でギアが吸水・膨張します。その結果、歯のかみ合いがきつくなり、異音や摩耗の促進、最悪の場合は駆動モーターの過負荷や停止につながります。このような用途では、低吸水で自己潤滑性にも優れるPOMや、さらに高い精度と耐薬品性が求められる場合にはPPSへの材料変更が有効な対策となります。
事例2:浴室乾燥機や調理機器の筐体

浴室乾燥機やスチームオーブンといった製品は、高温高湿という過酷な環境に晒されます。大型の筐体部品において、リブやボス周りと平面部で肉厚が異なると、吸水・乾燥のスピードに差が生じます。この不均一な膨張・収縮が内部応力を発生させ、部品全体の「反り」や「ねじれ」を引き起こします。結果として、部品同士の嵌合部に隙間が生じ、防水・気密性能の低下や、きしみ音の原因となります。対策としては、吸水率が極めて低く、加水分解にも強いmPPEや、ガラス繊維で強化して寸法安定性を高めたPPSなどが適しています。
事例3:電子部品コネクタの反り
基板に実装されるコネクタも、はんだリフロー時の高温や使用環境の湿度に影響を受けます。特に薄肉長尺のコネクタでは、僅かな吸水率の違いが反りを引き起こし、基板とのはんだ接合不良(実装浮き)の原因となります。この対策として、成形時の流動性に優れ、吸水率がほぼゼロでリフロー時の高温にも耐えるLCPが標準的に使用されています。
用途別!高湿度環境向け設計材料マップ
どの材料を選ぶべきか。ここでは「吸水率」と「機能性(耐熱性・強度)」を軸に、高湿度環境向けの材料を用途別にマッピングします。コストも考慮に入れながら、最適な材料選定の指針としてご活用ください。
【カテゴリA】超高精度・高機能ゾーン(最優先候補)
該当材料:PPS, LCP
特徴: 吸水率がほぼゼロ。最高の寸法安定性、高耐熱性、優れた耐薬品性を誇るスーパーエンプラ
主な用途:
分析装置・医療機器: 血液や薬液に触れる流路部品、バルブ、精密ポンプ部品
半導体製造装置: 純水や薬液を使用する環境下のウェハーチャック、ガイド
電子部品: 高周波対応コネクタ、リフロー実装される精密部品
選定ポイント: コストは高めですが、精度や信頼性が最優先される用途では代替の難しい選択肢です。
【カテゴリB】高バランス・汎用ゾーン(第一候補)
該当材料:mPPE、POM
特徴: 非常に低い吸水率と優れた寸法安定性。機械的物性のバランスが良く、コストパフォーマンスにも優れる。
主な用途:
調理機器・住宅設備: スチームオーブンの内部機構部品、給湯器のポンプハウジング、浄水器カートリッジ、シャワーヘッド
OA機器: プリンター内部の給水系部品、機構部品
選定ポイント: 多くの水回り・高湿度環境において、性能とコストのバランスから第一候補となる材料群です。mPPEは加水分解性、POMは摺動性に優れるなど、細かな要求特性に応じて使い分けます。
【カテゴリC】条件付き採用ゾーン
該当材料:PBT、PC
特徴: カテゴリBよりは吸水率が高い。高温多湿下での加水分解のリスクがあるため、使用条件の吟味が必要。
主な用途:
PBT: 電気的な特性が求められるコネクタ、スイッチ類(常温・常湿環境に近い場合)
PC: 透明性が必須なメーターカバー、インジケーター窓(ただし、蒸気や温水環境は避ける)
選定ポイント: POMやmPPEでは満たせない特性(例:PCの透明性)が必要な場合に限定的に検討します。加水分解に強い特殊グレードの選定が鍵となります。
【カテゴリD】慎重な検討を要するゾーン
該当材料:PA6、PA66
特徴: 高い吸水率により、寸法・物性変化が著しい。
主な用途: 乾燥環境下でのギア、クリップ、ファスナーなど
選定ポイント: 水回りでの使用は原則として避けるべきですが、どうしてもPAの強靭性や耐摩耗性が必要な場合は、ガラス繊維強化で寸法変化を抑制し、吸湿平衡状態での物性値で強度計算を行うなど、高度な設計ノウハウが求められます。
信頼性評価の要!加湿試験・温湿度サイクル試験への対策
製品の長期信頼性を保証するためには、実使用環境を想定した評価試験が欠かせません。特に高湿度環境向け製品では、「加湿試験」や「温湿度サイクル試験」が重要となります。
加湿試験(恒温高湿試験)
これは「85℃/85%RH」のような高温高湿の環境下に製品を長時間(例:1000時間)放置し、性能や外観の変化を評価する試験です。この試験で問題となるのは、前述の「加水分解」です。ポリエステル系のPBTやPCは、高温の水分子によってポリマー主鎖が切断され、強度が著しく低下します。対策の基本は、mPPEやPPSといった加水分解に強い材料を選ぶことです。
温湿度サイクル試験
高温高湿と低温低湿の環境を交互に繰り返す、より過酷な試験です。この試験では、材料の吸水による膨張と乾燥による収縮が繰り返されるため、材料自体や、金属インサート部品との界面に大きな応力がかかります。この応力が、クラック(ひび割れ)や剥離を引き起こすのです。
この試験への対策は、材料選定と設計の両面からアプローチします。
材料選定
吸水率が低く、線膨張係数が小さい材料(LCP、PPS、ガラス繊維強化mPPEなど)が有利です。
設計上の工夫
肉厚の均一化: 部品内の吸湿・乾燥速度を均一にし、内部応力の発生を抑制します。
応力集中部の緩和: シャープエッジを避け、コーナー部に適切なRを設けることで、クラックの起点をなくします。
金属インサート設計: 樹脂の肉厚を十分に確保し、金属部品を完全に包み込むことで、界面への水分侵入と応力集中を防ぎます。
これらの試験をクリアするには、初期段階での適切な材料選定と、応力を考慮した設計が成功の鍵を握ります。
PA樹脂の吸水対策まとめ資料のご紹介
本資料では、府中プラが長年培ってきた知見に基づき、この吸水問題に対し「材料選定」、「製品設計」、「成形・処理」という三つの視点から、体系的かつ実践的な対策を解説します。
PA樹脂の吸水対策でお困りの方はお気軽にダウンロードください。
>>「PA樹脂の吸水対策まとめ資料(PDF)」をダウンロードする
まとめ
高湿度・水回り環境で使用されるプラスチック部品の設計において、吸水率は最も重要な管理指標の一つです。吸水は、寸法変化、強度低下、反りといった品質問題に直結します。
成功の秘訣は、単に吸水率の低い材料を選ぶだけでなく、要求される耐熱性、機械的強度、耐薬品性、そしてコストを総合的に評価し、用途に最適な材料を戦略的に選定することにあります。本コラムで紹介した材料マップや試験対策を参考に、信頼性の高い製品開発にお役立てください。
府中プラでは、お客様の用途や課題に合わせた最適な材料提案を行っております。材料選定でお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。