エンプラの耐摩耗性をどう見極めるか?摺動部品に最適な材料選定

摺動性とは、一般に「滑りやすさ」と「摩耗しにくさ」という2つの要素で構成されます。本コラムでは、このうち後者の「耐摩耗性」に焦点を当てて深掘りします。
ギア、軸受、摺動レールといった長寿命化が求められる部品において、初期の「摩擦係数」の低さ以上に、長期的な「摩耗の進行抑制」が設計寿命を大きく左右します。既に掲載済みのコラムとは一線を画し、本稿では“どのように耐摩耗性を評価し、最適な材料を見極めるか”という、より実践的な指針を提示することを目的とします。府中プラがこれまで培ってきた知見に基づき、材料選定の核心に迫ります。
「耐摩耗性」とは何か? 〜設計者のための定義と評価指標〜
耐摩耗性を正しく理解することは、適切な材料選定の第一歩です。まず、摩耗がどのようなメカニズムで発生し、それをどのように数値化して評価するのかを解説します。
摩耗とは:表面がすり減る4つの基本メカニズム
摩耗は、接触する2つの物体が相対運動する際に、その表面が徐々に消耗していく現象です。その発生メカニズムは、主に以下の4つに大別されます。
アブレッシブ摩耗(研磨摩耗)
硬い相手材の突起や、摺動面に介在する硬質粒子によって、材料表面がひっかかれ、削り取られる現象です。紙やすりで木材をこするイメージに近く、特に硬度差の大きい材料同士の組み合わせで顕著になります。摺動部品においては最も一般的な摩耗形態の一つです。
アデーシブ摩耗(凝着摩耗)
摺動する面同士が微視的に接触・凝着し、その部分がせん断破壊されることで発生する摩耗です。凝着した部分が引きちぎられ、一方の面から他方の面に移動したり、摩耗粉として脱落したりします。特に金属同士や、清浄な表面同士で生じやすい現象です。
疲労摩耗
摺動面に応力が繰り返し作用することで、表面下に応力集中が発生し、微小な亀裂が生じます。この亀裂が進展し、最終的に表面が剥離(フレーキングやピッチング)する現象です。玉軸受や転がり軸受などで見られる代表的な摩耗形態です。
コロージョン摩耗(腐食摩耗)
腐食性雰囲気中での摺動運動において、化学的反応によって生成された脆い腐食生成物が、機械的な摺動作用によって除去される複合的な劣化現象です。化学プラントのポンプ部品や、湿度の高い環境で使用される摺動部品などで問題となります。
耐摩耗性の評価方法と指標
これらの摩耗現象を定量的に評価するため、様々な試験方法が規格化されています。代表的なものに、試験片を回転する研磨紙に押し当てる「テーバー摩耗試験」、ピン状の試験片を回転するディスクに押し当てる「ピンオンディスク試験」、リング状の試験片同士を摺動させる「スラストワッシャー試験」などがあります。これらの試験から得られる主な評価指標は以下の通りです。
摩耗量(mm³) / 比摩耗量(mm³/N·m)
一定の条件下で摺動させた後の、試験片の体積減少量です。これを荷重と摺動距離で規格化したものが比摩耗量で、材料固有の耐摩耗性を示す指標として用いられます。値が小さいほど耐摩耗性に優れます。
摩耗係数(μm/km)
一定の荷重下で1km摺動した際の、摩耗深さを示す指標です。主に実用的な観点から摩耗の進行度合いを評価する際に用いられます。
PV限界値(MPa·m/s)
摺動部品が正常に機能し続けられる圧力(P)と速度(V)の積の上限値です。この値を超えると、摩擦熱による急激な温度上昇で材料が溶融したり、摩耗が異常に増大したりします。材料の耐熱性や機械的強度と密接に関係します。
重要なのは、これらの指標はあくまで特定の試験条件下での相対比較値であるという点です。実際の使用環境では、相手材の材質・硬度・表面粗さ、潤滑の有無、温度、湿度などが複雑に影響します。そのため、カタログスペックを鵜呑みにせず、可能な限り実使用に近い条件で試験を行い、材料を比較評価することが、信頼性の高い選定には不可欠です。
耐摩耗性に優れるエンプラとは? 材料特性から見る本質
耐摩耗性は、エンプラが持つ分子構造や物理的特性と深く関わっています。ここでは、材料の本質的な特性がどのように耐摩耗性に寄与するのかを解説します。
分子構造がもたらす摩耗耐性
エンプラの耐摩耗性は、その化学構造や高次構造に由来します。
高結晶性(POM、PBT、PPSなど)
分子鎖が規則正しく並んだ結晶領域の割合が高い材料は、一般に硬度が高く、機械的強度に優れます。この硬さが、アブレッシブ摩耗に対する抵抗力を高めます。特にPOMは、高い結晶性と自己潤滑性を併せ持ち、耐摩耗性材料の代表格とされています。
強靭性(PA、PEEKなど)
分子鎖が強固に絡み合い、衝撃や繰り返し荷重に対する抵抗力が高い材料は、疲労摩耗に強い傾向があります。PEEKやPAは、その優れた靭性により、衝撃的な負荷がかかるギアや高荷重の軸受においても、微小な剥離を起こしにくい特性を持ちます。
低表面エネルギー(PTFE、PFAなど)
フッ素樹脂に代表される、表面エネルギーの低い材料は、他の物質が付着しにくい性質を持ちます。この「非粘着性」が、アデーシブ摩耗の起点となる凝着を防ぎ、優れた摺動性を発揮します。ただし、一般に機械的強度は低いため、フィラーとして他の樹脂に添加されることが多いです。
摩耗に強い代表材料とその特徴
以上の特性を踏まえ、耐摩耗性が求められる摺動部品で多用される代表的なエンプラとその特徴を以下に示します。
| 材料 | 特長 | 耐摩耗性の傾向 | 留意点 |
| POM | 高結晶性、優れた自己潤滑性、高剛性 | ◎ | 高荷重や高温環境下ではクリープ変形に注意が必要。 |
| PPS | 高温安定性、高硬度、優れた寸法精度 | ◎ | 靭性が低く脆い側面がある。ガラス繊維強化グレードは相手材を攻撃しやすい。 |
| PA66/PA46 | 高い靭性、優れた耐衝撃性、比較的低摩耗 | ○ | 吸水による寸法変化や物性低下が顕著なため、環境条件の考慮が必須。 |
| PEEK | 優れた耐熱性、高荷重下での耐摩耗性、耐薬品性 | ◎ | 材料コストが非常に高い。高い溶融温度のため、成形条件が難しい。 |
| UHMWPE | 極めて高い耐摩耗性、低摩擦係数、自己潤滑性 | ◎ | 強度、剛性、耐熱性が低く、PV限界値も高くないため、低速・低荷重用途に限定される。 |
この表からわかるように、万能な材料は存在しません。それぞれの材料が持つ長所と短所を正確に把握し、使用条件と照らし合わせて選定することが重要です。
添加剤と補強材による耐摩耗性の強化技術
ベースとなる樹脂の特性だけでは要求仕様を満たせない場合、添加剤や補強材によって耐摩耗性をさらに向上させることが可能です。
潤滑剤添加による効果と限界
摺動特性を改質する目的で、固体潤滑剤が添加されることがよくあります。
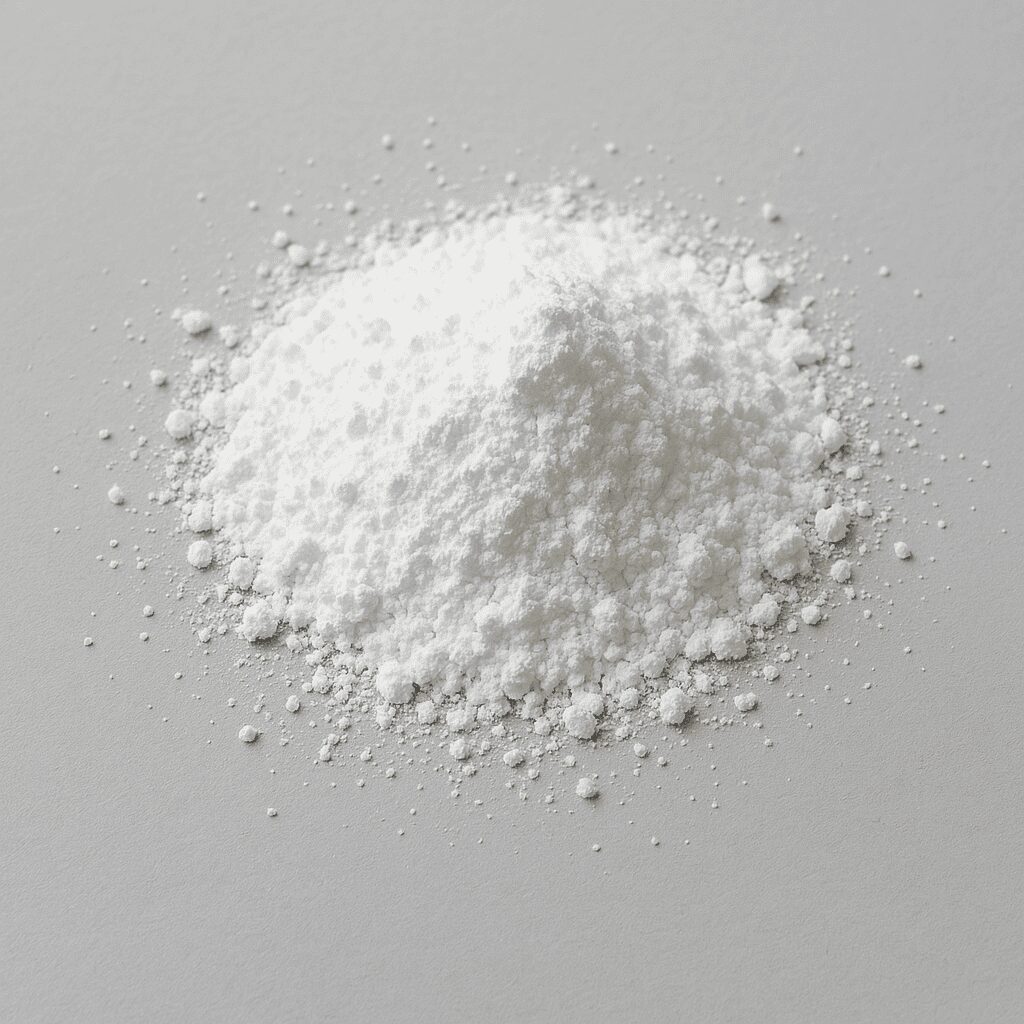
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)粉末
代表的な固体潤滑剤であり、母材樹脂に添加することで摩擦係数を大幅に低減し、耐摩耗性を向上させます。摺動時に相手材表面にPTFEの薄い膜を形成し、樹脂同士の直接接触を防ぐことで摩耗を抑制します。しかし、PTFE自体は柔らかいため、過剰に添加すると母材の機械的強度(特に引張強度や剛性)が低下する懸念があります。

グラファイト(黒鉛)、二硫化モリブデン(MoS₂)
これら層状結晶構造を持つ潤滑剤も、優れた摩耗抑制効果を発揮します。PTFEと比較して耐荷重性が高く、摺動面の発熱を拡散させる効果も期待できます。ただし、グラファイトは導電性を持ち、MoS₂は高温の酸化雰囲気で潤滑性を失うなど、使用環境を選ぶ側面があります。また、いずれも黒色であるため、製品の着色に制約が生じます。
繊維強化による耐久性アップ
高荷重下での寸法安定性やクリープ特性が求められる場合、繊維による強化が有効です。
GF(ガラス繊維)
最も一般的な補強材で、安価に剛性、強度、耐熱性を向上させることができます。これにより、面圧が高い条件下での耐クリープ性が改善され、結果として長期的な耐摩耗性が向上します。しかし、ガラス繊維は硬く、相手材を削るアブレッシブ性が非常に高いため、組み合わせる金属(特にアルミや真鍮などの軟質金属)を著しく摩耗させるリスクがあります。相手材が硬質鋼などでない限り、使用には慎重な検討が必要です。
CF(カーボン繊維)
ガラス繊維と同様に高い補強効果を持つと同時に、自己潤滑性も併せ持つ優れた補強材です。摺動特性の向上に加え、相手材への攻撃性がガラス繊維に比べて格段に低いという大きな利点があります。また、熱伝導性にも優れるため、摺動熱を効率的に逃がし、PV限界値の向上にも寄与します。耐摩耗性、潤滑性、低相手材攻撃性のバランスに優れますが、ガラス繊維に比べて高価であることが課題です。
設計現場での「摩耗トラブル」あるあると材料起因の見極め方
理論を理解していても、現場では予期せぬ摩耗トラブルが発生します。ここでは、代表的なトラブル事例と、その原因が材料にあるのかを見極めるための視点を提供します。
ギア摩耗・削れ粉の発生

ギアの歯先や歯面が異常に摩耗し、周辺に削れ粉が堆積するトラブルは後を絶ちません。この時、摩耗粉の状態を観察することが原因究明のヒントになります。
粉状の細かい摩耗粉であれば、硬い相手材や異物混入による「アブレッシブ摩耗」が疑われます。一方、フィルム状や繊維状の摩耗粉が見られる場合は、樹脂同士の凝着・剥離による「アデーシブ摩耗」の可能性が高いです。
また、GF強化グレードの樹脂ギアと、アルミやダイカストなどの軟質金属ピニオンの組み合わせは、典型的な失敗例です。GFが相手材を一方的に削ってしまい、早期にバックラッシの増大や噛み合い不良を引き起こします。
異音・引っかかりの増加
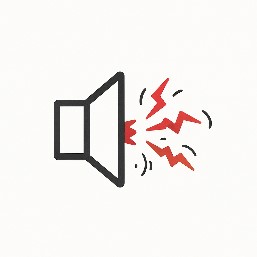
使用初期はスムーズだったものが、時間経過と共に異音(軋み音、ビビリ音)や引っかかり感が増加するケースです。これは、摺動面に蓄積した摩耗粉が研磨剤のように作用して摩耗を加速させたり、摩耗によって部品間のクリアランス(ガタ)が増大し、正常な接触状態が維持できなくなったりすることが原因です。
ここで注意すべきは、「摩擦係数の低減」が必ずしも「耐摩耗性の向上」には繋がらないという点です。例えば、PTFEを過剰に添加して摩擦係数を下げても、母材の強度が低下すれば、高荷重下では変形・摩耗しやすくなることがあります。
相手材との「相性」による加速摩耗
摩耗は、常に2つの物体の相互作用です。相手材との「相性」を見誤ると、摩耗は劇的に加速します。
例えば、同じ種類の樹脂同士(例:POM vs POM)はアデーシブ摩耗を起こしやすく、一般的に避けるべき組み合わせとされています。また、相手材となる金属の材質や表面処理(メッキ、窒化処理など)、そして表面粗さ(粗すぎても細かすぎても摩耗が増える場合がある)によって、摩耗の形態と進行速度は全く異なります。
カタログデータだけで判断せず、実機で想定されるP/V条件下での組み合わせ評価を事前に行うことが、後々のトラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。
耐摩耗性に着目した材料選定フロー
最後に、これまで述べてきた内容を踏まえ、耐摩耗性を重視した実践的な材料選定フローを提案します。
要求仕様に基づく選定ステップ
感覚的な選定ではなく、定量的なアプローチを心がけます。
荷重・速度条件からP/V値を算出する
まず、設計する部品にかかる面圧(P: Pressure)と摺動速度(V: Velocity)を計算します。このP/V値が、材料選定の最も基本的な指標となります。各材料のPV限界値を下回っているかを確認します。
目標寿命から許容摩耗量を設定する
製品に求められる寿命(時間、サイクル数)から、その期間内に許容できる摩耗量(摩耗深さや体積減少量)を定義します。例えば、「10000時間で摩耗深さ0.1mm以内」といった具体的な目標を設定します。
使用環境条件を整理する
潤滑の有無(無潤滑、グリス、油)、使用温度・湿度、雰囲気(水中、薬品、屋外など)、相手材の材質・硬度・表面粗さといった、摩耗に影響を与える全ての条件をリストアップします。
これらの要求仕様を明確にすることで、候補となる材料群を効率的に絞り込むことができます。
材料提案時の比較評価例
複数の候補材料が挙がった場合、多角的な視点での比較評価が必要です。
同一条件下での摩耗試験結果の比較
最も信頼性が高いのは、実際の使用条件を模した試験装置で、候補材料を同一条件で評価することです。その結果を「比摩耗量」や「摩耗係数」で比較し、横軸に材料名、縦軸に摩耗量をとったグラフで可視化すると、優劣が直感的に理解できます。
マトリクスによる総合評価
耐摩耗性だけで材料は決まりません。コスト、機械的強度(剛性、靭性)、寸法安定性、成形性など、他の要求特性とのバランスを考慮する必要があります。下図のようなマトリクスを作成し、各評価項目を点数化して総合的に判断することが、最適な材料選定に繋がります。
| 評価項目 | POM/PTFE | PA/CF | PEEK |
| 耐摩耗性 | ◎ | ○ | ◎ |
| 耐荷重性 | ○ | ◎ | ◎ |
| 相手材攻撃性 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 寸法安定性 | ◎ | △ | ◎ |
| コスト | ◎ | ○ | △ |
| 総合評価 | A | B | B |
このような客観的な評価プロセスを経ることで、なぜその材料を選んだのかという設計根拠を明確にすることができます。
まとめ
エンプラの摺動性を語る上で、「摩擦係数」は重要な指標ですが、長期信頼性を確保するためには「耐摩耗性」を独立した重要軸として捉える必要があります。
材料自体の分子構造、潤滑剤や繊維強化といった添加技術、そして何よりも相手材との相性が複雑に絡み合い、摩耗現象を支配します。そのため、カタログスペックの比較に留まらず、摩耗評価と材料選定には実使用条件を模擬した上での見極めが不可欠です。
摩耗トラブルに悩まされない摺動部品を設計するためには、P/V限界や摩耗形態といった基礎的な知識の理解と、適切な「材料」、最適な「相手材」、合理的な「形状」という三位一体のアプローチが成功の鍵となるのです。




