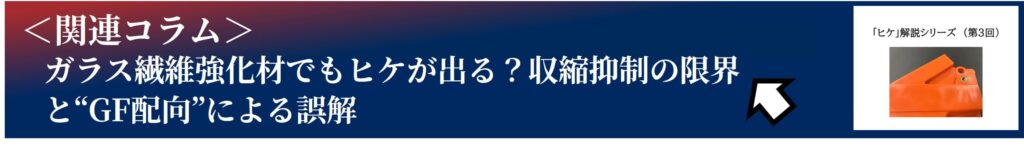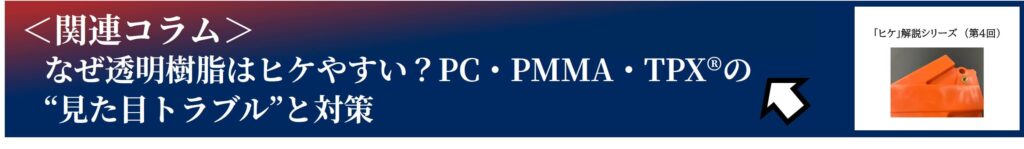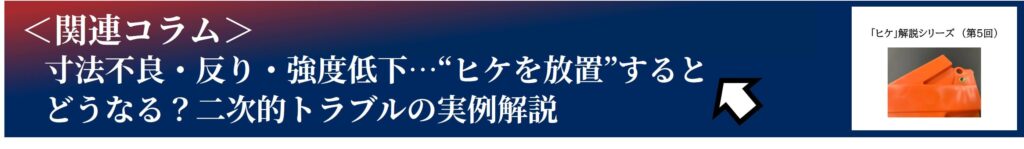「リブやボス周りのヒケ」がなくならない理由:設計・金型で防ぐ“局所収縮”の実践知識

「ヒケ」解説シリーズ 第1回
射出成形において、ヒケは最も一般的かつ厄介な外観不良の一つです。成形品の表面に生じる意図しない凹みは、製品の価値を大きく損ないます。中でも、強度確保や部品固定のために設けられる「リブ」や「ボス」の周辺は、特にヒケが集中して発生しやすい箇所であり、多くの設計者や成形技術者を悩ませる問題です。なぜ、対策を講じているはずなのに、リブやボス周りのヒケはなくならないのでしょうか。本コラムでは、この問題の根源を“局所収縮”という観点から掘り下げ、設計段階と金型段階で実践できる具体的なヒケ対策について、府中プラが培ってきた実務知識を交えて解説します。
なぜリブやボス周辺はヒケが起きやすいのか
リブやボス周辺のヒケは、偶然発生するわけではありません。その構造自体に、ヒケを誘発する物理的な要因が潜んでいます。
局所的な肉厚増加と冷却速度の不均衡
射出成形品においてヒケが発生する根本的な原因は、溶融した樹脂が冷却・固化する過程で体積が収縮することにあります。リブやボスは製品のベースとなる壁に付加されるため、その付け根部分は“実質的な肉厚部”となります。
金型内に充填された高温の溶融樹脂は、金型に接触している表面から冷却が始まります。薄い部分は速やかに固化しますが、リブやボスの付け根のような肉厚部は、内部に熱がこもりやすく、中心部まで完全に固化するのに時間がかかります。外側の表面が固まり始めているにもかかわらず、内部ではまだ高温の樹脂がゆっくりと冷却・収縮を続けています。この内部収縮の力が、まだ固化しきっていない表面を内側へと引っ張るのです。これがヒケの正体であり、局所的な肉厚増加が引き起こす「冷却速度の不均衡」が根本原因です。
外観面の“引き込み”現象
この現象を製品の外観面から見ると、より直感的に理解できます。例えば、平滑な板の外観面を持つ製品の裏側に、補強のためのリブが一本設けられているとします。外観面からはリブは見えず、均一な厚みの壁に見えるかもしれません。しかし、その裏側には紛れもなく肉厚部が存在します。
前述の通り、この肉厚部では冷却が遅れ、内部収縮が大きく発生します。この収縮力は、固化しつつある外観面の平滑な壁を、まるで裏側から引っ張るように作用します。その結果、外観面にはリブの形状に沿った線状の凹み、すなわち、ヒケとして現れます。これは「引き込み」とも呼ばれ、リブやボスの背後にヒケが集中する構造的な要因を明確に示しています。
設計段階でできるヒケ低減の工夫
ヒケの根本原因が構造にある以上、最も効果的な対策は設計段階にあります。「ヒケが出にくい形状」を最初から作り込むことが、後工程の負担を減らし、品質を安定させるための鍵となります。
リブ肉厚の基本ルール「母材の40〜70%」
リブ設計の基本原則は、母材の肉厚とのバランスです。ヒケを避けるための一般的な目安として、リブの肉厚は母材の肉厚の40〜70%程度に設定することが推奨されます。この比率は使用する樹脂の収縮率によって変動し、収縮率の高い結晶性樹脂(POMなど)ではより薄く(40〜50%)、収縮率の低い非晶性樹脂(PCなど)ではやや厚め(60〜70%)に設定します。この範囲を守ることで、局所的な肉厚増加を抑制し、冷却の不均衡を最小限に抑えます。
リブの高さと配置の工夫で強度とヒケを両立
強度を確保しようとリブを高くしすぎると、たとえ肉厚比率を守っていても、充填抵抗が増してヒケの原因となり得ます。強度が必要な場合は、一本の高いリブに頼るのではなく、高さを抑えた複数のリブを配置したり、斜めリブやV字リブを活用したりすることで、応力を分散させつつヒケを抑制する工夫が有効です。
ボス設計の基本:「肉抜き」「底抜け」でヒケの根源を断つ
ボスはネジ留めや位置決めに不可欠ですが、ヒケの主要因でもあります。特に母材との接合部である「底部」に肉が集中します。この対策として最も有効なのが、「底抜けボス」や「肉抜き」です。ボスを貫通させる、あるいはボスの周囲や内側をくり抜くことで、根本的な肉厚部をなくし、ヒケの発生源を断つことができます。
ボスの強度と外観を両立させる補強リブ
底抜け設計が難しい場合でも、ボスを独立した円筒として立てるのではなく、周囲に複数の薄い補強リブを設けることで、強度を維持しながらボスの肉厚を薄く保つことができます。この際、補強リブ自体の厚みも、前述のリブ設計の原則(2-1)に従う必要があります。ネジ留め設計においては、必要な強度とヒケ回避のバランスを見極めることが求められます。
「厚みのつながり」を滑らかにするフィレットとテーパ
急激な肉厚の変化はヒケだけでなく、応力集中の原因にもなります。リブやボスが母材から垂直に立ち上がるような角張った形状は避け、付け根には必ずR形状を設けて厚みの変化を滑らかにつなげることが重要です。R形状は応力集中を緩和し、溶融樹脂の流れをスムーズにして充填性を向上させます。また、側面への抜き勾配も、樹脂の流れと応力緩和に寄与し、ヒケの低減につながります。
金型設計によるヒケ抑制技術
製品設計で万全を期しても、ヒケのリスクをゼロにすることは困難です。そこで重要になるのが、設計の意図を最大限に活かし、問題を顕在化させないための金型設計の技術です。
冷却水管と高熱伝導インサートによる局所冷却
リブやボス周辺のヒケは局所的な冷却の遅れが原因のため、金型側ではその部分を強制的に冷却する仕組みが求められます。具体的には、ヒケが発生しやすいリブやボスの背面に相当する金型部分に、冷却水管を追加・近接させます。これにより、熱がこもりやすい箇所の熱を効率的に奪います。より高い冷却効果が求められる場合は、熱伝導率の高い金属をその部分だけに入れ子として使用する手法も有効です。
ヒケやすい箇所へ圧力を届けるゲート設計
樹脂を金型内に送り込むゲートの位置と数は、ヒケの抑制に大きな影響を与えます。ヒケは、冷却収縮する体積を補うための圧力(保圧)が十分に伝わらない箇所で発生しやすくなります。そのため、最も肉厚でヒケが懸念される箇所にゲートを配置する、あるいはその箇所を最後に充填させるように流動を設計し、十分な保圧がかかるようにします。これにより、収縮しようとする部分に後から樹脂を「押し込む」ことができ、ヒケを抑制します。
充填不良を防ぐガスベント設計
見落とされがちですが、ヒケの裏には充填不良が隠れているケースがあります。特にリブやボスの先端は充填末端になりやすく、行き場を失った空気やガスが溜まりやすい場所です。このガスが圧縮されて樹脂の流入を妨げ、圧力不足からヒケの原因となります。この対策として、金型のパーティングラインやコアピンの隙間などに、意図的にガスを外部に排出するためのガスベントを設けることが極めて重要です。
材料と成形条件の“限界”を知る
設計と金型で対策を施した上で、最後の砦となるのが材料選定と成形条件の最適化です。しかし、これらには限界があることを理解しておく必要があります。
低収縮材料は万能ではないという認識
PC(ポリカーボネート)やガラス繊維(GF)配合グレードのような低収縮材料を選択すれば、ヒケのリスクは確かに低減します。しかし、これらの材料を使ったからといって、設計の基本原則を無視して良いわけではありません。根本原因である「局所的な肉厚」が存在する限り、ヒケのリスクは完全になくなりません。材料の物性を過信せず、設計での対応が不可欠であることを認識すべきです。
対症療法になりがちな成形条件調整の限界
現場では、発生したヒケに対して射出圧力や保圧を上げる、といった成形条件の調整で対応しようとすることが多々あります。これらは確かに一定の効果がありますが、多くの場合、対症療法に過ぎません。無理に保圧を上げすぎれば、バリや残留ひずみといった新たな問題を引き起こします。構造的にヒケやすい形状に対し、成形条件だけで抑え込むことには限界があります。問題の根本が設計や金型にある場合は、そこに立ち返って対策を講じることが重要です。
リブ・ボスを含めたヒケ全体の原因整理と対策の考え方は、
射出成形におけるヒケの原因と対策
で体系的にまとめています。
まとめ
リブやボス周辺に集中する厄介なヒケは、その多くが「局所的な冷却遅延と収縮集中」という構造的な要因に起因します。この問題を根本的に解決するためには、成形条件の調整といった後工程の対策に頼るのではなく、製品開発の源流である設計段階からのアプローチが最も重要です。
府中プラでは、リブやボスの肉厚比率、形状のつながりの滑らかさ、強度と外観を両立させる補強方法といった設計上の工夫を徹底しています。そして、その設計思想を具現化するために、金型における最適な冷却設計やゲート設計を連携させて対応します。材料の特性や成形条件には限界があるからこそ、「最初からヒケが出にくい形状をつくる」という視点を常に持ち、お客様に高品質な成形品をお届けすることをお約束します。リブやボス周りのヒケでお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。