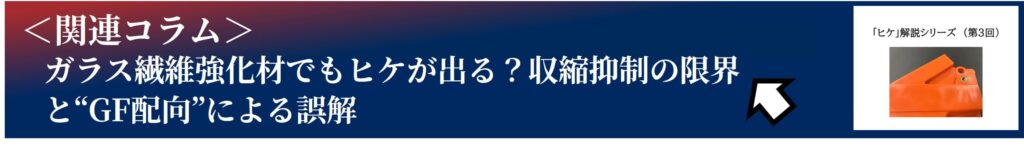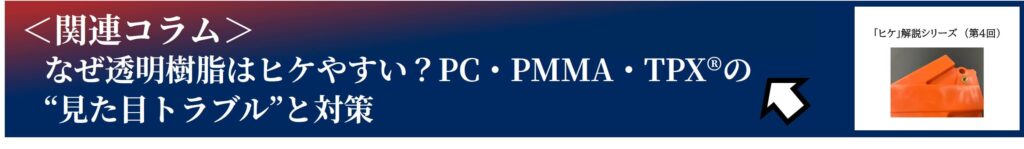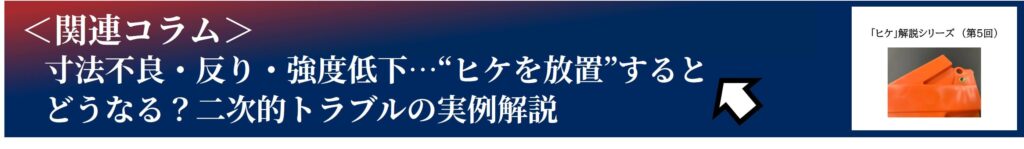ヒケの主因は“保圧”にあり!保圧時間・圧力が与える影響と最適条件の導き方

「ヒケ」解説シリーズ 第2回
射出成形におけるヒケ不良は、製品の設計、金型構造、使用する材料など、多様な要因が絡み合って発生します。しかし、それらの要素を最適化したとしても、成形条件、特に「保圧」の設定が不適切であれば、ヒケを根絶することはできません。むしろ、保圧条件の不備がヒケの主因となっているケースは極めて多いのが実情です。本コラムでは、成形プロセスにおける保圧の役割からヒケとの根本的な関係、そして保圧時間と圧力の具体的な設定方法まで、府中プラが現場で培ってきた実務に即した指針を提示します。
ヒケ全体の発生メカニズムや、原因・対策の整理については、
射出成形におけるヒケの原因と対策
で詳しく解説しています。
なぜ保圧が“ヒケ対策のカギ”になるのか
保圧は、単なる成形サイクルの一工程ではありません。ヒケの発生を直接的に左右する、極めて重要な役割を担っています。
成形サイクルにおける「保圧」の役割とは
射出成形は、大まかに「射出(充填)→保圧→冷却→型開き・突き出し」というサイクルで進行します。この中で「保圧」は、溶融した樹脂を金型内に高速で充填する「射出」工程の直後に行われます。その役割は、金型内で冷却・固化していく樹脂の体積収縮を補うために、追加の樹脂をじっくりと押し込み、補充することです。溶融した樹脂は冷えて固まる際に必ず体積が減少します。この収縮分を放置すれば、製品表面の凹み、すなわちヒケとなって現れます。保圧は、この体積減少を補償し、製品の形状と寸法を安定させるための不可欠な工程なのです。
保圧不足が招くヒケのメカニズム
保圧による樹脂の補充が不十分だと、ヒケはどのようにして発生するのでしょうか。金型内では、まず金型壁に接した部分(表層)から冷却が始まり、固化層が形成されます。一方、製品の内部、特に肉厚部の中心は高温のままで、ゆっくりと収縮を続けます。このとき、十分な保圧がかかっていれば、内部の収縮分を補うようにゲートから追加の樹脂が供給されます。しかし、保圧が不足していると、この補充が追いつきません。結果として、内部に収縮による負圧や微小な空隙(ボイド)が生じ、まだ固化しきっていない表層部分がその負圧に引かれて内側に凹んでしまいます。これが保圧不足によるヒケの発生メカニズムであり、特に冷却に時間がかかるリブやボスの裏側で顕著に現れます。
ヒケと“ゲートシール”の致命的な関係
保圧を理解する上で最も重要な概念が「ゲートシール」です。ゲートとは、金型内で樹脂が製品キャビティに流れ込むための狭い入口のことです。保圧は、このゲートを通して樹脂を補充しますが、ゲート自体も金型によって冷却されています。そのため、保圧工程の途中でゲート部分の樹脂が完全に固化してしまう瞬間が訪れます。これを「ゲートシール」と呼びます。ゲートがシール(固化して閉鎖)されると、それ以降はいくら高い圧力をかけ続けても、樹脂は製品内部に到達しません。つまり、保圧時間の設定がゲートシール時刻より短い場合、製品が完全に収縮を終える前に補充が打ち切られ、ヒケが発生します。逆に、ゲートシール後も延々と保圧をかけ続けることは、エネルギーと時間の無駄になるだけでなく、別の不良を引き起こす原因にもなります。
保圧時間はどう決める? ゲートシールを基準にした設定法
ヒケ対策における保圧時間の設定は、「ゲートが固化するまでの時間」をいかに正確に見極めるかにかかっています。
保圧時間の短縮によるヒケ発生の典型例
成形サイクルタイムを短縮し、生産性を上げたいという理由から、保圧時間を安易に短く設定してしまうケースは少なくありません。しかし、ゲートシール時間を無視した短縮は、リブやボスの裏側といった肉厚部に致命的なヒケを発生させます。特に、ピンポイントゲートやサブマリンゲートのような断面積の小さいゲートは、ダイレクトゲートなどに比べてシールするまでの時間が短くなります。使用する材料の固化特性や製品形状、ゲート設計に応じて、ゲートシール時間は大きく変動するため、それぞれの条件に合わせた適切な保圧時間の設定が不可欠です。
ショート保圧 vs 過剰保圧のリスク
保圧時間は、短すぎても長すぎても問題を引き起こします。
ショート保圧(短すぎる場合)
ヒケや内部の空隙であるボイド、寸法不足や寸法バラツキの主因となります。品質の安定性が著しく損なわれます。
過剰保圧(長すぎる場合)
ゲートシール後の無駄な加圧は、パーティングラインのバリや、製品内部に過大な応力(残留ひずみ)を蓄積させ、反りやクラックの原因となります。また、サイクルタイムの不必要な延長や成形機への負荷増大にもつながります。
最適な保圧時間とは、ゲートシールが完了する直後までの時間であり、これを見つけることが安定した品質への第一歩です。
保圧圧力がヒケに与える影響
保圧時間と並んで重要なのが、保圧圧力です。適切な時間を設定しても、圧力が不足または過剰であれば、ヒケやその他の不良を防ぐことはできません。
圧力不足による“充填不足”と体積収縮補償の失敗
保圧圧力が低いと、金型内の流動抵抗に打ち勝って樹脂を隅々まで押し込む力が不足します。特に、金型の充填末端部や、射出工程から保圧工程へ切り替わる(V/P切替)タイミングでの圧力降下が大きいと、体積収縮を補うための樹脂が十分に供給されず、ヒケが発生します。圧力は高ければ良いというわけではありませんが、製品形状や樹脂の流動性を考慮し、収縮を補うのに十分な圧力を確保することが基本です。
高すぎる保圧圧力のリスクと見極め
ヒケを恐れるあまり保圧圧力を過剰に高く設定すると、別の問題が発生します。第一に、金型の型締め力を上回る圧力がかかると、パーティングラインがわずかに開き、バリが発生します。第二に、過剰な圧力は樹脂を無理やり押し込むため、金型内のガスが抜けきらずに圧縮され、ショートショットやガス焼けの原因となることがあります。さらに、製品内部に大きな残留ひずみを生じさせ、成形後の反りや、経時変化による割れ(クラック)のリスクを高めます。最適な保圧圧力は、バリや反りが発生せず、かつヒケが十分に抑制できる範囲内に存在します。
材料・金型設計に応じた保圧最適化の勘所
保圧の最適条件は、使用する材料や金型の設計によって大きく変化します。
樹脂の種類ごとの最適保圧時間・圧力の傾向
樹脂の特性は、保圧設定に直接影響します。例えば、結晶性樹脂(PA, POMなど)は、溶融状態から固体になる際に大きな体積収縮を起こします。そのため、収縮を補うために比較的高めの保圧圧力が必要ですが、固化速度が速いため、保圧時間は比較的短くて済む傾向があります。一方、非晶性樹脂(PC, ABSなど)は、収縮率が比較的小さく、ゆっくりと固化します。そのため、圧力は中程度で良いものの、収縮が完了するまでじっくりと圧力をかけ続ける必要があり、保圧時間は長くなる傾向があります。このように、材料の物性を理解することが、保圧設定の出発点となります。
金型ゲート設計と保圧の関係
ゲートの形状とサイズは、保圧の効果を決定づける重要な要素です。例えば、製品に直接ゲートを設けるダイレクトゲートは断面積が大きいため、圧力が伝わりやすく、ゲートシールまでの時間も長くなります。対照的に、細いピンで構成されるピンポイントゲートや、製品の側面に潜り込むように設けられるサブマリンゲートは、断面積が小さいため圧力損失が大きく、ゲートシールも早くなります。したがって、ヒケやすい肉厚の製品に小さなゲートを採用すると、いくら保圧をかけてもゲートが先に固化してしまい、効果的にヒケを抑制できません。金型を設計する段階で、製品形状と保圧効果を考慮したゲート設計を行うことが、ヒケ抑制の成否を分けるのです。
成形現場で使える保圧設定の実践フロー
理論を理解した上で、現場でどのように保圧条件を設定していくか、その実践的な流れを紹介します。
初期条件の設定指針(圧力・時間・切替点)
新しい金型で成形を始める際、まずは経験則に基づいた初期条件を設定します。例えば、保圧圧力は射出圧力の50〜70%程度から始め、保圧時間は製品の肉厚やゲートサイズに応じて数秒程度に設定します。射出から保圧への切替点(V/P切替点)は、キャビティが95〜98%充填された時点に設定するのが一般的です。これは、「体積収縮の約10%を保圧で補う」という考え方に基づいています。この初期条件から成形を始め、製品の状態を見ながら微調整を加えていきます。
品質トラブル発生時の見直しチェックリスト
ヒケが発生した場合、やみくもに条件を変更するのではなく、論理的に原因を探る必要があります。まずは、ゲートシール時間が保圧時間より短いのではないかと疑い、前述の重量変化法などで確認します。もしゲートシール前に保圧が終わっているなら、保圧時間を延長します。それでも改善しない場合は、保圧圧力が不足している可能性を考え、バリが発生しない範囲で圧力を段階的に上げていきます。圧力曲線のデータを確認し、V/P切替後に圧力が十分に維持されているか、ゲートシールと圧力降下のタイミングがずれていないかを見抜くことが、的確な対策につながるヒントとなります。
まとめ
射出成形におけるヒケ抑制の本質は、「冷却に伴う樹脂の体積収縮に対して、どれだけ適切に樹脂を補充できるか」に尽きます。そして、その成否を直接的に左右するのが「保圧時間」と「保圧圧力」の設定です。特に、ゲートがいつ固化するのかという「ゲートシール」を中心にした設計的思考は、ヒケ対策の要と言えます。
材料の特性、製品形状、そしてゲート設計に応じた最適化フローを確立し、現場で実践することで、ヒケの発生は大幅に減少させることが可能です。府中プラは、ヒケを防ぐためには「保圧こそが最大の調整パラメータである」と再認識し、科学的アプローチに基づいた成形条件の最適化に取り組んでいます。