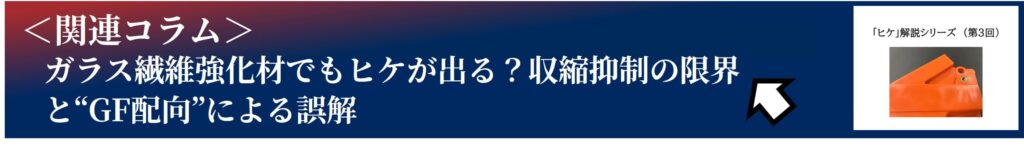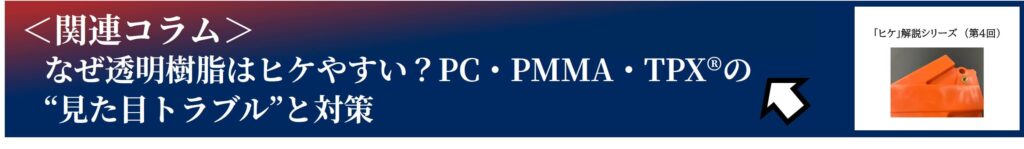寸法不良・反り・強度低下…“ヒケを放置”するとどうなる?二次的トラブルの実例解説

「ヒケ」解説シリーズ第5回
ヒケは、射出成形において最も頻繁に遭遇する典型的な外観不良の一つです。しかし、その扱いについては「多少のヒケは仕方ない」、「見た目の問題だから機能には影響しない」といった認識で、軽視されてしまうことが少なくありません。本当にそうでしょうか。ヒケを単なる「見た目の問題」として放置することは、寸法不良、反り、強度低下といった、より重大な二次的トラブルの引き金となるリスクを内包しています。本コラムでは、ヒケを放置したことで実際に発生したトラブル事例を基に、そのメカニズムと予防策を設計者の視点から解説します。
ヒケの発生原因や初期段階での対策については、
射出成形におけるヒケの原因と対策
で詳しく解説しています。
ヒケが引き起こす4つの二次トラブル
ヒケの裏側には、成形品の品質を根底から揺るがす構造的な問題が潜んでいます。
寸法精度の劣化と嵌合不良
ヒケは、製品表面の単なる凹みではありません。その本質は、局所的な体積収縮が周囲よりも大きく、不均一に発生したことの現れです。つまり、ヒケがある部分は、設計上の狙いよりも大きく縮んでしまっていることを意味します。この局所的な収縮のばらつきが製品全体の寸法を歪ませ、図面上の公差を逸脱する原因となります。特に、複数の部品を組み合わせる製品において、ボス穴の位置ズレや嵌合部の変形は致命的です。後工程である組立の段階で「部品がうまく合わない」、「ネジを締めると浮き上がる」、「組み付け後にガタつきがある」といった問題が頻発し、生産ラインの停止や手戻りを引き起こします。
残留応力による反り・変形
ヒケが発生している製品の内部では、必ずと言っていいほど不均一な応力(残留応力)が蓄積されています。ヒケている部分は強く内側に引っ張られている状態であり、製品全体として応力のバランスが崩れています。成形直後はかろうじて形状を保っていても、この不安定な応力は、輸送中の振動や、使用環境における温度変化(特に高温)によって解放されようとします。その結果、製品に予期せぬ「反り」や「ねじれ」といった変形が生じます。この変形が、他の部品との構造的な干渉や、スイッチ類の接触不良といった誤動作の原因となるのです。
強度・耐衝撃性の低下
ヒケが発生している箇所の内部は、樹脂の充填が不十分で密度が低くなっていたり、微小な空洞(ボイド)が存在したりする可能性が非常に高くなります。これは、構造的に明らかな弱点です。通常の使用荷重では問題が顕在化しなくても、落下などの衝撃が加わった際や、継続的に負荷がかかるような環境下では、このヒケの部分を起点としてクラック(亀裂)や破断が生じやすくなります。製品に求められる本来の強度や耐衝撃性を、ヒケは見えないところで著しく損なっているのです。
外観検査で発見できず、大きなトラブルに
最も厄介なのは、これらの二次トラブルが、出荷時の検査をすり抜けて市場で発生するケースです。特に、時間経過や環境変化によって顕在化する反りや強度低下は、顧客の手に渡ってから初めて発覚します。これは、顧客クレーム、製品の返品・交換といった事態に発展し、企業の信頼を大きく損なうだけでなく、保証対応にかかる莫大な損失につながります。
ヒケを見逃して起きうるトラブル例
ヒケの影響を過少評価するとこのようなトラブルに発展しかねません。十分注意が必要です。
ネジ穴位置ズレ(筐体部品)
機器の外装ケースで、ネジを固定するボスの根元に軽微なヒケがあった。部品単体での寸法検査では公差内に収まっていたが、ヒケによる収縮でボス全体がわずかに内側に傾いていた。組立時に相手部品と合わせるとネジ穴の位置が微妙にずれ、作業者が無理にネジを締め付けた結果、内部に実装されていた高価な電子基板にストレスがかかり、割れてしまうという破損事故につながった。
高温下での反り変形(屋外製品)
屋外に設置されるスイッチのベース部品で、補強リブの裏側にヒケがあった。成形直後は問題なかったが、夏場の炎天下で車内温度が70℃以上に達した際、ヒケの部分に潜んでいた残留応力が熱によって解放され、部品全体が反り返ってしまった。これによりスイッチが筐体から浮き上がり、接触不良による誤作動を引き起こす原因となった。
使用中の破損(配管部の固定爪)
工場の冷却水配管を固定するための樹脂製クリップで、勘合用の爪の付け根にヒケが発生していた。見た目ではほとんど分からなかったものの、この部分の強度は著しく低下していた。配管の振動と内圧による継続的な負荷に長期間耐えきれず、ある日突然、爪が疲労破壊で折損した。結果として配管が外れて漏水事故が発生し、生産ラインを長時間停止させてしまった。
加工工程での寸法不良(ネジ成形品)
特殊な形状のネジ山を直接成形する部品において、ヒケによる不均一な収縮でネジ山の高さが部分的に低くなっていた。組立工程でトルクレンチを用いて締め付けた際に、この低い部分が原因で規定トルクに達する前にネジが空転してしまうという不良が発生した。原因が特定されるまで多くの時間を要し、最終的には全数に対してネジ山の高さを測定するという膨大な検査・選別作業が発生した。
なぜヒケの管理は難しいのか?
ヒケは他の成形不良と比べて、管理が容易ではないケースが多いのはなぜでしょうか。
外観検査では“見えない”ケースが多い
特に黒色などの濃色成形品や、表面にシボ加工などのテクスチャが施されたマットな製品では、光の反射が抑えられるため、ヒケによる僅かな凹みが非常に視認しにくくなります。検査員の経験や熟練度、検査環境の照明などにも大きく左右され、「注意して見なければ気付かない」、「光の当たる角度によっては見えない」といった理由で見逃されてしまうのです。
寸法公差内でも“機能不良”が起こる
図面に指示された特定箇所の寸法を測定し、公差内に収まっていることで「合格」と判断されるケースがあります。しかし、前述の通り、ヒケによる影響は製品全体の歪みや反りといった「形状」に現れます。図面で指示されていない部分が変形することで、嵌合不良などの機能的な問題を引き起こすのです。「寸法はOKなのに、なぜか組めない」という問題の裏には、ヒケが隠れていることがあります。
関係者間の“品質のギャップ”
最も根深い問題は、関係者間の品質に対する認識のギャップとコミュニケーション不足です。「これくらいのヒケは許容範囲だろう」、「承認された限度見本内だから問題ない」といった判断が、社内外の関係者間で微妙にズレがあるという状況です。これは、ヒケに限らず、あらゆる不良現象に共通することですが、関係者間で品質の目合わせをすることは、成形品を扱う関係者の間で永遠のテーマとも言えます。
ヒケを二次トラブルにしないための設計・管理手法
ヒケに起因する二次トラブルを防ぐには、部門を超えた総合的なアプローチが必要です。
肉厚変化と構造設計の工夫
対策の原点は設計にあります。ヒケの根本原因である「急激な肉厚変化」を設計段階で徹底的に排除することが基本です。リブやボスの肉厚を母材に対して適正な比率に抑えるといった設計セオリーを遵守します。さらに一歩進んで、万が一ヒケが発生しても、それが製品の嵌合精度や強度に影響を及ぼさないような、リスクを回避する構造設計を検討することも重要です。
ゲートシールタイミングと保圧制御の徹底
ヒケの多くは、成形条件、特に保圧工程の不具合に起因します。樹脂の補充経路であるゲートが固化する「ゲートシール時間」を正確に把握し、それに見合った適切な保圧時間と圧力を設定することが、ヒケを防ぐ直接的な対策となります。CAE解析による事前予測や、実際の成形モニタリングデータを活用し、ヒケが発生するメカニズムを「見える化」して科学的に管理することが求められます。
図面仕様にできない品質リスクの共有
寸法公差や外観限度見本だけでは、ヒケがもたらす機能的なリスクを管理することはできません。設計者は、なぜその部分にヒケが出てはいけないのか、放置するとどのような不具合につながるのか、その「設計意図」や「背景」を金型メーカーや成形現場と密に共有することが不可欠です。そのリスクを品質基準書や作業標準書に具体的に明文化し、関係者全員の共通認識として工程管理に落とし込む必要があります。
まとめ
ヒケは、単なる外観不良で終わらないことがあります。それは、寸法不良、反り、強度低下といった重大な二次トラブルを引き起こす、構造的な欠陥に繋がりうる「予兆」という面もあります。
この問題を解決するためには、「ヒケを発生させない設計」、「安定して再現できる成形技術」、そして「図面に書かれないリスクを共有するモノづくりの姿勢」という三つの要素が重要だと考えています。特に高い信頼性が求められる製品の設計・開発においては、ヒケを「未然に防止すべき構造的不良」として捉え、開発の初期段階から真摯に取り組むべきであると府中プラは考えています。