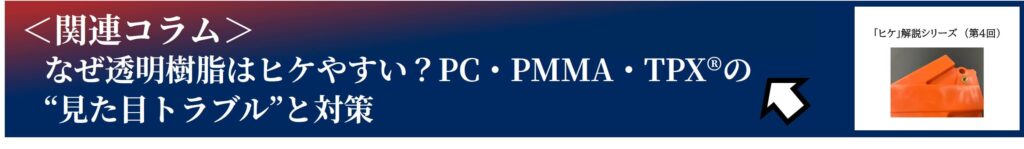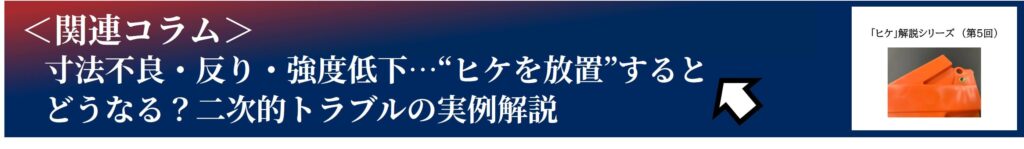ガラス繊維強化材でもヒケが出る?収縮抑制の限界と“GF配向”による誤解

「ヒケ」解説シリーズ 第3回
射出成形の設計現場では、ヒケ対策の有効な手段として「ガラス繊維(GF)入り材料を使えばヒケは抑えられる」という考えが広く浸透しています。確かにGF強化材は樹脂の収縮を抑制する効果がありますが、それを過信した結果、「GF入り材料を使ったのにヒケが解消されない」、「むしろヒケが目立つようになった」といった想定外のトラブルに直面する事例を、私は材料メーカーに在籍していた頃、しばしば見てきました。本コラムでは、GFが収縮を抑制するメカニズムとその限界を明らかにし、設計・成形段階で見落とされがちな“GF配向”のリスクと対策について、府中プラの実務的な視点から解説します。
GFがヒケを抑えるメカニズムとは?
まず、なぜガラス繊維(GF)を添加するとヒケが抑制されるのか、その基本的な原理を理解することが重要です。
無機繊維による寸法安定性の向上
ヒケの根本原因は、樹脂が溶融状態から冷却・固化する際の体積収縮にあります。ガラス繊維は樹脂と比較して、熱による寸法変化(線膨張率)や冷却時の収縮率が極めて小さい無機材料です。このGFを樹脂に混ぜ込むと、樹脂の中にGFが骨格のように分散し、樹脂単体で収縮しようとする動きを物理的に抑制します。これにより、成形品全体の収縮率が低減され、結果としてヒケの発生が抑えられます。また、GFは樹脂よりも熱伝導率が高いため、製品内部の熱が外部へ伝わりやすくなり、肉厚部の冷却を促進する効果も、間接的にヒケ抑制に寄与します。
GFの含有量とその効果
GFによる収縮抑制効果は、基本的にその含有量に比例して高まります。しかし、含有量を増やせば増やすほど良いというわけではありません。GFの含有率が20〜30wt%(重量パーセント)を超えてくると、溶融樹脂の流動性が低下して金型への充填が難しくなったり、製品表面にGFが浮き出て外観品質を損ねたり、金型の摩耗を促進したりといったデメリットが顕在化します。そのため、多くの工業製品では、ヒケ抑制効果と成形加工性、コストのバランスが取れた「GF30%」といったグレードが標準的に使用される傾向にあります。
それでもヒケが出るのはなぜか?
GFによる収縮抑制のメカニズムを理解してもなお、現場でヒケ問題がなくならないのには、いくつかの明確な理由が存在します。
GFは万能ではない:収縮抑制“できない箇所”がある
GFによる収縮抑制効果は、成形品全体に均一に作用するわけではありません。特に、リブやボスといった局所的な肉厚部では、その効果に限界が生じます。これらの箇所では、GFによる抑制効果を上回るほどの大きな体積収縮が発生するため、ヒケのリスクは依然として残ります。また、金型内の複雑な三次元構造を持つ部分や、樹脂が最後に流れ着く充填末端領域では、GFの分散が不均一になったり、圧力が十分に伝わらなかったりするため、GFの効果が十分に発揮されず、ヒケが発生しやすくなります。
材料特性を含めたヒケ全体の発生要因と対策整理については、
射出成形におけるヒケの原因と対策
を参照してください。
ヒケが“目立ちやすくなる”材料特性
GF入り材料を使った際に、「ヒケがむしろ目立つようになった」と感じることがあります。これは、ヒケ自体が大きくなったわけではなく、材料表面の特性変化によって視覚的に強調されているケースがほとんどです。非強化の樹脂(ナチュラル材)は表面に光沢が出やすいのに対し、GF強化材は表面に微細な繊維が露出するため、光沢が抑えられたマットな質感になります。このマットな表面にヒケによる僅かな凹みが生じると、光の反射具合が周囲と大きく異なり、人の目にはかえって外観不良として認識されやすくなるのです。特に、黒色などの濃色でマットな仕上げが求められる製品では、この傾向が顕著になります。
最大の要因:「GF配向」による寸法不均一とヒケ
GF強化材でヒケが発生する最も本質的で、かつ見落とされがちな原因が「GFの配向」です。GFは細長い繊維状のフィラーであり、金型内を樹脂が流動する際に、その流れに沿って向きを揃える性質があります。これを「配向」と呼びます。
問題は、GFが配向した方向(流れ方向)とその直交方向とで、収縮率が大きく異なる点にあります。GFは繊維の長手方向にはほとんど収縮しないため、GFが流れに沿ってきれいに整列した方向の収縮率は非常に小さくなります。しかし、繊維と繊維の間を埋める樹脂は自由に収縮できるため、流れと直交する方向の収縮率は相対的に大きくなります。この収縮率の差(異方性)が、製品に意図しない反りを引き起こしたり、局所的なヒケの原因となったりするのです。
設計・成形時に起きやすい「GF配向」による誤解
「GFを入れたから安心」という考えは、この配向の問題を見過ごす原因となります。対策は、設計・金型の段階から始まります。
「GFを入れたのにヒケた」は成形設計ミスの可能性
GF強化材でヒケが出た場合、安易に材料のせいにするべきではありません。多くの場合、GFの配向特性を考慮しない設計や成形に問題が潜んでいます。「樹脂は流れ方向に沿って充填される」という基本に依存しすぎ、ゲート位置を単純に決めると、製品の特定部分でGF配向が極端に偏り、直交方向の大きな収縮によってヒケが誘発されることがあります。経験則としての「流動方向は寸法が安定する」という知識は、その直交方向での問題を無視している可能性があり、万能ではないことを理解する必要があります。
金型設計で配向を制御する方法
GFの配向はある程度、金型設計によってコントロールすることが可能です。単一のゲートから放射状に樹脂が流れると、配向の偏りが大きくなります。これを緩和するため、スリットゲートやファンゲートのように幅の広いゲートを用いて樹脂を面で流し、配向を均一化する方法があります。また、製品の形状が複雑な場合は、多点ゲートを採用して複数の方向から樹脂を充填させ、配向のバランスを取ったり、ウェルドライン(樹脂の合流点)の位置を意図的にコントロールしたりする「配向設計」という発想が極めて重要になります。
配向が乱れる箇所の冷却補強
リブやボスのような垂直な構造部や、樹脂の流れが滞留するような箇所では、GFの配向が乱れたり、弱くなったりします。このような場所は、GFによる収縮抑制効果が十分に得られない上に、冷却も遅れがちになるため、ヒケの発生リスクが非常に高くなります。対策として、該当箇所の金型に冷却水管を近接させるなどの冷却強化や、収縮を補うための保圧条件の最適化が不可欠です。特にGF含有率が高い材料では、金型温度の僅かな偏りが配向の乱れとヒケに直結するため、精密な温調管理が求められます。
材料・設計・成形の“合わせ技”でヒケを防ぐには
GF強化材のヒケ対策は、一つの要素だけでは完結しません。総合的なアプローチが必要です。
材料特性に応じたリブ・ボスの設計指針
GF強化材を使用する場合でも、ヒケ対策の設計基本原則は変わりません。リブの肉厚を母材の40〜70%に抑える、ボスには肉抜きを施すといったセオリーは遵守する必要があります。非強化の透明樹脂などとは異なり、GF強化材では製品内部のボイド(空隙)が見えにくいため、外観上のヒケだけを気にしがちです。しかし、本質的な対策は、内部応力や収縮バランスを考慮した「構造バランス」でヒケを防ぐという考え方にシフトすることが重要です。
成形条件によるGF配向とヒケの両立制御
成形条件もGFの配向に影響を与えます。一般的に、射出速度を速くするとGFの配向は強くなる傾向がありますが、樹脂のせん断発熱やガスの巻き込みといった別の問題を引き起こす可能性があります。金型温度を高く設定すると樹脂の流動性が向上し、配向が緩和されることもありますが、サイクルタイムの延長につながります。射出速度、金型温度、保圧条件などを適切に管理し、求める製品強度に必要な配向を確保しつつ、ヒケを抑制するという二律背反の課題を両立させる、高度な応力コントロールが求められます。
まとめ
ガラス繊維(GF)強化材は、正しく使えばヒケ対策に有効な優れた材料です。しかし、その効果は万能ではなく、「GFを添加しても物理的に収縮を抑制しきれない箇所がある」、「GFの配向によって新たな収縮差が生まれる」という点を正しく理解することが、トラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。
材料の特性だけに頼るのではなく、GFの配向を考慮した製品設計、配向をコントロールする金型設計、そして配向とヒケを両立させる成形条件の最適化という、設計・金型・成形の「三位一体」で対策を講じる必要があります。府中プラでは、材料の特性を最大限に引き出すための総合的なアプローチで、お客様の製品品質向上に貢献します。