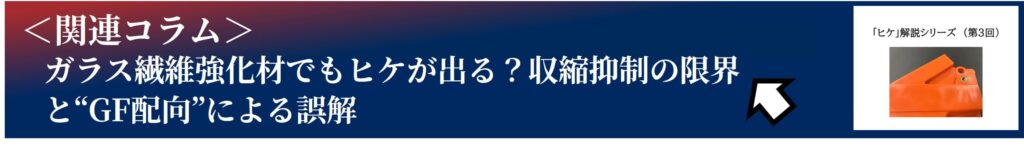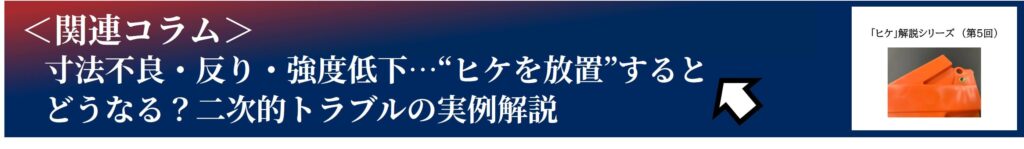なぜ透明樹脂はヒケやすい?PC・PMMA・TPX®の“見た目トラブル”と対策

「ヒケ」解説シリーズ第4回
射出成形におけるヒケは、あらゆる製品で避けたい外観不良ですが、特に透明部品においてはその深刻度が格段に増します。不透明な部品であれば単なる表面の凹みで済む問題も、透明部品では光の透過や屈折を歪ませ、製品の意匠性や光学性能そのものを著しく損なう致命的な欠陥となるからです。レンズ、ライトガイド、意匠カバーなど、透明性が価値の源泉である部品にとって、ヒケは機能不良に等しいと言えます。本稿では、なぜ透明樹脂が本質的にヒケやすいのか、その原因を掘り下げ、主要な材料別の対策から光学部品に求められる実務的なノウハウまで、府中プラの知見を交えて解説します。
透明樹脂に限らず、ヒケの基本的な発生原理や対策の考え方は、
射出成形におけるヒケの原因と対策
で整理しています。
透明樹脂にヒケが出やすい主な要因
透明樹脂がヒケやすい背景には、材料特性、成形条件のシビアさ、そして求められる品質レベルの高さという、三つの複合的な要因が存在します。
材料特性:強化材でごまかせない“素の収縮”
一般的な不透明の樹脂部品では、ガラス繊維(GF)などの強化フィラーを添加することで、樹脂の収縮自体を物理的に抑制し、ヒケを低減させる手法が広く用いられます。しかし、透明性を維持しなければならない透明樹脂では、このような不透明なフィラーを添加することはできません。つまり、透明樹脂は樹脂本来の収縮(素の収縮)と真正面から向き合わなければならない宿命にあります。PMMA(アクリル)に代表されるように、剛性が比較的低く、粘度が高い材料も多く、冷却時の収縮応力に負けて表面が凹みやすい傾向があります。
成形条件のシビアさ:高い金型温度のジレンマ
透明部品には、曇りのない美しい表面が求められます。この高い表面転写性を実現するため、透明樹脂の成形では、溶融樹脂の流動性を高めて金型の細部まで行き渡らせる必要があり、一般的に金型温度を比較的高く設定します。しかし、高い金型温度は、成形品全体の冷却時間を長引かせ、結果として総収縮量を増大させるというジレンマを抱えています。冷却がゆっくり進むほど、内部の収縮がより大きく進行し、ヒケが発生しやすくなるのです。美しい表面を得るための高温設定が、皮肉にもヒケのリスクを高めるという、非常にシビアな条件下での成形が求められます。
高外観要求による“許容範囲の狭さ”
最大の要因は、求められる品質基準の厳しさにあります。不透明な部品であれば、ごく僅かなヒケは光の加減で見え隠れし、許容範囲と見なされるかもしれません。しかし、透明部品の場合、僅かなヒケでも光の通り道を歪ませ、レンズであれば焦点がずれ、意匠部品であれば向こう側の景色が歪んで見えます。内部を通過する光が、ヒケの存在を明確に映し出してしまうのです。このように、不良として検知されるレベルが他と一線を画すため、「ヒケが出やすい」のではなく「ヒケが許されない」という厳しい現実があります。
材料別のヒケ傾向と対策
一口に透明樹脂と言っても、材料ごとに特性は大きく異なります。ここでは代表的な3つの材料について、ヒケ対策の勘所を解説します。
PC(ポリカーボネート):厚肉部での内部収縮に注意
PCは、優れた耐衝撃性と透明性から広く使用される材料です。非晶性樹脂のため成形収縮率自体は比較的小さいですが、溶融時の粘度が高く、流動性が良くありません。そのため、特に厚肉形状の製品では、内部まで十分な保圧が伝わりにくく、表面は固まっているのに内部で大きな収縮が起こり、深いヒケや内部の空洞(ボイド)を発生させやすいという特徴があります。
PCのヒケを防ぐには、十分な保圧時間と圧力を確保することが基本です。ゲートは製品の最も厚い部分に直接配置(ダイレクトゲートなど)し、収縮を補うための樹脂の通り道を確保します。また、設計段階で可能な限り肉抜きを行い、極端な厚肉部を作らないことが重要です。
PMMA(アクリル樹脂):ヒケが“割れ”の起点になるリスク
PMMAは、最高の透明度と表面光沢を誇りますが、PCに比べて剛性が低く、脆いという弱点があります。この脆さがヒケ問題と結びつくと、深刻な事態を招きます。ヒケによる凹みの角部分には応力が集中しやすく、この応力集中点が起点となって、成形後の冷却過程や使用中にクラック(割れ)へと進行するリスクがあるのです。
PMMAの成形では、過剰な保圧による内部応力の発生を極力避ける必要があります。金型温度を高めに設定し、射出速度を適切にコントロールすることで、樹脂を無理なく充填し、内部応力を緩和させることがヒケと割れの同時対策となります。ヒケを「発生させない」ための、より緻密な製品・金型設計が求められます。
TPX®(ポリメチルペンテン):結晶性樹脂特有の大きな収縮
三井化学(株)の登録商標であるTPX®は、耐熱性や離型性に優れた透明樹脂ですが、PCやPMMAと決定的に違うのは結晶性樹脂であるという点です。結晶性樹脂は、融点付近で分子が規則正しく整列する際に急激な体積収縮を起こすため、非晶性樹脂に比べて本質的にヒケが大きく発生しやすい性質を持っています。
TPX®のような結晶性透明樹脂では、設計段階での厳密な肉厚の均一化が絶対条件となります。リブやボスを設ける場合は、母材肉厚に対する比率をよりシビアに管理し、厚みの変化を極力滑らかにする必要があります。また、冷却速度のコントロールも重要で、金型内で均一に冷却を進めることで、収縮のばらつきを抑え、ヒケを防ぎます。
光学部品でヒケを抑えるための実務対策
レンズやプリズムといった光学部品では、ヒケは即、性能劣化につながります。ここでは、より高度な対策が求められます。
金型温度と冷却系設計の重要性
光学部品の成形では、単に金型を冷やすのではなく、「均一に」、「ゆっくりと」冷却し、樹脂の内部応力を極限まで低減させることが重要です。そのため、製品形状に沿って緻密に設計された冷却回路や、金型表面を急速に加熱・冷却して転写性と低ひずみを両立させる特殊な温調技術が有効となります。金型温度の僅かなムラが、そのままヒケや性能低下に直結するため、冷却系設計はまさに成否を分ける心臓部です。
ヒケと内部ひずみ(複屈折)の密接な関係
ヒケは表面の凹みとして現れますが、その根本原因は製品内部の不均一な収縮応力(残留ひずみ)にあります。この内部応力は、偏光板を通して光を当てることで「複屈折」と呼ばれる虹色の縞模様として可視化できます。ヒケが大きい製品は、ほぼ例外なく強い複屈折を示します。つまり、ヒケをなくすための対策(保圧の最適化、均一冷却など)は、光学性能を低下させる複屈折を低減させる対策と同義です。表面の形状と内部の応力は、表裏一体の関係にあるのです。
設計段階での徹底した対策:肉厚均一化とゲート設計
結局のところ、最も効果的な対策は設計段階にあります。光学部品、特にレンズでは、僅かな肉厚差が焦点距離や収差に影響するため、設計の基本は「完全な肉厚均一化」です。機能上どうしても肉厚変化が必要な場合でも、その変化は極めて滑らかでなければなりません。ゲートは、圧力伝達が最も効率的な製品の最も厚い部分に配置し、十分な保圧がかけられるダイレクトゲートやファンゲートが選択されることが多くなります。同時に、成形後にゲートをカットした跡が光学有効面にかからないよう、細心の注意を払った位置決めが不可欠です。
まとめ
透明部品にとって、ヒケは単なる外観不良ではありません。それは製品の価値を根底から覆しかねない機能不良であり、“ヒケ=クレーム”に直結する重要管理項目です。透明樹脂が持つ本質的なヒケやすさを克服するには、材料特性への深い理解はもちろん、美しい表面を得るための高温設定と収縮抑制という相反する要求を両立させる、高度な金型技術と成形ノウハウが不可欠です。府中プラは、この高難易度の課題に対し、設計・金型・成形の三位一体となった総合的なアプローチで、お客様の期待を超えるクリアな品質を実現します。