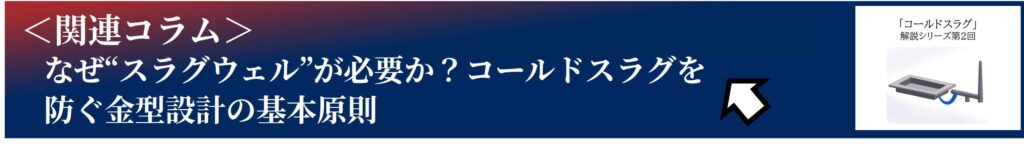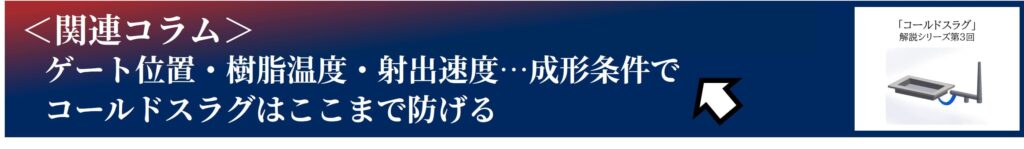冷えた樹脂が不良を生む!射出成形におけるコールドスラグの正体と発生メカニズム

「コールドスラグ」解説シリーズ第1回
射出成形において発生する「コールドスラグ」は、ヒケやバリといった代表的な不良に比べると、その重要性が見過ごされやすい傾向にあります。しかし、この冷えた樹脂の塊は、製品の外観品質を損なうだけでなく、機械的強度や密封性といった信頼性にも深刻な影響を及ぼす重要な成形不良の一つです。特に若手の技術者にとっては「名前だけは聞いたことがある」という程度の理解に留まり、その本質的なリスクが見過ごされているケースも少なくありません。
本コラムでは、このコールドスラグが「何であり、なぜ発生し、どのような問題を引き起こすのか」という基本に立ち返り、その発生原理から設計・成形への影響までを、実務的な視点から解説します。
コールドスラグとは何か? ― 不良の定義と特徴
コールドスラグとは、射出成形機のノズル先端や、金型内のスプルー・ランナーといった樹脂の流路内で先行して冷却された樹脂の一部が、後から流れてくる高温の溶融樹脂と共に金型キャビティ内へ流入し、製品に混入してしまう現象、およびその樹脂塊そのものを指します。
製品上では、この冷え固まった樹脂が周囲の正常な樹脂と完全に溶け合わないために、様々な外観不良として現れます。例えば、製品表面に斑点状の模様や異物のように見える塊、あるいは滑らかな光沢の中に部分的なムラ(艶引け)として観察されます。特に透明な樹脂で成形された部品においては、その存在はより顕著です。内部に曇りや白濁、まるで水の中に墨を一滴垂らしたようなモヤっとした模様として現れ、製品のクリアな外観を著しく損ないます。その見た目から、外部から混入したコンタミネーション(異物汚染)と誤認されることも少なくありません。
なぜ発生するのか? ― メカニズム解説
コールドスラグの発生メカニズムは、樹脂の「冷却」という物理現象に起因します。射出成形プロセスを時系列で追うと、その発生過程が明確になります。
成形が1サイクル完了し、次のショットが開始されるまでの間、射出成形機のノズル先端部は金型のスプルーブッシュに接触したまま待機しています。スプルーブッシュは通常、冷却水によって金型本体と同じ温度(数十℃程度)に保たれているため、ノズル先端にある高温の溶融樹脂(200℃以上)の先端部分は、この金属壁との接触によって急速に熱を奪われ、冷えて固まりかけの状態になります。これが「コールドスラグ」の元です。
そして次の射出工程が始まると、このノズル先端で冷やされた樹脂塊が、後続の高温の溶融樹脂に押し出される形で、先頭を切ってスプルー内に進入します。同様の現象は、ランナーの分岐点や行き止まりといった「死角部」でも発生する可能性があります。もし、金型にこの冷えた樹脂塊を意図的に捕捉・排出するための「スラグウェル(コールドスラグ溜まり)」が設けられていない、あるいはその機能が不十分な場合、コールドスラグはランナーを通過し、ゲートからキャビティ内へと流れ込んでしまいます。
キャビティ内でコールドスラグは、後から来る正常な溶融樹脂と完全には融合しません。低温で粘度が高まっているため、周囲と混ざり合うことなく、そのまま製品の一部として固化します。これが、ゲート位置が不適切であったり、樹脂温度が低すぎたり、そして何よりもスラグウェルが未設置であるといった条件が重なることで発生する、コールドスラグの典型的なメカニズムです。
なぜ問題なのか? ― 信頼性上のリスク
コールドスラグによる問題は、単なる外観不良に留まりません。製品の信頼性を根底から揺るがす、潜在的なリスクを内包しています。まず、外観不良としての影響は深刻です。高い意匠性が求められる化粧品容器や家電製品の筐体、精密な光学特性が要求されるレンズや導光板、あるいは医療機器の部品などでは、わずかな斑点や曇りも許容されません。コールドスラグは、これらの製品にとって致命的な欠陥となります。
しかし、より重大なのは、製品内部に潜む構造的な欠陥としてのリスクです。コールドスラグは、周囲の正常な樹脂と分子レベルで完全に一体化(溶着)していません。そのため、その境界部分は物理的な不連続面となり、構造上の弱点となります。この不連続面は、製品に荷重がかかった際の応力集中点となり、本来の材料物性を発揮できなくなります。結果として、層間強度の低下や、特定の方向からの衝撃に対する脆弱性を生み出します。
さらに、気密性や液密性が求められる容器や配管部品では、このコールドスラグと母材との界面が、微小なリーク(漏れ)の経路となる可能性があります。また、繰り返し応力がかかる部品では、この界面が疲労破壊の起点となり、想定よりもはるかに短い寿命で製品が破損する原因にもなり得ます。目視では確認できない製品内部に存在するコールドスラグは、まさに「見えない時限爆弾」として、製品の長期的な信頼性を脅かすのです。
設計者が知っておくべき“入口の問題”
コールドスラグは、成形現場での条件調整で改善することもありますが、その根本原因を突き詰めると、多くの場合、より上流の工程にたどり着きます。府中プラでは、コールドスラグを「金型構造と樹脂流動の設計が不適切だった」ことの現れであると捉えています。

つまり、これは樹脂が金型キャビティに到達するまでの「入口」で発生する問題であり、その対策は入口の設計、すなわち金型設計の段階で講じられるべきだということです。スプルー直下やランナーの突き当たりに、冷えた樹脂を捕捉するためのスラグウェルが設置されていない、あるいはそのサイズや形状が不適切で機能していない。ゲートの形状や位置が、樹脂の流れに対してコールドスラグを巻き込みやすい設計になっている。これらはすべて、金型設計段階での配慮不足が背景にあります。
成形現場での樹脂温度の引き上げや射出速度の調整は、あくまで対症療法であり、根本的な解決にはなりません。真の対策は、コールドスラグの発生を物理的に防ぐための「予防設計」を、金型に織り込むことなのです。次回以降のコラムでは、この予防設計の要となる「金型設計」と、それを補完する「成形条件」について、具体的な対策をそれぞれ詳しく解説していきます。
まとめ
コールドスラグは、時に異物と見紛う外観不良を引き起こし、目に見えない内部欠陥として製品の信頼性を損なう、決して軽視できない成形不良です。その原因は、成形機のノズル先端や金型内で冷えた樹脂がキャビティに混入するという、単純な物理現象で説明できます。
しかし、この現象の根本には、金型設計、特に樹脂がキャビティに流れ込むまでの流路設計における問題が潜んでいることが少なくありません。したがって、実務における本質的な対策は、発生後の条件調整ではなく、発生させないための「予防設計」が鍵となります。本シリーズを通じて、このコールドスラグという問題に対し、設計・金型・成形条件の各視点から体系的にアプローチしていきます。