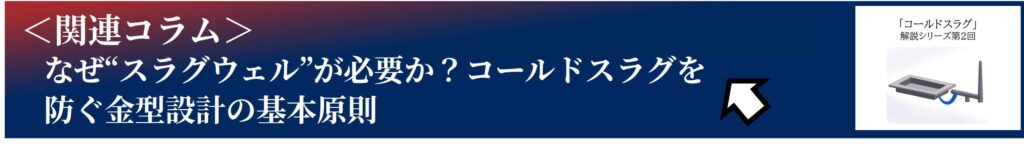ゲート位置・樹脂温度・射出速度…成形条件でコールドスラグはここまで防げる

「コールドスラグ」解説シリーズ第3回
前回のコラムでは、金型設計におけるスラグウェルの重要性を解説しました。しかし、どれだけ優れたスラグウェルを設けても、成形条件が不適切であればコールドスラグを完全に防ぐことはできません。樹脂の流動前端の挙動は、その「温度・速度・圧力」といった条件のわずかな違いによって大きく変化し、スラグウェルの効果を無効化してしまうことさえあるからです。
金型という「ハードウェア」の対策と、成形条件という「ソフトウェア」の制御は、コールドスラグ対策における車の両輪です。本シリーズの最終回となる本コラムでは、この「ソフトウェア」の側面に焦点を当て、コールドスラグを抑制するために設計者と成形担当者が共に意識すべき、具体的な条件設定の基本を整理します。
ゲート位置と流動設計の影響
成形条件の議論に入る前に、その前提となるゲート位置と流動設計について触れておく必要があります。ゲートはキャビティへの最終入口であり、その位置はコールドスラグが製品のどこに、どのように影響を及ぼすかを決定づけるからです。
例えば、流動距離が長く、分岐が多い複雑な形状の製品では、ランナー内で発生したコールドスラグが意図しない経路を辿り、スラグウェルをすり抜けてしまう、いわば“迷子”の状態になることがあります。また、ゲートの位置が不適切で、キャビティ内の最初に充填される領域が製品の意匠面や重要機能部である場合、たとえ微量なコールドスラグでも致命的な不良に直結します。
これを防ぐため、製品設計の段階から「コールドスラグが流れ込むこと」をある程度想定した設計思想を取り入れることも有効です。例えば、キャビティ内で最初に充填される領域を、意図的に製品の機能や外観に影響のない部分(例えば、後工程で切除されるタブや、見えない裏面など)に設定するのです。これにより、万が一コールドスラグがキャビティに侵入しても、その影響を最小限に抑えることができます。
成形条件で変わる流動前端の温度
コールドスラグは「冷えた樹脂」であるため、その発生を抑制する最も直接的なアプローチは、流動前端の温度をいかに下げないか、という点に集約されます。この結果は、本コラムで示す実践的な調整指針の有効性を裏付けるものです。
樹脂温度:設定温度が低すぎると、ノズル先端で冷却されやすくなるため、コールドスラグの発生量そのものが増加します。逆に、温度を上げればスラグは発生しにくくなりますが、上げすぎると樹脂の熱分解(デグレード)を引き起こし、物性低下やガス焼けといった別の不良の原因となるため、材料メーカーが推奨する適正範囲内での調整が必須です。
金型温度:金型温度が低すぎると、ノズルから射出された樹脂がスプルーやランナーの冷たい壁面に接触した際に急冷され、流動前端の温度低下、すなわちコールドスラグの形成を助長します。金型温度を適切に保つことは、樹脂の流動性を安定させ、前端の温度低下を防ぐ上で非常に重要です。
射出速度:射出速度が遅すぎると、樹脂が金型内を移動する時間が長くなり、その間に金型壁面から熱を奪われて流動前端の温度が低下します。これを防ぐためには、ある程度の高速射出によって、樹脂が冷える前にランナーを通過させ、キャビティに到達させる工夫が必要です。高速で流れる樹脂は、せん断発熱によって自ら温度を維持する効果もあり、コールドスラグの抑制に繋がります。
圧力設定・保圧制御の観点
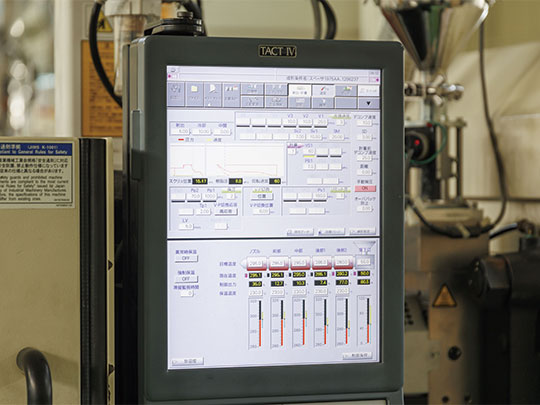
圧力の制御も、コールドスラグの挙動に影響を与えます。充填完了までの射出圧力が低すぎると、樹脂の流れに勢いがなくなり、先に冷えて粘度が高まったコールドスラグが流動の主導権を握ってしまい、スラグウェルに捕捉されにくくなることがあります。
適切な射出圧力をかけることで、後続の高温樹脂が勢いよく流れ、先行するコールドスラグを力強くスラグウェルへと押し込む効果が期待できます。また、保圧工程においても、適切な圧力をかけることで、キャビティ内に侵入してしまった微小なコールドスラグの塊を、後から来る高温高圧の樹脂で押し潰し、周囲と溶着させて目立たなくする効果を狙うこともできます。ただし、これはあくまで最終手段であり、根本的な解決ではないことを理解しておく必要があります。コールドスラグ対策の基本は、あくまでも「キャビティに入れない」ことです。
成形現場でできる実践的対策
理論的な条件設定に加え、成形現場のオペレーションレベルで実行できる、より実践的な対策も存在します。
一つは、ショットの直前に、ごく微量の樹脂をノズル先端から排出しておく「パージ」という操作です。これにより、待機時間中にノズル先端で冷やされた樹脂の塊をあらかじめ捨ててから本番の射出を行うため、コールドスラグの発生源を物理的に除去できます。自動化された成形ラインでは難しい場合もありますが、手動での試作成形などでは非常に有効な手法です。
また、金型の昇温タイミングの最適化も効果的です。特に生産開始直後は金型が十分に温まっておらず、コールドスラグが発生しやすい状態です。生産開始前に金型をしっかりと予熱し、安定した温度に到達してから成形を始めることで、初期の不良率を大幅に低減できます。
まとめ
本シリーズでは全3回にわたり、見過ごされがちな成形不良「コールドスラグ」について、その正体から対策までを体系的に解説してまいりました。
第1回では、コールドスラグが「ノズル先端などで冷やされた樹脂の塊」という物理的な現象であり、それが製品の外観品質だけでなく、強度や気密性といった信頼性を損なう潜在的リスクであることを明らかにしました。問題の本質を正しく理解することが、全ての対策の出発点となります。
続く第2回では、最も効果的なハードウェア対策である「スラグウェル」に焦点を当てました。コールドスラグをキャビティに到達する前に物理的に捕捉するこの構造は、いわば製品品質を守るための「保険」です。その配置、容積、通気性といった設計の要点を押さえることで、不良発生率を劇的に低減できることを示しました。
そして最終回である本コラムでは、金型というハードウェアを補完するソフトウェア、すなわち「成形条件」による対策を解説しました。樹脂温度、金型温度、射出速度といったパラメータを適切に制御し、樹脂の流動前端の温度をいかに維持するかが、スラグの発生を抑制し、スラグウェルを効果的に機能させる鍵となります。
結論として、コールドスラグ対策は、金型設計と成形条件のどちらか片方だけでは不十分です。設計者と成形担当者が連携し、「発生したスラグを確実に捕捉する構造(金型)」と、「スラグの発生そのものを抑制する流れ(成形条件)」の両輪を追求すること。こうしたアプローチこそが、コールドスラグという問題を根本から解決する唯一の道筋なのです。