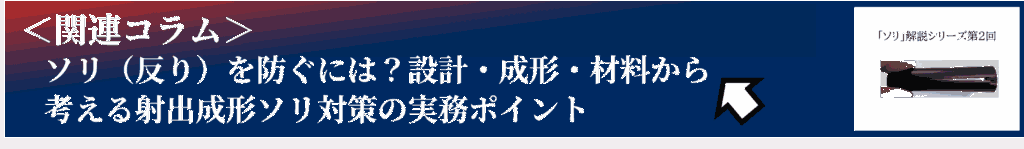なぜソリ(反り)が起きるのか?射出成形におけるソリの発生メカニズムと原因整理

「ソリ」解説シリーズ第1回
射出成形において、「ソリ」または「反り」と呼ばれる成形不良は、多くの製造現場で直面する根深い課題の一つです。このソリは、単に製品の見た目を損なうだけでなく、部品同士の嵌合性を悪化させ、厳密な寸法精度が求められる製品においては致命的な欠陥となり得ます。アッセンブリ工程での不具合や、製品寿命の低下にも直結するため、その影響は軽視できません。
この問題を解決するためには、成形品の開発初期段階、すなわち製品設計や金型設計、成形条件を設定する時点で、ソリが発生する根本的なメカニズムを深く理解しておくことが不可欠です。府中プラは、現象の背後にある物理的な原理を正しく把握し、予防的な対策を講じることが高品質なものづくりへの鍵であると考えます。本コラムでは、ソリの発生メカニズムを体系的に解き明かし、その原因を整理することで、現場での具体的な対策立案の一助となることを目指します。
ソリとは何か?現象の定義と分類
まず、ソリという現象を明確に定義することから始めます。府中プラでは、ソリを「射出成形によって作られた成形品が、金型から取り出されて冷却が進む過程、あるいはその後に、設計意図とは異なる形状に曲がったり、ねじれたりする変形」と捉えています。これは、成形直後の寸法誤差とは性質が異なります。ソリの背景には、成形品の内部に蓄積された「残留応力」や、部位による「異方性収縮」が存在し、これらが解放されることで変形が引き起こされるのです。
ソリの現れ方は一様ではなく、代表的なパターンとしては、全体湾曲(平板状の製品全体が、弓なりに曲がってしまう)、端部反り返り(製品の端部やフランジ部分が、設計平面から浮き上がるように反り返る)、スクリュー反り(平板状の製品が、プロペラのように対角線方向にねじれてしまう)の3つでしょう。これらの変形は、製品の機能性や組み立て精度に直接的な影響を及ぼすため、成形不良の中でも特に管理が重要視されます。
ソリの三大要因:成形条件・金型設計・材料特性
ソリの発生原因は、単一の要素で説明できるほど単純ではありません。多くの場合、「成形条件」、「金型設計」、「材料特性」という三つの大きな要因が複雑に絡み合って発生します。府中プラは、これらの要因を個別に分析するだけでなく、それらが相互にどう影響し合っているのかを理解することが、真の原因究明への近道だと考えています。
例えば、特定の材料(材料特性)は特定の成形条件(温度や圧力)でソリやすい性質を持っていたり、不適切な金型設計が成形条件の最適化を困難にしていたりします。そのため、問題解決にあたっては、これら三つの視点から総合的にアプローチすることが不可欠です。
成形条件に起因するソリ
成形現場で調整可能な「成形条件」は、ソリに直接的な影響を与える最も変動しやすい要因です。
充填速度と圧力

溶融した樹脂を金型内に送り込む際の充填速度や圧力は、ソリの発生に大きく関わります。充填速度が速すぎると、溶融樹脂内の高分子鎖やガラス繊維が流れの方向に強く配向し、それが冷却後に異方性収縮を引き起こす原因となります。また、射出圧力が不十分だと、金型内の樹脂が十分に充填・加圧される前に固化が始まり、収縮を補うことができずにソリやヒケにつながります。逆に、保圧が高すぎると金型内で過剰な応力が残留し、離型後にその応力が解放されることで変形を引き起こす可能性があります。
冷却時間と冷却不均一
冷却工程の管理は、ソリ対策の核心とも言える部分です。金型内で成形品が十分に冷却されずに取り出されると、内部に多くの熱エネルギーが残ったままの状態になります。この残存熱が、離型後の環境下で不均一に放熱されることで、部位ごとの収縮差を生み出し、ソリの原因となります。特に、金型の固定側(キャビティ)と可動側(コア)の温度に差があると、成形品の表裏で冷却速度が異なり、その収縮差が製品を曲げる力として作用します。この「片面冷却」は、ソリを発生させる典型的な原因の一つです。
樹脂温度・金型温度
樹脂温度や金型温度の設定も重要です。樹脂温度が高すぎると流動性は向上しますが、分子の配向を助長したり、冷却に必要な時間が増加したりします。逆に、温度が低すぎると樹脂の流動性が低下し、金型内を均一に充填できなくなる可能性があります。金型温度は、特に結晶性樹脂の挙動に大きく影響します。金型温度が高いと、結晶化がゆっくりと進行し、より大きく収縮するためソリの原因となり得ます。逆に低すぎると、製品表面だけが急激に固化し、内部との収縮差から応力が発生します。
金型設計に起因するソリ
ソリの原因が、そもそも金型の構造に起因しているケースも少なくありません。
ゲート位置・サイズ不良
ゲートは、溶融樹脂が製品キャビティに入る入り口であり、その位置やサイズ、数は製品の品質を大きく左右します。ゲート位置が不適切だと、樹脂の流れが不均一になり、充填末端での圧力不足や、キャビティ内の圧力分布のばらつきを引き起こします。この圧力の不均一さが、そのまま収縮の不均一さにつながり、ソリを発生させます。ゲートサイズが小さすぎても、樹脂の通過抵抗が大きくなり、十分な保圧が伝わらない原因となります。
冷却配管の不均一
成形条件における冷却不均一の問題は、金型内の冷却回路の設計と密接に関連しています。製品の肉厚部やリブの周辺など、熱が集中しやすい箇所に適切な冷却回路が配置されていないと、局所的な冷却遅れが生じます。この冷却のムラが、部位ごとの収縮差を生み出し、ソリの直接的な原因となります。特に板状の製品では、キャビティ側とコア側の冷却能力を均一に設計することが、ソリを抑制する上で極めて重要です。
離型設計不良
成形品を金型から突き出す際の設計も、ソリに影響を及ぼします。突き出しピンの位置や数が不適切だと、まだ高温で強度が低い状態の成形品に無理な力がかかります。この突き出し時の不均一な力が、製品に変形や応力を与え、それがソリとして残ってしまうことがあります。特に薄肉品や、複雑な形状を持つ製品では、突き出しのバランスを十分に考慮した金型設計が求められます。
材料特性に起因するソリ
使用する樹脂材料そのものの特性が、ソリの発生しやすさを決定づけることもあります。
結晶性樹脂の挙動(PA, PBT, POM, PPS など)
PA(ポリアミド)やPBT(ポリブチレンテレフタレート)、POM(ポリアセタール)に代表される結晶性樹脂は、非晶性樹脂(PC, PSなど)と比較して、溶融状態から固体へ変化する際の体積収縮が著しく大きいという特徴があります。これは、冷却過程で分子が規則正しく並び、「結晶化」という構造変化を起こすためです。この大きな成形収縮率は、わずかな冷却の不均一さや肉厚の差によって大きな収縮量の差となり、結果として強いソリを引き起こす傾向があります。
ガラス繊維入り樹脂

強度や剛性を高める目的でガラス繊維(GF)などを添加した強化プラスチックは、ソリの問題が顕著に現れやすい材料です。溶融樹脂が金型内を流れる際、細長いガラス繊維が流れの方向に沿って並ぶ「配向」という現象が起こります。繊維自体はほとんど収縮しないため、樹脂が冷却・固化する際にその収縮を拘束します。これにより、繊維が配向した方向(流れ方向)と、それに直交する方向とで収縮率に大きな差(異方性収縮)が生じます。この異方性収縮が、製品に複雑な曲がりやねじれを引き起こす主要な原因となります。
高収縮率材料
結晶性樹脂に限らず、全体として成形収縮率が高い材料は、ソリのリスクが高いと言えます。成形条件のわずかな変動や金型内の温度差が、収縮量の大きなばらつきとして現れやすいためです。この収縮差は内部応力を増大させ、最終的にソリという変形につながります。材料を選定する際には、製品に求められる寸法精度と、材料固有の収縮特性を天秤にかけて検討することが重要です。
ソリ発生のメカニズムまとめ
丸山らの研究では、熱可塑性樹脂における成形収縮とソリ変形との関連を、熱応力ひずみ理論に基づく物理モデルで定量的に解析しています。モデルでは板厚方向の収縮不均一が応力分布を生み、それがソリ変形として表面化することが明瞭に示され、CAE解析結果との整合性も確認されています[2]。これまで述べてきた様々な要因が、どのようにしてソリという現象を引き起こすのか、そのメカニズムを以下に整理します。
内部応力と収縮差の発生:金型内への樹脂の充填・保圧・冷却という一連のプロセスの中で、分子の配向、圧力分布の不均一、冷却速度の差、ガラス繊維の配向などによって、成形品内部には「残留応力」が蓄積され、部位ごとに異なる「収縮率」が内在化します。
拘束からの解放:成形品が金型から突き出される(離型する)ことで、金型による形状の拘束から解放されます。
変形の顕在化:拘束から解放された結果、内部に蓄積されていた残留応力や、部位ごとの収縮差がバランスを取ろうとして一気に表面化します。この力の解放が、製品の「曲がり」や「ねじれ」、すなわち「ソリ」という変形として現れるのです。
つまり、ソリは単一の原因ではなく、成形プロセス全体を通じて蓄積された「歪み」が、最終的に目に見える形となって現れた結果と言えます。
ここまで、ソリ(反り)が発生するメカニズムについて解説してきました。
実際の成形現場では、これらの現象を成形条件・金型設計・材料特性と結びつけて整理することが重要になります。
射出成形におけるソリ(反り)の原因と対策
では、ソリ発生の全体像を整理し、各要因をどのように切り分けて考えるべきかを体系的に解説しています。
まとめ
射出成形におけるソリという不良現象は、見た目の問題に留まらず、製品の寸法精度や機能性を著しく損なう深刻な課題です。その真因を突き詰めると、府中プラは「内部応力の不均一」、「収縮率の差(異方性)」、「冷却バランスの崩壊」という三つの根源的なキーワードに集約されると考えています。
これらの要因は、成形条件、金型設計、材料特性という異なる領域にまたがって複雑に絡み合っています。そのため、問題が発生してから対策を講じる対症療法的なアプローチには限界があります。真に高品質な製品を安定して生産するためには、製品設計、金型設計、材料選定といった開発の初期段階から、ソリの発生メカニズムを念頭に置いた予防的な視点を持つことが不可欠です。この視点こそが、手戻りをなくし、最終的なコスト削減と品質向上を実現するための最も確実な道筋であると考えています。