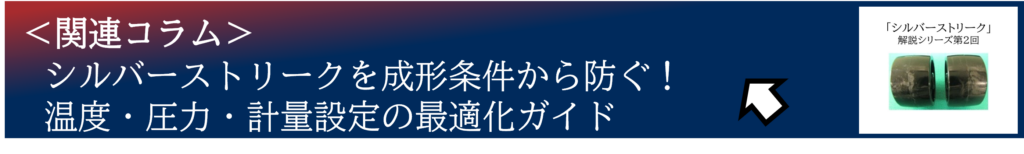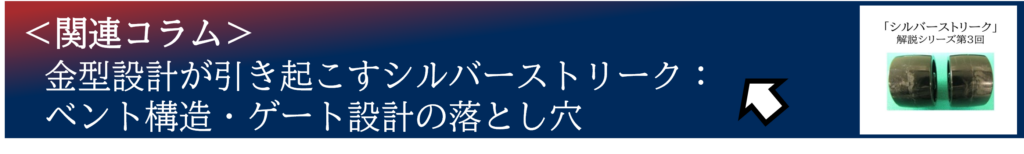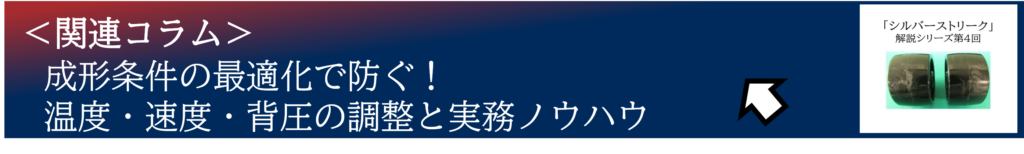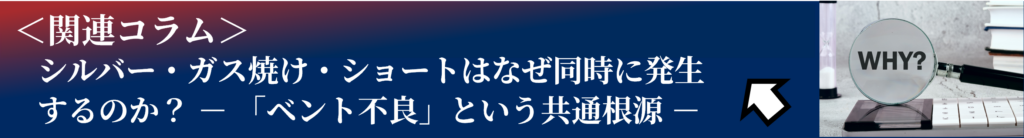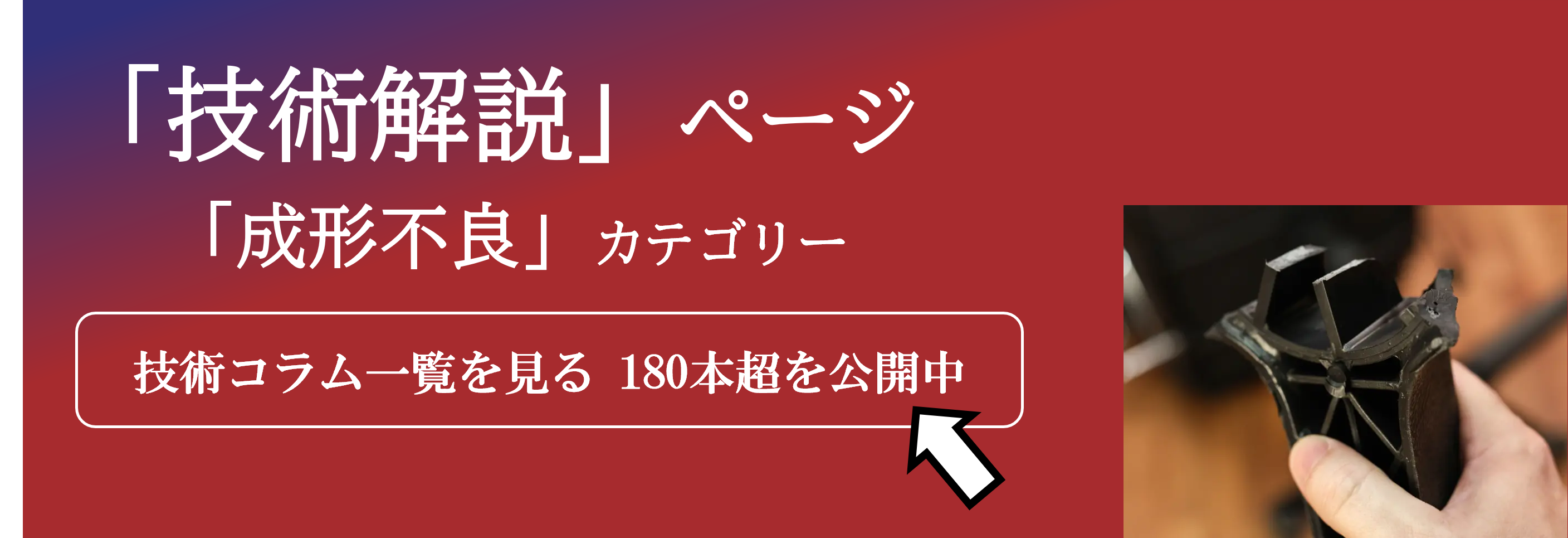シルバーストリークとは?発生メカニズムと3大要因から見る基礎理解

射出成形品の表面に現れる銀色や白色の線状の模様、これを「シルバーストリーク」または「銀条」と呼びます。これは成形不良の中でも特に発生頻度が高く、多くの製造現場で課題となっている現象です。シルバーストリークは、製品の外観品質を著しく損なうだけでなく、その発生原因によっては製品内部の気泡(ボイド)を伴い、機械的強度の低下といった機能面にも悪影響を及ぼす可能性があります。
この不良は、単一の原因で発生するものではなく、材料の管理状態、金型の設計、そして日々の成形条件といった複数の要因が複雑に絡み合って生じます。府中プラは、安定した品質の製品を供給するためには、このシルバーストリークが発生する根本的なメカニズムを正しく理解し、体系的な視点から原因を究明することが不可欠であると考えています。本コラムでは、シルバーストリークの基礎知識として、その発生メカニズムと主要な三つの原因カテゴリについて解説します。
シルバーストリークの発生メカニズム
シルバーストリークの正体は、溶融した樹脂に含まれるガス成分です。成形材料に含まれる水分や揮発成分、あるいは樹脂自体が熱によって分解して生じたガス、さらには成形機や金型内に巻き込まれた空気が、その主な発生源となります。
射出成形のプロセスにおいて、樹脂は加熱シリンダー内で高温に熱せられ、溶融状態になります。この時、樹脂に含まれていた水分や揮発分は気化し、ガスとなります。また、樹脂温度が適正範囲を超えて過度に高くなると、樹脂の分子構造が破壊される「熱分解」が起こり、分解ガスが発生します。
これらのガス成分は、溶融樹脂の中に微細な気泡として混入した状態で、高い圧力と速度で金型キャビティ内へと射出されます。金型キャビティに充填される過程で、樹脂は金型内壁に沿って引き伸ばされながら流動します。この時、樹脂内部の気泡も同じように引き伸ばされ、細長い形状になります。そして、樹脂が冷却・固化する際に、引き伸ばされた気泡の跡が製品表面に線状の模様として転写されます。これが、シルバーストリークとして私たちの目に認識されるのです。
つまり、シルバーストリークは「ガスや水分の気化・混入 → 射出時の引き伸ばし → 表面への転写」という一連の物理現象によって引き起こされる視覚的な欠陥であると言えます。
発生原因と3大カテゴリー
シルバーストリークを引き起こすガスの発生源は多岐にわたります。府中プラでは、その原因を体系的に理解するため、大きく「成形条件」、「金型設計」、「材料特性」の三つのカテゴリに分類して整理しています。
成形条件による原因
日々の生産活動で調整される成形条件は、シルバーストリークの発生に直接的に関わっています。
過熱による熱分解
成形機の加熱シリンダーの設定温度が高すぎると、樹脂が必要以上に加熱され、熱分解を起こしてガスを発生させます。これはシルバーストリークの直接的な原因となります。また、シリンダー内に樹脂が滞留する時間が長すぎることでも、同様に熱分解が促進されるため注意が必要です。
射出速度の過大
溶融樹脂を金型に送り込む射出速度が速すぎると、樹脂がゲートなどの狭い流路を通過する際に大きな剪断抵抗を受け、その摩擦熱(せん断発熱)によって局所的に樹脂温度が急上昇します。この現象が熱分解を引き起こし、ガス発生の原因となることがあります。
保圧不足
充填後の保圧工程で圧力が不足していると、金型キャビティ内に発生・残留したガスを十分に圧縮しきれず、製品表面にシルバーストリークとして現れやすくなります。
計量時の背圧不足と過剰なサックバック

計量工程(次の射出のためにスクリューを後退させながら樹脂を溶融・混練する工程)でかける背圧が低すぎると、ホッパーから供給されるペレットと共に空気を巻き込みやすくなります。また、計量後にノズルからの樹脂漏れを防ぐために行うサックバック(スクリューを少し後退させる動作)の量が過剰であると、ノズル先端から空気を吸い込んでしまい、これが次ショットのシルバーストリークの原因となります。
金型設計による原因
金型そのものの構造が、シルバーストリークを発生しやすくしているケースも少なくありません。
不適切なゲート設計
樹脂の入り口であるゲートの断面積が小さすぎると、樹脂が通過する際の剪断発熱が大きくなり、熱分解を誘発します。ゲート径や形状は、使用する樹脂の特性や製品形状を考慮して適切に設計される必要があります。
冷却の不均一
金型内の冷却回路の設計が不適切で、局所的に温度が高い部分が存在すると、その部分で樹脂の熱分解が促進される可能性があります。金型温度を均一に保つことは、シルバーストリーク防止の観点からも重要です。
排気構造の不足

射出の際、もともと金型キャビティ内に存在した空気は、充填される樹脂によって押し出され、外部へ排出される必要があります。この空気の逃げ道となるエアベント(ガスベント)の設計が不十分であったり、メンテナンス不足で詰まっていたりすると、空気が樹脂内に閉じ込められ、シルバーストリークやショートショット、ウェルドラインの強度低下などを引き起こします。
材料特性による原因
使用する樹脂材料の種類や、その管理状態も極めて重要な要因です。
乾燥不足
これはシルバーストリークの最も一般的かつ主要な原因です。特にPC(ポリカーボネート)、PA(ポリアミド)、ABS樹脂、PET樹脂といった材料は吸湿性が高く、空気中の水分を吸収しやすい性質を持っています。これらの材料を成形前に十分に乾燥させないと、ペレットに含まれる水分が加熱シリンダー内で水蒸気となり、大量のシルバーストリークを発生させます。
吸湿性の高い材料の使用
材料自体の吸湿性が高い場合、推奨される乾燥条件を遵守することはもちろん、乾燥後の保管方法や成形機ホッパー上での滞留時間にも注意を払う必要があります。開封後の材料を長時間放置することも避けるべきです。
再生材の熱履歴

コスト削減のために使用される再生材(リサイクル材)は、少なくとも一度は成形プロセスによる熱履歴を受けています。この熱履歴によって材料の劣化が進行している場合があり、バージン材に比べて低い温度でも熱分解を起こしやすくなる傾向があります。再生材の使用率が高いと、シルバーストリークの発生リスクも増大します。
対策アプローチの全体像
シルバーストリークの発生原因が多岐にわたることから、その対策も多角的な視点からアプローチする必要があります。府中プラでは、前述の3大カテゴリに対応する形で、対策の全体像を捉えています。
成形条件の最適化
まず取り組むべきは、成形条件の見直しです。具体的には、樹脂の熱分解を防ぐためのバレル温度の適正化、剪断発熱を抑制するための射出速度や射出圧力の調整、ガスを圧縮するための保圧時間と圧力の最適化、そして空気の巻き込みを防ぐための計量条件の調整などが挙げられます。
金型設計の改善
成形条件の最適化だけでは解決が困難な場合は、金型の構造に起因する問題が考えられます。せん断発熱を低減するためのゲート設計の見直し、均一な温度分布を実現するための冷却ラインの最適化、そしてキャビティ内のガスを効率的に排出するためのエアベント構造の追加や改善などが、根本的な対策として有効です。
材料管理の徹底
最も基本的な対策として、材料管理の徹底が挙げられます。特に吸湿性樹脂に対しては、メーカーが推奨する条件での予備乾燥を確実に行うことが不可欠です。また、材料の保管環境を適切に維持し、吸湿を防ぐこと、そして再生材を使用する場合にはその使用率や品質を厳格に管理することも、シルバーストリークの発生を未然に防ぐ上で極めて重要です。
シルバーストリークは単一の原因で発生する不良ではなく、成形条件、金型設計、材料特性が相互に影響し合って顕在化します。
射出成形におけるシルバーストリークの原因と対策
では、発生要因を全体像として整理し、どこから対策を検討すべきかを体系的に解説しています。
まとめ
シルバーストリークは、成形品の表面に現れる線状の模様であり、外観品質や製品強度に影響を及ぼす代表的な成形不良です。その根本原因は、樹脂に混入したガス成分であり、その発生源は「成形条件」、「金型設計」、「材料特性」という三つの領域にまたがっています。
この不良を効果的に解決するためには、目先の現象だけにとらわれるのではなく、なぜガスが発生し、それがどのようにして製品表面に現れるのかというメカニズムを理解することが第一歩となります。そして、原因が潜む可能性のある全ての要因を視野に入れ、設計、金型、材料、成形という各分野が連携して対策を講じる総合的なアプローチが求められます。府中プラは、長年の経験で培った知見と技術に基づき、こうした品質問題の根本原因を究明し、お客様と共に最適な解決策を導き出す支援体制を整えています。