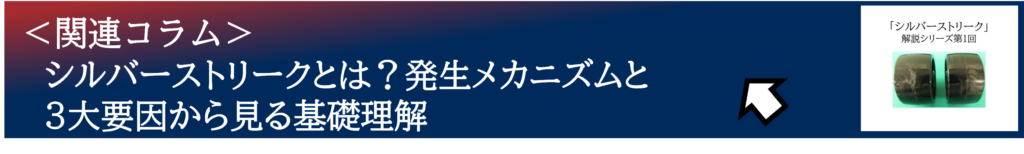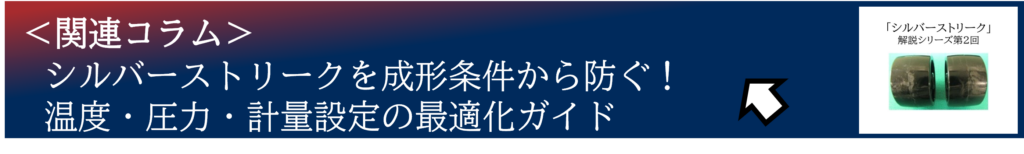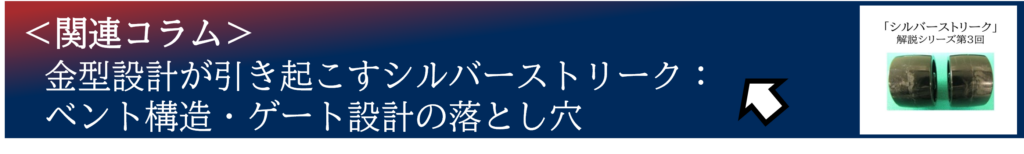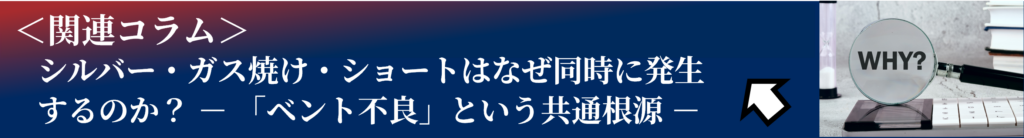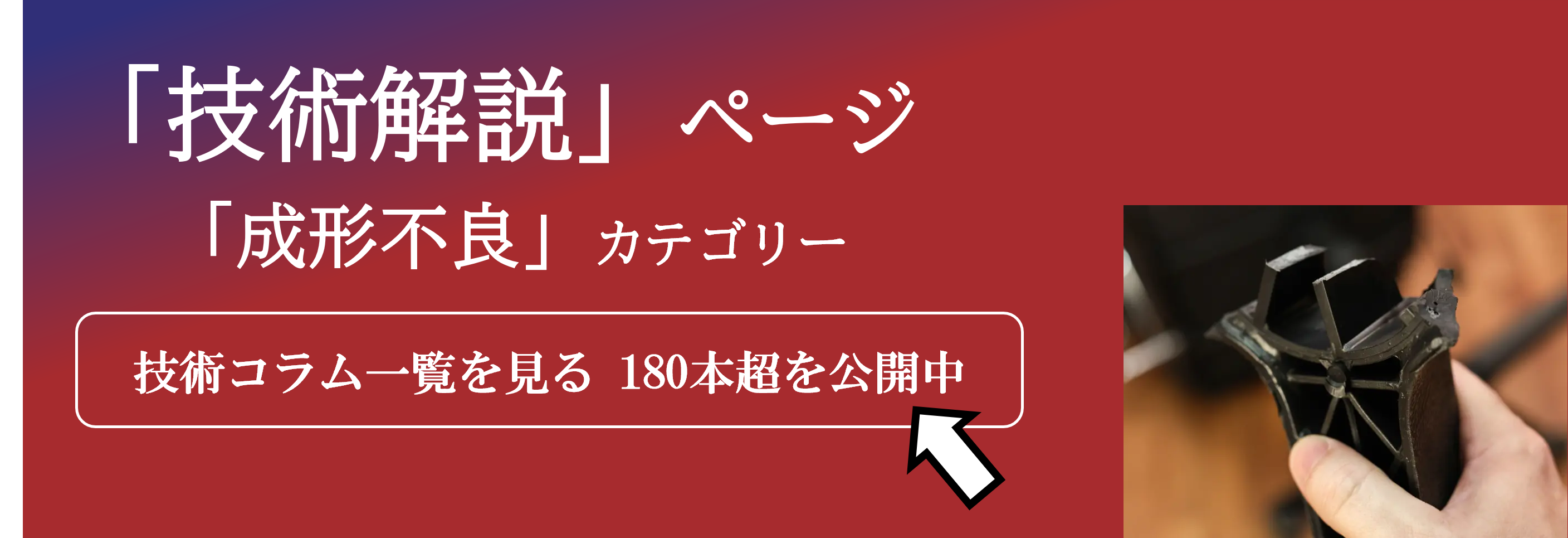シルバーストリークを成形条件の最適化で防ぐ!温度・速度・背圧の調整と実務ノウハウ

4回にわたりお送りしてきたシルバーストリーク解説コラム、その最終回となる本コラムでは、製造現場で日々行われる「成形条件の調整」による対策に焦点を当てます。成形条件の調整は、しばしば経験と勘に頼ったトライ&エラーの繰り返しになりがちです。しかし、安定した品質を継続的に実現するためには、なぜその調整が有効なのかという理論的背景を理解し、再現性のある手順に基づいて最適化を進めることが極めて重要となります。
府中プラは、シルバーストリーク対策の鍵が「揮発性成分の挙動」、「気泡の巻き込み」、「フローフロントの不安定化」という三つの物理現象をいかにコントロールするかにあると考えています。本コラムでは、これらの現象を抑制するための具体的な条件設定と、実務的な調整ノウハウについて解説します。
シリンダー温度とバレルゾーン設定の考え方
樹脂を溶融させるシリンダー温度は、シルバーストリークに直結する最も基本的な成形条件です。設定温度が高すぎても低すぎても、それぞれ異なるメカニズムで不良を引き起こします。
温度が高すぎる場合のリスク
シリンダーの設定温度が樹脂の適正範囲を超えて高すぎると、樹脂の熱分解が促進され、分解ガスが大量に発生します。これがシルバーストリークの直接的な原因となるのは、第2回のコラムでも解説した通りです。特に、PA(ポリアミド)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PC(ポリカーボネート)といった材料は、熱安定性に比較的敏感であり、わずかな過熱でもガス発生のリスクが高まります。成形を中断した後の再開時など、シリンダー内に樹脂が滞留した状態では、設定温度が適正範囲内であっても熱履歴の蓄積により分解が進むため、特に注意が必要です。実際に、熱安定性の低い樹脂ではわずかな温度超過でも揮発性ガスの発生量が急増し、銀条の発生率が著しく高まることが報告されています。
温度が低すぎる場合のリスク
逆に、温度が低すぎると、樹脂が十分に溶融せず、粘度が高いまま射出されることになります。この溶融不良の状態では、樹脂の流れが不安定になり、スクリューから供給される際に空気を巻き込みやすくなります。また、粘度が高いために樹脂内の気泡が抜けにくく、そのまま製品内部に残留し、シルバーストリークの原因となります。さらに、流動性の悪化はフローフロントの不均一化を招き、部分的なショートショットや、ウェルドライン部でのガス閉じ込めといった複合的な不良を引き起こす可能性もあります。
射出速度・圧力の設定とフロー挙動
溶融樹脂を金型へ充填する際の速度と圧力は、フローフロントの挙動を直接コントロールし、空気の巻き込みを左右する重要な要素です。
高速射出がもたらす乱流と空気巻き込み
生産効率を上げるために射出速度を高く設定すると、溶融樹脂のフローフロントがジェット流のように不安定になり、乱流を発生させやすくなります。この乱流が、金型キャビティ内の空気を周囲から巻き込み、シルバーストリークとして製品表面に現れることがあります。金型に適切なエアベント(ガス逃げ)が設計されていれば、ある程度のガスは排出されますが、ベントの能力を超える速度で充填すると、ガスが逃げ切れずに閉じ込められてしまいます。射出速度が高すぎる場合の乱流形成とガス閉じ込めリスクは多くの実験で確認されており、特に流動長が長い製品では注意が必要とされています。射出速度の設定は、必ず金型のガス逃げ能力との整合性を考慮する必要があります。
低速射出による冷却・凝固と表面筋
高速射出が問題だからといって、単純に速度を落とせば良いわけではありません。射出速度が遅すぎると、樹脂が金型キャビティの隅々まで充填される前に、金型表面で冷却・固化が始まってしまいます。この半固化した樹脂層の上を後から来る樹脂が乗り越えるように流れるため、その境界が線状の筋(フローライン)となって現れます。このフローラインが、シルバーストリークと酷似した外観を呈することがあり、原因の誤認につながるケースも少なくありません。
最適な射出速度を見極める一つの目安として、府中プラでは「流動長と製品肉厚のバランス」を考慮します。薄肉で流動長が長い製品ほど、固化する前に充填を完了させるため、ある程度の速度が必要になります。
スクリュー背圧とサックバック(スクリュー後退量)
次ショットの射出に備えて樹脂を可塑化・計量する工程の設定も、シルバーストリークの発生に大きく関わっています。
背圧が低すぎるとガス混入しやすい
計量時にスクリューへかける抵抗圧である「背圧」には、樹脂を圧縮して密度を高め、溶融を均一化するとともに、樹脂に含まれる空気や揮発性ガスをスクリュー後方(ホッパー側)へ押し出す「脱気」という重要な役割があります。この背圧が低すぎると、脱気が不十分となり、樹脂内に気泡が残留したままシリンダー先端に送られてしまいます。これが次ショットでのシルバーストリークの大きな原因となります。特に、吸湿しやすい材料や、多くの空気を含みやすい再生材を使用する場合には、安定した溶融と脱気を促すために、適切な背圧をかけることが極めて重要です。背圧と脱気量の関係を定量的に示した成形事例では、背圧不足により気泡混入が2倍以上に増加したとする報告も存在します。
サックバックによる逆流現象の防止
サックバックは、計量完了後にスクリューをわずかに後退させ、ノズルからの樹脂漏れを防ぐための操作ですが、この後退量が過大だと、シリンダーのノズル先端から外気を吸い込んでしまいます。この吸い込まれた空気が、次ショットの樹脂の先頭に混入し、シルバーストリークを発生させます。サックバックは、あくまで鼻タレが防止できる最小限の量に設定することが鉄則であり、材料の粘度やノズルの種類によって最適値は異なるため、慎重な調整が求められます。
成形条件最適化の手順とチェックポイント
理論を理解した上で、現場で条件を最適化していくためには、体系的な手順を踏むことが重要です。府中プラでは、以下のプロセスを推奨しています。
基準の確認
まず、使用する樹脂の材料メーカーが発行する特性データや成形条件の推奨値を確認し、現在の設定がその範囲から大きく逸脱していないかを確認します。これを全ての調整の出発点とします(当たり前のように思われるかもしれませんが、意外とこれができていないケースを、私は材料メーカー在籍時に数多く目にしてきました)。
不良の観察と仮説立案
発生しているシルバーストリークが、製品のどの位置に、どのような形で現れているかを詳細に観察します。「全体的に発生しているなら乾燥不足か熱分解」「特定の位置に集中しているならガスベント不良かフローフロントの乱れ」といったように、観察結果から原因の仮説を立てます。
1条件ずつの調整と結果の確認
仮説に基づいて、影響が大きいと考えられる条件を「一つだけ」変更し、数ショット成形して結果を観察します。複数の条件を一度に変更すると、どの変更が有効だったのかが分からなくなってしまいます。この「仮説→実行→検証→考察」というPDCAサイクルを回すことが、再現性のあるノウハウを蓄積する上で不可欠です。成形条件の最適化においてPDCAサイクルを明確に運用することが、成形不良削減の鍵になるという報告も多く、現場での記録と分析の重要性が強調されています。
条件間の相関関係の理解
成形条件は互いに影響し合っています。例えば、背圧を上げると樹脂の溶融状態は改善しますが、せん断発熱によって樹脂温度が上昇し、結果として射出速度を調整する必要が出てくる、といった相関関係があります。一つの条件を調整する際は、それが他の条件にどう影響するかを常に念頭に置く必要があります。
実際の成形現場では、シルバーストリーク対策を単一視点で判断するのではなく、原因を整理したうえで優先順位を付けて対応することが重要になります。
射出成形におけるシルバーストリークの原因と対策
では、実務で迷いやすい判断ポイントを含め、全体整理の考え方を体系的に解説しています。
まとめ
4回にわたるシリーズを通して解説してきたように、シルバーストリークという一つの成形不良には、多様な原因が潜んでいます。そして、その対策は、成形条件を最適化するだけで大幅に改善できる場合もあれば、金型設計や材料管理といった、より上流の段階にまで遡らなければ根本解決に至らない場合もあります。
重要なのは、成形条件に普遍的な「正解」はなく、その時々の「材料」「金型」「成形品形状」の組み合わせによって最適値は常に変化する、という事実を認識することです。しかし、「なぜこの条件がシルバーストリークに悪影響を与えるのか」という理論的背景を理解していれば、闇雲なトライ&エラーから脱却し、論理的かつ再現性のある対策を講じることが可能になります。
シルバーストリーク対策は、射出成形における品質管理の縮図です。府中プラは、この「材料」、「金型」、「成形条件」の三位一体のバランスを追求し続けることこそが、高品質なものづくりへの道であると考えています。