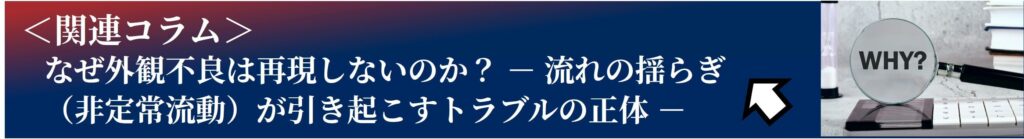なぜフローマークが発生するのか?射出成形における波状模様の原因を徹底解説

射出成形品の表面に現れる波状の模様「フローマーク」。製品の美観を損ない、特に外観部品では致命的な不良となります。この不良はなぜ発生するのでしょうか。本コラムではフローマークの原因に焦点を当て、設計・金型・成形条件・材料の4つの視点から発生原因を解説します。
フローマークの発生メカニズム
フローマークの発生メカニズムを理解するには、まず金型内部での溶融樹脂の動きを捉える必要があります。射出された高温の溶融樹脂は、金型内を流れながら充填されていきます。このとき、樹脂の流れの先端部分(メルトフロント)は、温度の低い金型表面に接触することで冷却され、粘度が上昇し始めます。後から送られてくる比較的温度の高い樹脂が、この冷えて固化し始めた先端部を追い越し、あるいは合流する際に、その流動の痕跡が表面に転写されることで、波状や年輪のような模様として現れます。これがフローマークの基本的な発生原理です。
つまり、フローマークとは、金型キャビティ内における樹脂の流れの乱れや、部分的な温度の不均一性によって引き起こされる、メルトフロントの挙動が可視化された現象と言えます。その発生は、単一の原因ではなく、後述する成形条件、金型構造、材料特性、そして製品設計といった複数の要因が複雑に絡み合って起こるケースがほとんどです。
ここで、他の代表的な外観不良との違いを明確にしておきましょう。例えば「ジェッティング」は、狭いゲートから射出された樹脂が、キャビティ内でジェット噴流のように直進し、蛇行した痕跡を残す現象です。また、「シルバーストリーク」は、材料中の水分や揮発ガスが気化し、成形品表面に銀色の筋となって現れる現象を指します。これらはフローマークとは発生のメカニズムが根本的に異なります。不良現象を正確に識別することが、原因究明の精度を高める鍵となります。
成形条件による原因
成形現場で最初に着手することが多いのが、成形条件の見直しです。フローマークは、樹脂の温度と流動性をコントロールする成形条件の設定に大きく左右されます。
樹脂温度の不足
設定された樹脂温度が低い場合、溶融樹脂の粘度が高いまま射出されることになります。粘度が高い樹脂は流動性が低いため、金型内をスムーズに流れることができず、メルトフロントの挙動が不安定になります。流れの先端部が早期に固化しやすくなるため、後続の樹脂がそれを乗り越える際の痕跡が、より顕著なフローマークとして表面に残ります。
金型温度の不足
金型温度が低い場合、キャビティ内に流入した溶融樹脂は、その表面が金型と接触した瞬間に急激に冷却されます。これにより、金型表面に薄い固化層(スキン層)が早期に形成され、内部を流れる溶融樹脂の流動を阻害します。このスキン層と内部の溶融樹脂との間で流動速度に差が生じ、流れが乱れることでフローマークが発生します。
射出速度の不適切な設定
射出速度はフローマークの発生に直接的な影響を与えます。速度が遅すぎると、樹脂がキャビティの隅々まで充填される前にメルトフロントの温度が低下し、冷えて固化が進んでしまいます。結果として、樹脂同士の融着が不十分となり、波状の模様が生じやすくなります。逆に、射出速度が速すぎる場合も問題です。速すぎる流れは乱流を引き起こし、キャビティ内の空気を巻き込みながら充填が進むことがあります。この巻き込まれた空気が流れを乱し、不規則なパターンを形成する原因となります。
保圧切替位置の不適切な設定
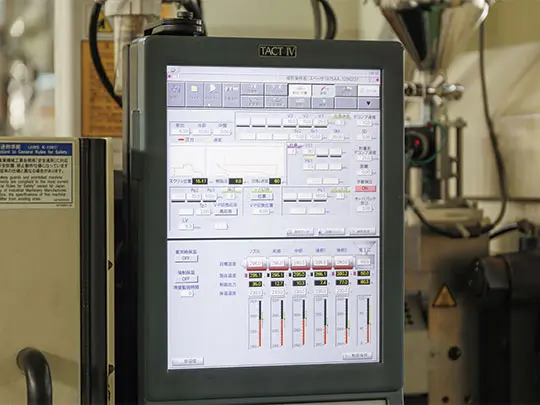
射出工程は、金型内を樹脂で満たす「充填工程」と、圧力をかけて収縮を補う「保圧工程」に分かれます。この二つの工程が切り替わるタイミング(V/P切替位置)の設定が不適切だと、フローマークの原因となることがあります。切替の瞬間に発生する圧力の急激な変動が、完全に固化していない成形品の表面に影響を与え、その痕跡が模様として残ってしまうのです。
金型設計による原因
成形条件を調整しても改善が見られない場合、原因は金型側にある可能性を検討する必要があります。金型設計は、樹脂の流れ方を決定づける重要な要素です。
ゲート位置・形状不適
ゲートは、樹脂がキャビティ内へ入る入口です。このゲートの位置や形状、サイズが製品形状に対して不適切な場合、樹脂は均一に広がることができません。特定の方向に樹脂が集中して流れることで、キャビティ内で部分的な流速差が生まれ、樹脂が合流する箇所などで表面速度の差に起因するフローマークが発生します。
ランナー・ゲートの断面積の不足
ランナーやゲートの断面積が小さすぎると、樹脂は狭い流路を通過する際に大きな抵抗を受けます。これにより圧力損失が大きくなるだけでなく、樹脂は無理に押し込まれる形でキャビティ内に流入するため、乱流状態となりやすくなります。この不安定な流れが、そのままフローマークとして製品表面に現れます。
キャビティ内の温度ムラ
金型には温度を一定に保つための冷却(温調)回路が設けられていますが、この回路の設計や配置に偏りがあると、キャビティの表面温度が不均一になります。特定の箇所だけが冷えやすかったり、温まりにくかったりすると、その場所を通過する樹脂の固化タイミングにズレが生じます。この局所的な冷却速度の違いが、フローマークの発生を助長します。
エアベントの不足
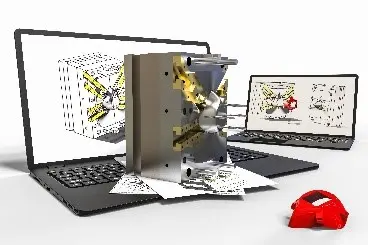
射出成形では、キャビティ内にもともと存在した空気を、流入してくる樹脂で置換しながら充填します。このとき、空気の逃げ道となるエアベントの設計が不十分だと、行き場を失った空気がキャビティの末端部などで圧縮されます。圧縮された空気は断熱圧縮により高温となり、樹脂の流れを阻害したり、場合によっては樹脂を燃焼させたりします。このガスの影響による流れの乱れも、フローマークの一因となり得ます。
材料特性による原因
使用する樹脂材料そのものの特性も、フローマークの発生に深く関わっています。同じ金型、同じ成形条件であっても、材料を変更した途端に不良が発生・解消することは珍しくありません。
粘度の高い樹脂
樹脂材料には、それぞれ固有の溶融粘度があります。ガラス繊維などで強化されたグレードなど、もともと溶融時の粘度が高い材料は流動性が低く、メルトフロントが乱れやすい傾向にあります。わずかな温度低下や速度変化でも流れの状態が変わりやすいため、フローマークが発生しやすい材料であると言えます。
充填挙動に影響する添加剤のばらつき
樹脂材料には、流動性や離型性を向上させるための滑剤や、製品に着色するための顔料など、様々な添加剤が含まれています。例えば、滑剤が不足していると、樹脂が金型表面をスムーズに流れにくくなります。また、顔料やガラス繊維といったフィラーの分散状態が悪いと、樹脂内で局所的な粘度ムラが生じ、これが均一な流れを阻害してフローマークの原因となることがあります。
リサイクル材・異材混入
コスト削減などを目的にリサイクル材を使用する場合、注意が必要です。リサイクル材は、繰り返しの熱履歴によってバージン材よりも物性が変化し、溶融粘度がばらつく傾向があります。また、物性の異なる異材が微量でも混入すると、溶融挙動が不安定になり、均一な流れが妨げられることで、予期せぬフローマークを引き起こす原因となります。
設計による原因
最後に、製品そのものの設計、つまり形状が原因となるケースです。成形性を見越した設計がなされていない場合、いくら成形条件や金型を工夫してもフローマークを防ぎきれないことがあります。
肉厚の急激な変化
製品形状において、薄い部分から厚い部分へ、あるいはその逆の肉厚変化が急激な箇所があると、樹脂の流れが大きく影響を受けます。断面積が急に変わることで樹脂の流速が変化し、流れの乱れが生じます。特に、段差部や厚肉部との境界付近では、この流速差が原因でフローマークが残りやすくなります。
長距離の流動設計
ゲートから非常に遠い位置まで樹脂を流さなければならない製品設計では、フローマークのリスクが高まります。樹脂は長い距離を流れる間に熱を失い、徐々に温度が低下して粘度が上昇していきます。そのため、充填の末端部分では流動性が著しく低下しており、わずかな影響でもフローマークとして現れやすくなります。
リブ・ボス等による急激な断面の変化
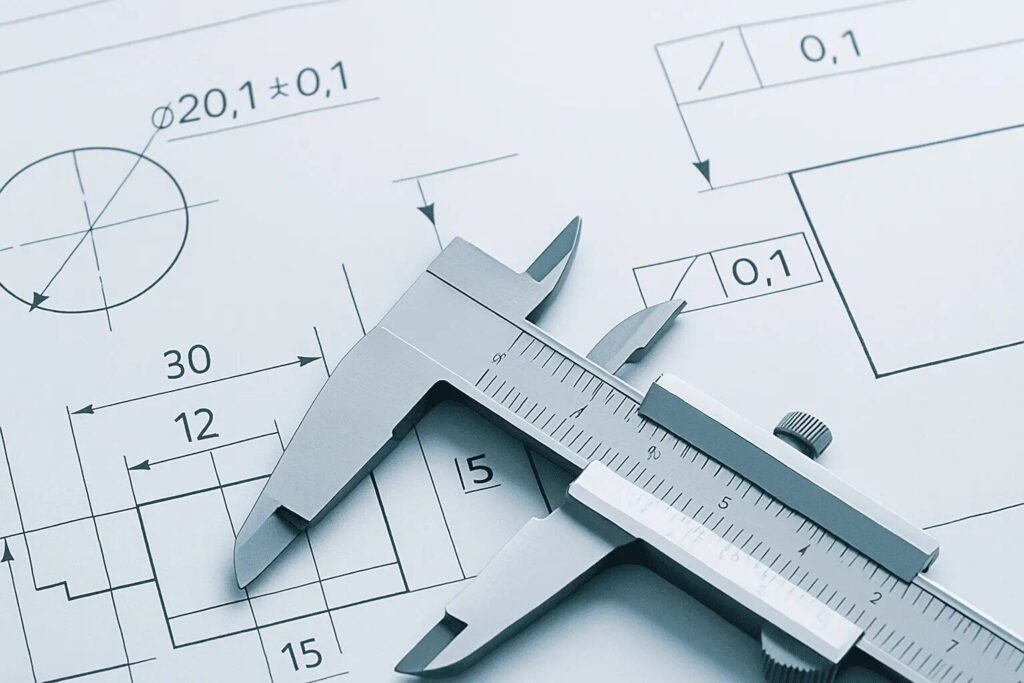
補強のためのリブや、締結のためのボスといった構造は、平坦な面の流れを阻害する要因となります。これらの突起物の周囲では、樹脂の流れが一度分断され、再び合流するという複雑な挙動を示します。この流れの分離や再合流の際に表面の乱れが生じ、フローマークの発生起点となることが多くあります。
フローマークは特定の条件だけで発生する不良ではなく、流動状態、温度分布、金型表面状態などが複合的に影響して現れます。
射出成形におけるフローマークの原因と対策
では、発生要因を全体像として整理し、どの観点から対策を検討すべきかを体系的に解説しています。
まとめ
フローマークは、成形条件・金型・材料・設計といった複数の要因が複雑に絡み合って発生します。原因の特定には多角的な分析が不可欠です。現場では「発生位置」、「外観パターン」、「再現テスト」の3点から分析し、仮説検証を進めるのが有効なアプローチです。
府中プラは、こうした複合要因を紐解き解決策を導きます。次回のコラムでは「対策編」として、原因別の具体的な改善方法を解説します。