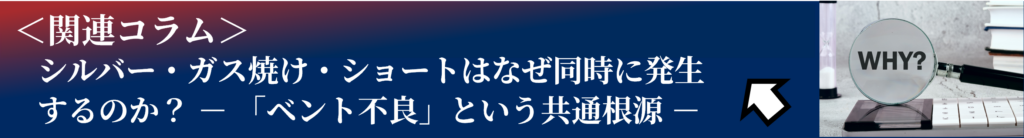なぜガス焼けが発生するのか?射出成形におけるガス焼けの原因を徹底解説

射出成形品の表面に現れる茶褐色から黒色の変色や焦げ跡、これが「ガス焼け(ヤケ)」と呼ばれる不良現象です。ガス焼けは、製品の外観品質を著しく損なうだけでなく、その部分の材質が劣化することで強度や耐久性にも悪影響を及ぼす可能性があります。この厄介な不良を解消するためには、まず「なぜガス焼けが発生するのか」その原因を正しく特定することが、効果的な対策を立案するための第一歩となります。本コラムでは、ガス焼けが発生する根本的なメカニズムと、その多様な原因について体系的に解説していきます。
ガス焼けの発生メカニズム
ガス焼けの発生メカニズムを理解する鍵は、「断熱圧縮」という物理現象にあります。金型が閉じられた状態でも、キャビティ(製品の形となる空間)の中は空気に満たされています。ここに高温の溶融樹脂が高速で射出・充填されると、もともと存在していた空気や、樹脂自体から発生する揮発成分(ガス)は行き場を失い、キャビティの隅(充填の末端部)へと追い詰められ、圧縮されます。
自転車の空気入れを素早く何度も押すとポンプが熱くなるように、気体は急激に圧縮されると温度が急上昇します。これが断熱圧縮です。金型内で圧縮されたガスは、瞬間的に数百度という高温に達することがあります。この超高温のガスによって、接触した樹脂が燃焼・炭化し、製品表面に焦げ跡として現れるのです。また、樹脂が狭いゲートやランナーを高速で通過する際の摩擦熱(せん断発熱)によって樹脂自体が分解し、発生した分解ガスがこの高温化をさらに助長することもあります。
金型設計・加工による原因
ガス焼けの直接的な原因が「ガスの閉じ込め」である以上、ガスの排出経路となる金型側の設計や加工状態は、最も根本的な原因となり得ます。
ベント(排気溝)の不足や位置不良

金型内のガスを外部へ逃がすための微小な溝が「ガスベント」です。このベントの数が足りない、あるいはガスの溜まりやすい充填末端に配置されていない場合、ガスは逃げ場を失い、閉じ込められてしまいます。ベントの深さが浅すぎたり、汚れで詰まっていたりして機能不全に陥っているケースも同様です。
空気溜まりを誘発する設計
ゲートの位置やランナーの配置が不適切で、樹脂が回り込むように合流する箇所(ウェルドライン部)や、リブ・ボスの行き止まり部分などは、構造的に空気を巻き込みやすく、ガス溜まりの発生ポイントとなります。
コアピンやインサート周りのガス滞留
複雑な形状を構成するコアピンや、金属部品をインサート成形する際、これらの部品とキャビティの嵌合部がガスの逃げ道を塞ぎ、滞留ポイントを作ってしまうことがあります。
金型精度の過剰な密閉性
金型の合わせ面(パーティングライン)も重要な排気経路の一つです。しかし、金型の加工精度が高すぎ、合わせ面が完全に密閉されていると、ガスが抜ける隙間がなくなり、かえってガス焼けを引き起こすことがあります。
成形条件による原因
成形条件の設定は、ガスの発生量や圧縮の度合いを直接左右するため、ガス焼けの主要な原因となります。
過剰な射出速度
射出速度が速すぎると、キャビティ内の空気がベントから排出される時間的猶予がなく、樹脂の流れに巻き込まれやすくなります。特に、充填の終盤で速度が速いままだと、ガスを急激に圧縮してしまい、断熱圧縮による高温化を招きます。
保圧切替位置の不適切な設定
充填から保圧への切り替えが遅すぎると、過剰な樹脂が金型内に押し込まれ(オーバーパック)、ガスを余計に圧縮してしまいます。逆に切り替えが早すぎても、その後の保圧による急な圧力上昇がガスの圧縮につながることがあります。
過剰な樹脂温度・金型温度
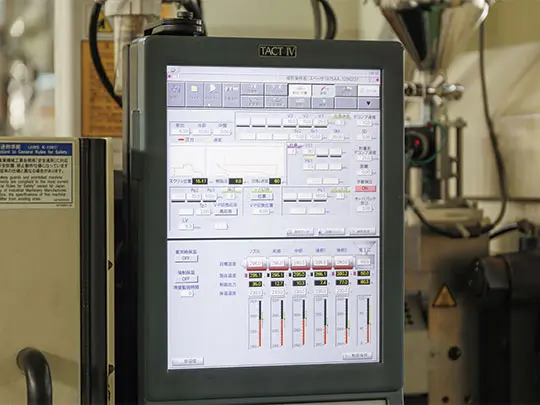
樹脂は必要以上に高い温度に晒されると、熱分解を起こしてガスを発生させやすくなります。特に、成形機シリンダー内での滞留時間が長い場合は注意が必要です。また、金型温度が高すぎると、樹脂の分解を促進してしまう可能性があります。
過剰な射出圧力
高い射出圧力は、ガスをより強く圧縮し、断熱圧縮による温度上昇を増大させます。流動性を補うために安易に圧力を上げることが、ガス焼けのリスクを高める結果につながります。
材料・管理による原因
使用する樹脂材料の種類や、その管理状態もガス焼けの発生に大きく影響します。
乾燥不足による水分・揮発成分
材料の予備乾燥が不十分だと、樹脂に含まれる水分が高温で水蒸気となり、ガスの発生量を増加させます。これがシルバーストリークだけでなく、ガス焼けの原因にもなります。また、材料自体に含まれる低分子量の揮発成分もガスの発生源です。
再生材・長期保管材の使用
再生材は繰り返しの熱履歴により、バージン材よりも熱的に不安定で分解しやすい傾向があります。長期保管された材料も、酸化劣化などにより分解ガスが発生しやすくなっている場合があります。
添加剤の影響
樹脂には難燃性や着色、摺動性などを付与するために様々な添加剤が配合されています。これらの添加剤の中には、熱に弱い成分が含まれている場合があり、それが分解してガスの発生源となることがあります。
吸湿性樹脂の加水分解
PA(ポリアミド)やPET、PBTといった吸湿性の高い樹脂は、水分を含んだまま高温で溶融されると「加水分解」という化学反応を起こします。これにより樹脂の分子構造が破壊され、ガスが発生しやすくなるだけでなく、製品の物性も著しく低下します。
設備・周辺環境による原因
成形機本体や周辺設備の状態が、間接的にガス焼けの原因となることもあります。
射出機スクリュー・シリンダーの摩耗

スクリューやシリンダーが摩耗していると、樹脂を均一に溶融できず、部分的な過熱(せん断発熱)を引き起こしやすくなります。この過熱が樹脂の分解を促進し、ガス発生につながります。
ノズル・ランナー内のデッドスペース
射出機のノズル先端や金型のホットランナー内に、樹脂が滞留しやすい「デッドスペース」が存在すると、その部分の樹脂だけが長時間熱に晒されて劣化・分解し、ガス発生の原因となります。
環境の湿度変化
工場内の湿度が高い日に、乾燥後の材料が再び吸湿してしまい、結果としてガス焼けにつながるケースもあります。乾燥機から成形機ホッパーへの輸送過程での吸湿管理も重要です。
ガス焼けは断熱圧縮という物理現象を起点にしつつも、金型構造、成形条件、材料管理など複数の要因が重なって発生します。
射出成形におけるヤケ(焼け)の原因と対策
では、発生要因を全体像として整理し、どこから対策に着手すべきかを体系的に解説しています。
まとめ
ガス焼けは、これまで見てきたように、単一の原因で発生するとは限りません。多くの場合、「ベントが不十分な金型」で、「乾燥不足の材料」を、「速すぎる射出速度」で成形する、といった具合に、金型・成形条件・材料・設備の要因が複合的に絡み合って発生します。
そのため、原因を特定するには、まずこれらの4つの視点から要因を整理し、どこに最も大きな問題があるのかを切り分けていくアプローチが有効です。府中プラでは、こうした体系的な分析に基づき、最適な解決策を導き出します。次回の「対策編」では、今回解説した原因ごとに、具体的な改善策を詳しく提示していきます。