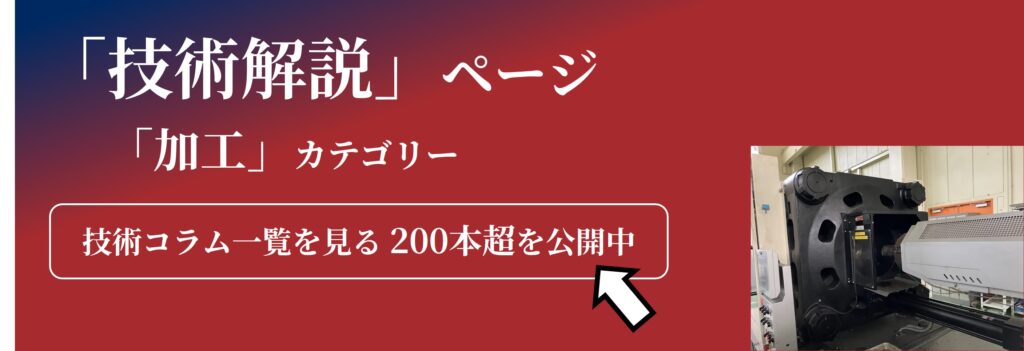型締力と投影面積の関係:バリ・ヒケを防ぐ正しい計算方法
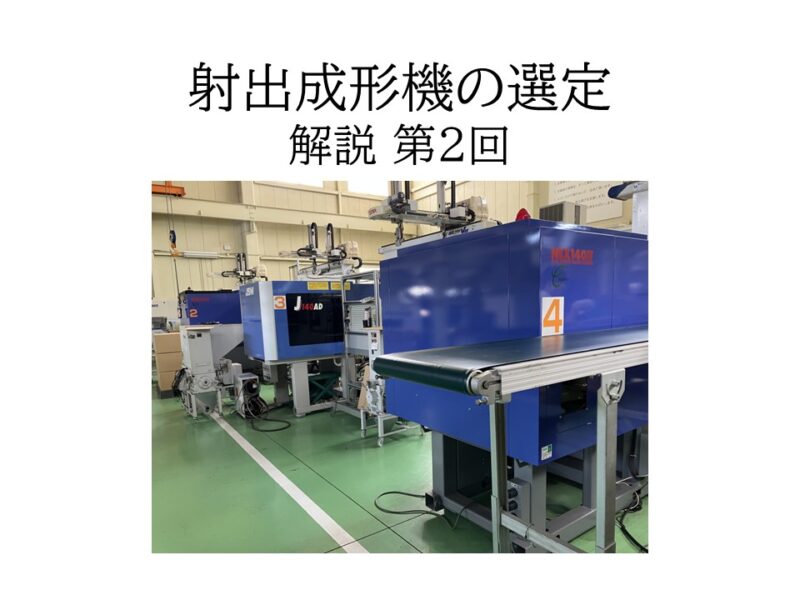
「射出成形機の選定」シリーズコラム第2回
射出成形において、適切な品質の製品を安定して生産するためには、成形機選定の最も基本かつ重要な指標の一つである「型締力」を正しく理解し、適用することが不可欠です。型締力が不足すると、金型から樹脂が漏れ出す「バリ」が発生し、製品不良に直結します。一方で、型締力が過剰であれば、金型に不要な負荷がかかり寿命が短縮されるだけでなく、無駄なエネルギーを消費することにもつながります。
この適正な型締力を求める上で、「投影面積」の概念を正確に把握することは欠かせません。本コラムでは、型締力と投影面積の基礎知識から、バリやヒケといった成形不良を防ぐための正しい計算方法、さらには実務におけるポイントまでを詳しく解説します。
型締力とは何か
型締力とは、射出成形プロセスにおいて、溶融樹脂が金型内部へ高圧で射出される際に、その圧力によって金型が押し開こうとする力に抵抗し、金型をしっかりと閉じた状態に保持するために必要な力を指します。これは射出成形機の基本的な能力を示すスペックの一つであり、「110t(トン)機」や「360t機」といった表現でその能力が示されます。
この型締力の必要値は、成形品の大きさや形状、使用する樹脂の種類、金型内部での樹脂の充填圧力といった多くの要因によって変動します。したがって、最適な成形条件を設定し、高品質な製品を生産するためには、使用する金型と成形材料に対して適切な型締力を設定することが極めて重要となります。
投影面積の基本
投影面積とは、射出成形において、溶融樹脂が金型内に射出される方向から見た、成形品(製品)とそれに付随するランナー(溶融樹脂をキャビティへ導く通路)を合わせた断面積のことを指します。この投影面積は、金型内部で樹脂が型開きの方向に作用する力を算出するための基準となります。
例えば、単純な平板形状の成形品であれば、その投影面積は縦と横の寸法を乗じることで比較的容易に算出できます。しかし、複雑な形状を持つ成形品の場合は、その形状を複数の単純な図形に分割してそれぞれの面積を算出し、それらを合計することで投影面積を求めます。
この投影面積が大きいほど、射出圧力が作用する面積が広くなるため、金型が開こうとする力、すなわち型内にかかる力も増加します。そのため、金型設計の初期段階でこの投影面積を正確に把握し、必要な型締力を適切に見積もることが、成形不良の未然防止に繋がる重要なステップとなります。
型締力の計算方法
適正な型締力を算出するための基本式は以下の通りです。
必要型締力(t)= 投影面積(cm²) × 型内圧( kg/cm ²) / 1,000
この式において、各要素の定義と考慮すべき事項は以下の通りです。
投影面積(cm²):前述の通り、成形品とランナーを含む、射出方向から見た断面積です。
型内圧( kg/cm ²):金型内部のキャビティにかかる樹脂圧力を指します。この圧力は、使用する樹脂材料の種類、成形品の肉厚、ゲート位置、射出速度、金型温度など、様々な成形条件によって変動します。一般的に、目安としては200~400 kg/cm ²の範囲で設定されることが多いですが、特に流動性の低い樹脂や複雑な形状の成形品では高めに設定される傾向があります。
安全率:実務においては、上記の基本計算で得られた値にさらに安全率を乗じて必要型締力を算出するのが一般的です。これは、成形条件の変動や金型のわずかな摩耗などを考慮し、予期せぬバリの発生を防ぐためのものです。安全率は通常1.1倍から1.3倍程度が目安とされますが、成形品の品質要求や生産安定性に応じて適宜調整します。
計算例:
投影面積が100 cm²、型内圧の目安を300 kg/cm ²とし、安全率を1.2倍とした場合。
必要型締力 = 100 cm² × 300 kg/cm ² / 1,000 × 1.2 = 36 t
この場合、少なくとも36トン以上の型締力を持つ成形機を選定することが適切であると判断します。
型締力不足で起きる不良
型締力が不足している状態で射出成形を行うと、樹脂が金型内部に充填される際の圧力によって金型がわずかに押し開かれ、以下のような成形不良が発生します。
バリ(フラッシュ):最も典型的な不良であり、金型のパーティングライン(合わせ面)から溶融樹脂が漏れ出し、成形品の縁に薄い膜状の突起が形成されます。バリは製品の外観品質を損なうだけでなく、後の工程での除去作業が必要となり、コスト増にもつながります。
寸法不良:型締力不足により金型がわずかに開くことで、成形品の肉厚が設計値よりも厚くなったり、金型のかみ合わせがズレて寸法精度が出なかったりする場合があります。特に高精度が求められる部品では致命的な問題となります。
成形品強度の低下:樹脂が金型内で適切に流動せず、バリとして漏れ出すことで、成形品内部の樹脂の流れが乱れることがあります。これにより、製品内部に応力集中が発生しやすくなり、結果として成形品の機械的強度が設計値を下回るケースも存在します。
型締力過剰で起きる問題
型締力が過剰である場合も、以下のような問題を引き起こす可能性があります。
金型寿命の低下:必要以上に高い型締力を金型にかけることは、金型に過大な負荷を与え、金型の早期摩耗や疲労破壊を促進する原因となります。特に、高硬度の金型材料であっても、繰り返し過剰な力が加わることで微細なクラックや変形が生じやすくなります。
成形機への負担増とエネルギーロス:過剰な型締力は、成形機自身の型締機構にも不必要な負荷をかけます。これにより、成形機の駆動部品の摩耗が早まり、メンテナンス頻度の増加や故障のリスクが高まります。また、必要以上の型締力を発生させるためには、より多くのエネルギーが必要となるため、無駄な電力消費に繋がります。
ヒケや残留応力増大:過剰な型締力は、金型内部での樹脂の流動を過度に制約することがあります。これにより、樹脂の充填末端部分での保圧が十分に行われず、成形品の表面に窪みが生じる「ヒケ」が発生しやすくなります。また、樹脂内部に過剰な残留応力が蓄積され、製品の反りや寸法変化、クラックの原因となることもあります。
実務でのポイント
実務において型締力を適切に設定するためには、以下の点に注意を払うことが重要です。
材料ごとの型内圧の違いを把握する:非晶性樹脂(例:PC、ABS、PSなど)は一般的に型内圧が高めに設定される傾向がありますが、結晶性樹脂(例:PPS、PA、POMなど)は流動性が良いため、比較的低い型内圧で成形できることがあります。使用する樹脂材料の特性を理解し、適切な型内圧の目安を設定することが重要です。
多数個取り金型での判断:複数の成形品を同時に生産する多数個取り金型の場合、必要型締力は個々の成形品の投影面積の合計に、ランナー部分の投影面積を加えた総投影面積を基に算出する必要があります。
実際の成形における確認:理論計算値はあくまで目安であり、実際の成形では金型の状態、成形機の特性、材料ロットのばらつきなど、多くの要因が影響します。そのため、成形開始後は「型締力モニタリング」機能などを活用し、成形機に表示される実際の型締力を確認しながら、バリの発生状況や製品品質に基づいて適正値を調整していくことが重要です。これにより、計算値と実測値の差異を埋め、最適な型締力設定を目指します。
まとめ
型締力は、射出成形における製品品質を左右する極めて重要な指標であり、その適正値は「投影面積」から算出されることが基本です。型締力が不足すれば、製品の品質を著しく損なう「バリ」が発生し、過剰であれば金型の寿命を縮めたり、不要なエネルギーを消費したりと、いずれの場合も生産効率やコストに悪影響を及ぼします。
投影面積と型締力の関係を正しく理解し、適切な計算方法を用いることで、成形トラブルを未然に防ぎ、安定した品質の製品を効率的に生産することが可能になります。さらに詳しい成形機の選定基準や総合的な判断については、シリーズコラム第4回「成形機サイズの決め方:製品重量・投影面積・型寸法から総合判断する方法」で解説しています。