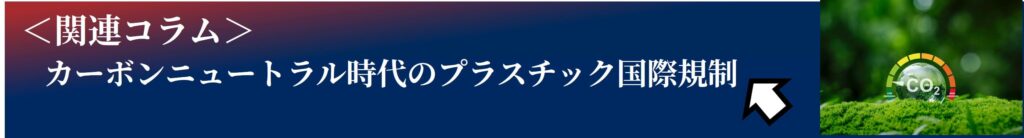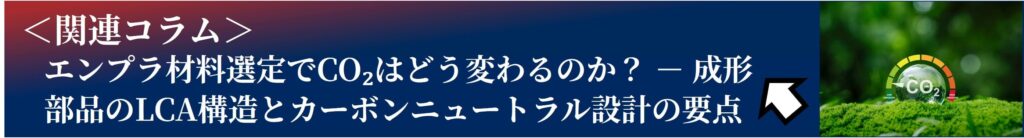エンプラのリサイクルグレードとは? ─ マテリアルリサイクルとケミカルリサイクル

近年、射出成形分野においてリサイクル材の活用が急速に進んでいます。この背景には、地球規模での環境負荷低減に対する社会的な要請の高まり、各国・地域の環境規制の強化、そしてサプライチェーン全体でのサステナビリティへの意識向上による顧客要求の厳格化があります。
このような状況において、府中プラは設計者の皆様が「リサイクルグレード」を正しく理解し、適切な材料選定や設計判断ができるよう支援することが重要であると考えます。
本コラムでは、エンプラにおけるリサイクル材の種類と基本的な特性について整理し、特に実務で主要となる「マテリアルリサイクル」と「ケミカルリサイクル」の基礎知識を解説します。
エンプラにおけるリサイクル材の位置づけ
環境意識の高まりとともに、様々な産業分野でリサイクル材の活用が推進されています。特に、PC(ポリカーボネート)、PA(ポリアミド)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)といったエンプラの分野では、その優れた機械的特性や耐熱性から幅広い用途で利用されており、リサイクルへの期待も大きくなっています。これらの樹脂は、家電製品、OA機器、建材など、多岐にわたる製品に採用されています。
射出成形用途における「リサイクルグレード」とは、使用済みのプラスチック製品や製造工程で発生する端材を回収し、再加工して得られる樹脂のグレードの総称です。これらは多くの場合、バージン材と比較して、品質、安定性、および調達面でいくつかの違いを持ちます。例えば、バージン材が持つ均一な物性や安定した供給に対し、リサイクル材は回収源やリサイクル方法によって物性にばらつきが生じる可能性があり、調達ルートも限定される場合があります。設計者はこれらの違いを理解した上で、リサイクルグレードの採用を検討する必要があります。
マテリアルリサイクル
マテリアルリサイクルとは、使用済み成形品や製造工程で発生する端材を物理的に粉砕し、洗浄、乾燥、溶融、ペレット化といった工程を経て、再び成形材料として利用する方法です。最も一般的で広く行われているリサイクル手法であり、射出成形分野で利用されるリサイクルグレードの多くはこの方式で製造されます。
特徴

マテリアルリサイクルの大きな特徴は、比較的シンプルな工程でリサイクル材を製造できる点にあります。このため、製造コストを抑えやすく、成形サイクルに直接戻して再利用できることから、コストメリットを享受しやすいという利点があります。特に、成形工場内で発生するランナーや不良品といった端材(ポストインダストリアルリサイクル:PIR材)を再利用する場合には、そのメリットは顕著です。
しかし、デメリットも存在します。樹脂は熱履歴や水分に晒されることで、加水分解や熱劣化といった化学変化を起こし、機械的特性が低下する場合があります。特にエンプラは、一般的に高温での成形が必要となるため、リサイクルを繰り返すことで分子鎖が切断されたり、架橋反応が進行したりするリスクがあります。これにより、強度、弾性率、衝撃吸収性などがバージン材に比べて低下する可能性があるため、注意が必要です。
この物性低下のリスクを考慮し、マテリアルリサイクル材はバージン材とブレンドして使用されるのが一般的です。
代表例
PC(ポリカーボネート)のリサイクル材は、マテリアルリサイクルの典型的な例です。使用済みのOA機器ハウジングやボトルなどを回収し、粉砕・ペレット化されたものが再利用されます。これらのリサイクルPCは、主にOA機器の内部部品や筐体、家電製品の部品などに活用され、要求される機械的特性が比較的緩やかな用途でその真価を発揮します。
PBT(ポリブチレンテレフタレート)のリサイクル材もまた、マテリアルリサイクルで広く利用されています。使用済みの電装部品や自動車部品(府中プラの主要事業とは異なりますが、参考として挙げます)などから回収されたPBTが再ペレット化され、電装部品のハウジングやコネクタ、一部の機械部品などに活用されています。PBTは耐薬品性や電気特性に優れるため、リサイクル材もこれらの特性が求められる用途で検討されることが多いです。
ケミカルリサイクル
ケミカルリサイクルとは、使用済みプラスチックを化学的に分解し、モノマー(単量体)やオリゴマー(少数のモノマーが結合したもの)の状態に戻した後、これらを精製し、再び重合させて樹脂を製造する方法です。分子レベルで樹脂を再構築するため、高品質なリサイクル材を得られる点が最大の特徴です。
特徴

ケミカルリサイクルの最大の特徴は、バージン材とほぼ同等の物性を持つ樹脂を再生できる可能性が高いことです。マテリアルリサイクルで懸念される熱劣化や加水分解による物性低下の影響を最小限に抑えることができるため、より高い品質や信頼性が求められる用途での採用が期待されます。例えば、食品容器や医療機器など、厳格な品質基準が求められる分野でもケミカルリサイクル材の適用が検討され始めています。
しかし、ケミカルリサイクルはマテリアルリサイクルと比較して、設備コストやエネルギーコストが高いという課題があります。複雑な化学プロセスや高度な精製技術が必要となるため、その投資額は大きくなります。また、分解・再重合のプロセスには多大なエネルギーを消費する場合があり、そのライフサイクルアセスメント(LCA)を考慮した上で、環境負荷低減効果を評価することが重要です。
これらのコスト構造から、ケミカルリサイクル材は射出成形材としては高付加価値用途に向けられることが多いです。特に、高い機械的特性、耐熱性、寸法安定性などが不可欠な部品や、バージン材からの置き換えが難しい高性能な部品での採用が期待されます。
代表例
PA(ポリアミド、ナイロン)やPET(ポリエチレンテレフタレート)は、ケミカルリサイクルの代表的な適用事例を持つ樹脂です。PAは加水分解に対して比較的弱く、マテリアルリサイクルでは物性低下が顕著になる場合がありますが、ケミカルリサイクルであれば高品質なPAを再生できます。再生されたPAは、コネクタ、機械部品、繊維製品など、幅広い用途で活用されています。
PETのケミカルリサイクルは、主にボトルtoボトルとして、使用済みPETボトルを回収し、分解・精製して再びPETボトルを製造するサイクルで確立されています。射出成形分野においても、再生PETはコネクタ部品や電子機器のハウジング、一部の工業用部品など、高付加価値が求められる用途で採用が進んでいます。特に、高い剛性や耐熱性、電気特性が求められる部品において、ケミカルリサイクルPETの可能性が探られています。
設計者が理解すべきリサイクルグレードの特性
リサイクルグレードの採用を検討する際には、バージン材とは異なる特性を設計者が深く理解することが不可欠です。以下に、特に注意すべき点を挙げます。
強度・寸法安定性のバラつき

マテリアルリサイクル材では、回収源のばらつき、リサイクル工程での熱履歴、異物混入の可能性などにより、強度や寸法安定性にロット間のバラつきが生じることがあります。例えば、引張強度や曲げ弾性率がバージン材よりも低下する可能性があり、また、成形時の収縮率が変動することで、成形品の寸法精度に影響を及ぼす場合があります。特に、高精度が要求される部品や、負荷がかかる構造部品への適用には、事前の十分な評価が必要です。ケミカルリサイクル材はバラつきが少ない傾向にありますが、それでもバージン材同等であるかをデータで確認することが重要です。
外観性(色むら、透明性低下など)
リサイクル材は、バージン材と比較して外観品質が劣る場合があります。特にマテリアルリサイクル材では、回収された材料の色が混在することによる色ムラ、異物混入による黒点、熱劣化による黄変、透明性低下などが発生しやすくなります。着色することで目立ちにくくすることは可能ですが、それでも色調の安定性はバージン材に及ばないことが多いです。外観が製品の評価に直結する部品、特に意匠部品や透明度が求められる部品への適用は、慎重な検討が求められます。
物性データの信頼性と限界
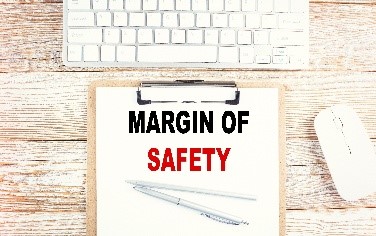
サプライヤーから提供されるリサイクルグレードの物性データは、多くの場合、特定のロットで測定された代表値です。しかし、前述の通り、リサイクル材はロット間で物性が変動する可能性が高いため、バージン材のデータと同じ感覚で評価することは危険です。設計時には、提示された物性データが最低保証値なのか、平均値なのかを確認するとともに、ロット間のバラつき範囲に関する情報も入手し、安全率を十分に考慮した設計を行う必要があります。可能であれば、試作を通じて実部品での物性評価を行うことが望ましいです。
調達面での制約(供給安定性、グレード数の制限)
リサイクル材の調達は、バージン材と比較して制約が多い場合があります。回収源の確保状況やリサイクルプラントの稼働状況によって、供給が不安定になるリスクがあります。また、リサイクル材として提供されるグレードの選択肢も、バージン材ほど豊富ではないのが現状です。特定の物性や色調のリサイクル材が必要な場合でも、それに合致するグレードが見つからないことがあります。安定供給の確保や、将来的なグレード変更の可能性なども考慮した上で、サプライヤーとの密な連携が不可欠です。
まとめ
エンプラのリサイクルグレードは、環境負荷低減とコストメリットの追求において、今後ますますその重要性を増していきます。特に実務的に重要なリサイクル手法として「マテリアルリサイクル」と「ケミカルリサイクル」の二つがあり、それぞれ異なる特徴と課題を持っています。
設計の第一歩は、これらリサイクル材がバージン材と比較してどのような特性の違いを持つのかを深く理解することです。強度や寸法安定性のバラつき、外観品質、物性データの信頼性、そして調達面での制約といった点を十分に考慮し、適用する部品の要求品質とリサイクル材の特性を適切にマッチングさせる必要があります。
次回(第2回)では、「設計・成形でどう使いこなすか」に焦点を当て、具体的な設計上の注意点、成形条件の最適化、品質保証の考え方などについて、府中プラの知見を交えながら解説いたします。