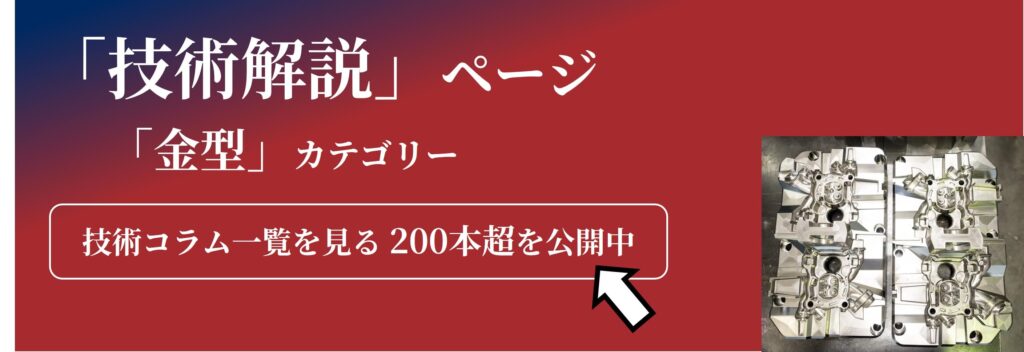射出成形における回転コアの基礎知識 ― 仕組み・種類・用途を徹底解説

射出成形は、複雑な形状を持つ製品を量産するために不可欠な技術です。しかし、設計上の自由度が高まるほど、金型構造は複雑化し、単純な直線的抜き方向だけでは対応できないアンダーカット形状が生じます。このような場合に活躍するのが「回転コア」です。府中プラでは、産業機器や流体制御部品を中心に、回転コアを活用した成形に取り組んできました。本コラムでは、その基礎知識として仕組みや種類、用途を整理します。
回転コアの基本原理
回転コアは、金型内部のコアを回転させることで、成形品のアンダーカットを解消しながら製品を金型から取り出す仕組みです。通常のスライドコアは直動で成形品を抜くため、ねじ構造や斜め方向のリブのように単純な直線運動では干渉が避けられない場合は対応できません。そこでコアを回転させ、樹脂製品の内側形状に沿って抜き取ることで離型が可能になります。
この仕組みにより、二次加工でねじ切りを行う必要がなくなり、製品強度や気密性を損なわずに一体成形を実現できます。さらに、回転コアは単なる「離型の補助」ではなく、設計段階での自由度を飛躍的に高める技術でもあります。例えば、従来は分割構造や接着が必須だった部品を、一体成形に置き換えることが可能となります。
回転コアの種類
回転コアにはいくつかの方式があり、製品形状や生産数量、求められる精度によって選択が分かれます。ここでは代表的な4種類を整理します。
手動回転コア
最も簡易的な方式で、成形サイクル終了後に作業者がコアを手で回転させて抜き取ります。設備投資を抑えられるため試作や小ロット品に適しますが、量産には不向きです。初期検討や外観確認の段階で有効に活用されます。
機械式回転コア
金型の開閉動作と連動し、ラック&ピニオンやカム機構を利用してコアを自動回転させる方式です。追加の動力源を必要とせず構造が比較的単純なため、保守性が高く広く使われています。例えば、樹脂製のキャップや簡易的な継手などで安定した量産が可能です。ただし、ギア部分の摩耗により精度が低下しやすいため、定期的なメンテナンスが求められます。
油圧・空圧駆動型
シリンダーを利用して強制的にコアを回転させる方式です。大型部品や高トルクが必要な部品に適しており、駆動力の安定性に優れます。産業用ポンプやバルブのインペラ成形などで採用されますが、金型に配管や制御機器を組み込む必要があり、コスト増とメンテナンス負荷が課題です。
サーボモータ駆動型
近年注目される方式で、サーボモータによってコアを高精度に制御します。ねじ構造や微細形状など位置決めが重要な部品に適し、自動化ラインにも組み込みやすい点が利点です。一方で、初期投資は高く、メンテナンスにも専門知識が求められます。分析機器や精密バルブのように品質安定が優先される分野で採用が進んでいます。
回転コアが必要となる代表的な製品
ネジ付き部品
ボトルキャップやねじ式の締結部品は、回転コアを代表する用途です。金属切削や後加工によらず、成形サイクルの中でねじを形成できるため、大幅な工程削減につながります。
インペラやファンブレード
流体機器のインペラやファンブレードは、斜め方向に複雑な羽根が配置されるため、直線的な抜き方向では成形できません。回転コアを用いることで、羽根形状を一体的に成形でき、強度や耐久性の向上が可能になります。府中プラでも、ポンプや送風機関連部品の樹脂化提案において回転コアを活用しています。
医療機器・バルブ・流路部品
医療用のバルブや継手は、流路内部に複雑なねじや段差を伴うことが多く、高精度と密封性が求められます。回転コアはこうした内部構造の一体化に適しており、金属部品からの代替や軽量化を実現する手段となっています。
回転コアのメリット
回転コアを導入する最大の利点は、従来では不可能または後加工を必要としていた複雑形状を、一体で成形できる点にあります。ここでは代表的な三つのメリットを整理します。
一体成形による強度と信頼性の向上
分割した部品を接着やねじ止めで組み立てる場合、接合部が弱点となり、強度低下や気密不良の原因となります。回転コアを使えば、一体成形によって接合部が不要となり、強度や耐圧性能が高まります。例えば、流体を扱う継手やバルブでは、シール性が大きく向上し、長期使用における漏れや破損リスクを低減できます。
二次加工レスによる効率化とコスト削減
従来は射出成形後に切削でねじを加工することが一般的でしたが、回転コアを利用すれば成形工程の中でねじ形状を完成させることが可能です。これにより追加工数を削減でき、量産ラインでは大幅なコスト低減につながります。また、加工時のバリや欠けの発生がなくなるため、品質の安定化にも寄与します。実際にねじ付きキャップや小型機構部品では、このメリットが高く評価されています。
設計自由度の拡大と高機能化
回転コアを使うことで、従来は金型構造上不可能とされた複雑なアンダーカット形状も実現可能になります。これにより、設計者は部品点数削減や小型化を積極的に進められます。例えば、ポンプ用のインペラを樹脂一体成形することで、軽量化と性能安定を同時に実現できます。また、部品を一体化することで組立工数も減少し、製品全体の信頼性向上につながります。
このように、回転コアは「強度」、「効率」、「設計自由度」という三つの観点で大きな価値を持ちます。産業機器や医療機器など高精度・高信頼性が求められる分野では特に有効であり、樹脂化による新しい設計戦略を可能にする技術といえます。
回転コアの課題
回転コアは設計自由度を大きく広げる一方で、導入にはいくつかの課題も伴います。これらを理解し、設計段階から対策を検討することが重要です。
金型構造の複雑化
回転コアを組み込むと、ギア、ラック、シリンダー、モータなどの駆動部品が追加され、金型全体の構造は複雑になります。その結果、製作コストは通常金型より高くなり、設計から量産開始までのリードタイムも長期化します。特にサーボ駆動型や油圧式では制御機器や配管が必要となり、初期投資が大きな負担となります。
メンテナンスと耐久性
回転機構は摩耗や損傷が避けられず、定期的な保守が不可欠です。潤滑不足や摩耗粉の発生は、離型不良や外観不良につながります。例えばギアが摩耗すると回転角度が安定せず、ねじ形状の精度が落ちることがあります。耐摩耗材や表面処理で寿命を延ばすことは可能ですが、その分コストが増加するため、維持管理と経済性のバランスをとる必要があります。
成形サイクルへの影響
回転動作が加わる分、成形サイクルは通常より長くなります。1ショットで数秒の差であっても、大量生産では年間数万〜数十万個単位での生産効率に影響します。特にトルクが大きい樹脂や複雑な形状では回転動作に時間を要し、歩留まりやコストに直結します。そのため、回転角度を最小化した設計やサーボ制御による動作高速化が求められます。
このように、回転コアは大きな利点を持つ一方で、コスト、メンテナンス、効率面での課題を伴います。設計者は利点とリスクを比較し、事前に十分な検討を行う必要があります。
府中プラの取り組み
府中プラは、電子機器、機械部品、流体制御機器、医療機器など、幅広い分野で回転コアを活用した成形実績を積み重ねてきました。特にインペラやポンプ部品のような流体関連部品では、金属から樹脂への置換を提案することで、軽量化と耐食性の両立を実現しています。
また、バルブや継手といった高精度流路部品では、気密性を確保しながら複雑な内部構造を一体成形するために回転コアを採用し、製品の信頼性向上に貢献しています。
府中プラは、単に回転コアを導入するのではなく、設計段階からお客様と協働し、コア構造や離型方法を最適化する提案を行っています。設計上の制約を踏まえつつ、金型構造、成形条件、量産効率を総合的に考慮し、最適解を導き出すことを強みとしています。こうした取り組みによって、後加工レス化、製品寿命の延長、品質安定化を同時に実現してきました。
まとめ
回転コアは、射出成形における特殊技術でありながら、複雑形状の一体成形を可能にし、設計の自由度を飛躍的に広げます。製品の信頼性向上、二次加工レスによる効率化、軽量化や耐食性の改善など、多くの利点をもたらします。一方で、金型構造の複雑化やコスト増といった課題もあるため、採用には慎重な検討が必要です。
府中プラは、設計段階からの相談を重視し、回転コアの効果を最大限に引き出す提案を行っています。設計者にとって、回転コアは単なる特殊機構ではなく、新しい設計戦略の一部として位置付けられるべき存在です。新規設計の際は、ぜひお気軽に府中プラまでご相談ください。