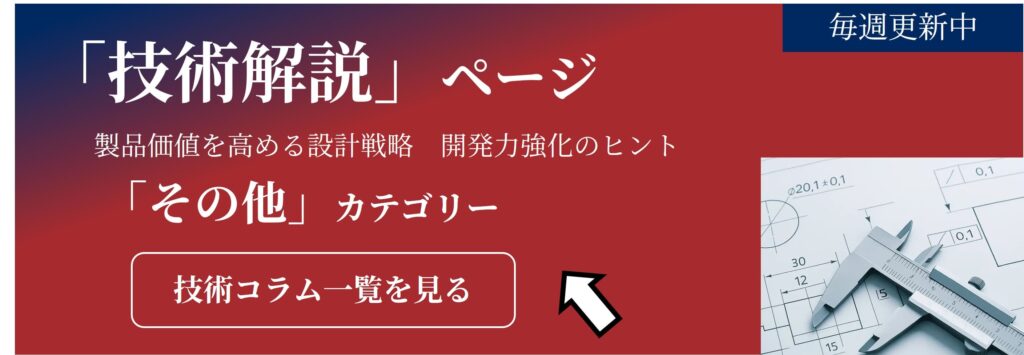射出成形部品の最適接合法 ― 超音波溶着/レーザー溶着/インサート成形の設計判断
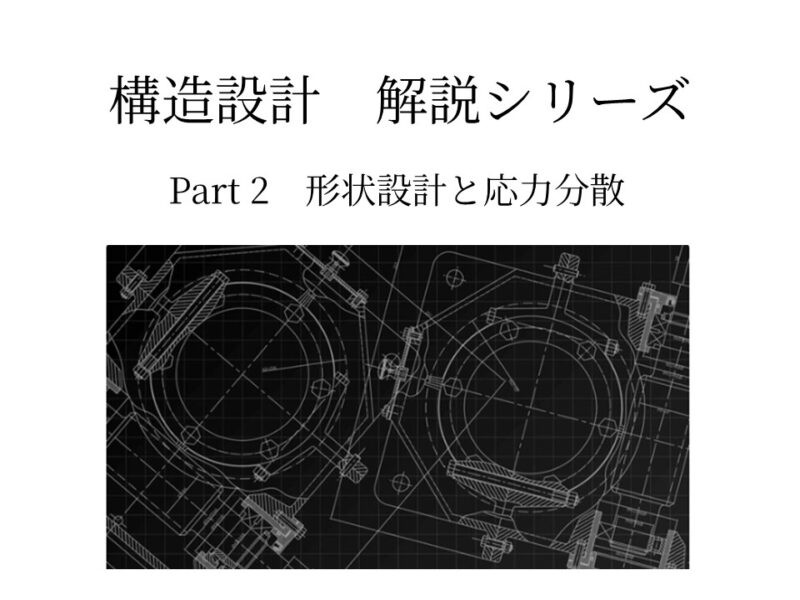
シリーズコラム第7回
エンプラ部品の接合は、単なる「固定」ではなく、製品に求められる「機能」を形成する重要な設計プロセスです。強度不足、気密性の欠如、耐久性の問題といった不具合の多くは、実は部品設計そのものよりも、接合方式の選択が製品要件とミスマッチしていることに起因します。
本コラムは、特定の接合技術のメリットを個別に紹介するものではありません。設計者が直面する課題に対し、「なぜその接合方法を選ぶのか」という判断基準、すなわち用途ごとの最適解を導き出すための設計視点に焦点を当てて解説します。
接合方式は“技術の優劣”ではなく、設計要件に対する“適合性”で選ぶ
超音波溶着、レーザー溶着、インサート成形といった技術には、それぞれに優れた特性がありますが、技術単体での優劣を比較することに大きな意味はありません。重要なのは、製品の設計要件に対して、どの技術が最も適合するかを見極めることです。
その選定の出発点となるのが、以下の3つの設計パラメータです。
- 荷重と応力のかかり方: 部品にどのような力(引張、圧縮、せん断、疲労、衝撃)が、どの程度の期間加わるのか。
- 気密・耐久などの機能要求: 防水・防塵といったシール性能や、特定の環境下での長期的な信頼性が求められるか。
- 材料の応答特性: 使用する樹脂の光学的特性(透明性)、吸水性、結晶性、また金属との熱膨張係数の差など、材料が持つ物理的性質。
設計者は、まずこれらの要求仕様を明確に定義し、3つの軸で評価することから、最適な接合方式の選定を始めるべきです。技術の流行や得意な方法から選ぶのではなく、設計要件から論理的に選択肢を絞り込むアプローチが不可欠です。
各方式の設計適性
ここでは、3つの代表的な接合方式について、どのような設計条件に適し、どのような制約や留意点があるかを簡潔に整理します。
| 接合法 | 適する設計条件 | 制約・留意点 |
| 超音波溶着 | 高い気密性や液密性が求められる容器形状。サイクルタイムを重視する大量生産品。多くの汎用エンプラやスーパーエンプラに適用可能。 | 溶着強度と安定性を確保するため、エネルギーダイレクタ(ED)に代表される専用のジョイント設計が必須。ガラス繊維などの強化材を含む場合、繊維の配向が強度に影響を与えることがある。 |
| レーザー溶着 | 接合部周辺への熱影響を極限まで抑えたい微細部品や精密部品。接合痕が目立たない、高い外観品質が求められる製品。透明樹脂同士の接合。 | 片方の部品がレーザー光を透過し、もう一方が吸収するという材料の光学的特性が必須条件。適用できる材料の組み合わせが限定されるため、特殊な用途になりやすい。 |
| インサート成形 | 大きな引張荷重や繰り返し発生する疲労荷重に耐える必要がある部位。確実な導電性や固定強度が求められる端子・ネジ部品。安全性が最優先される重要保安部品。 | 樹脂と金属の熱膨張係数の差により、成形後の冷却過程で反りや内部応力が発生しやすい。確実な結合を得るため、インサート部品のローレット加工やアンダーカット形状など、界面の設計が極めて重要になる。 |
設計段階での選定フロー
最適な接合方式は、設計要件を一つずつ確認していくことで、自然と導き出されます。府中プラが実践する選定フローを、設計者の思考プロセスに沿って紹介します。

Step 1:応力/荷重形態を確認する
まず、接合部にどのような力がかかるかを分析します。
継続的な引張荷重、ねじり、繰り返し発生する振動や衝撃が主な負荷となる場合、樹脂だけでは長期的な信頼性を確保できない可能性があります。このような高荷重や疲労が想定される設計では、金属部品の剛性を利用して構造的に一体化させるインサート成形が最初の有力候補となります。一方、静的な荷重や、部品全体で応力を分散できる構造であれば、他の選択肢を検討します。
Step 2:気密・シール性の必要性を確認する
次に、製品に防水、防塵、液密性といったシール性能が求められるかを確認します。
ケースや容器のように、内部を保護するための高い気密性が必要な場合、接合界面を溶融させて一体化する超音波溶着やレーザー溶着が適しています。特に超音波溶着は、適切に設計されたジョイントによって接合面全体を均一に溶融させるため、安定したシール性能を実現しやすいです。
Step 3:使用温度・熱影響を確認する
製品の使用環境や、接合プロセスが内部部品に与える影響を評価します。
接合部の周辺に熱に弱い電子部品などが実装されている場合、熱影響を最小限に抑える必要があります。この点では、エネルギーを微小な領域に集中させ、非接触で加工できるレーザー溶着が最も有利です。超音波溶着も局所的な発熱であるため熱影響は比較的小さいですが、振動が内部の繊細な部品に影響を与えないか確認が必要です。インサート成形は、溶融樹脂がインサート部品全体を包み込むため、熱影響は最も大きくなります。
Step 4:材料の特性・光学性を確認する
使用する樹脂材料の特性が、接合方式の制約とならないかを確認します。
ここで最も重要なのがレーザー溶着の適性です。レーザー溶着は、片方の樹脂がレーザー光を透過し、もう一方が吸収するという原理に基づいているため、材料の組み合わせがこの条件を満たさない限り採用できません。透明な材料同士の接合などが主な用途となり、汎用性は高くありません。一方、超音波溶着は多くの熱可塑性樹脂に適用できますが、POMのように振動エネルギーを吸収しにくい材料や、吸湿性の高いPAのように厳密な乾燥管理が必要な材料では、条件設定の難易度が上がります。
Step 5:量産のサイクルタイム・初期費用の許容範囲を確認する
最後に、生産性(サイクルタイム)とコストのバランスを評価します。
一個あたりの接合時間が0.1秒~数秒と非常に短い超音波溶着は、大量生産におけるコスト効率で圧倒的に有利です。ただし、製品ごとに専用のホーン(工具)や治具が必要になります。インサート成形は、射出成形と同時に接合が完了するため、後工程の組立が不要になり、トータルでの生産性を高められる場合がありますが、金型が複雑化し初期投資は増加する傾向があります。レーザー溶着は、設備自体が高価になることが多く、初期投資の観点からは慎重な判断が求められます。
このように、設計要件を順に検討することで、複数の候補の中から最も合理的な接合方式を一つに絞り込むことが可能です。
超音波溶着とインサート成形が「なぜ汎用性が高いのか」
前述の選定フローからも分かるように、レーザー溶着は材料の光透過性という明確な制約から、その用途は微細加工や医療分野などの特殊なケースに限定されます。
一方で、多くのエンプラ部品において、超音波溶着とインサート成形が汎用性の高い選択肢となるのには明確な理由があります。

超音波溶着は、「強度」、「気密性」、「自動化(量産性)」、「材料自由度」の4つのバランスに優れています。分子レベルで樹脂を一体化させるため信頼性の高い強度と気密性を実現でき、高速なサイクルは自動化ラインとの親和性が高く、多くの熱可塑性樹脂に対応できるため、電子機器の筐体やセンサーケースなど、一般的なエンプラ部品の接合において、多くの場合で標準的かつ最適な選択肢となります。
対してインサート成形は、「構造の一体化」と「高荷重・高耐久性」が求められる場面で戦略的な選択肢となります。金属の強度や導電性といった機能を樹脂部品に直接付与できるため、単なる接合に留まらず、部品点数の削減や軽量化、そして製品全体の信頼性向上に大きく貢献します。特に、従来は金属切削品などで対応していた部品をエンプラ化する際に、強度と信頼性を両立させるための鍵となる技術です。
まとめ
エンプラ部品の接合方式は、「どの技術が最も高性能か」で選ぶ時代から、「製品の機能要求に対して、どの技術が最適解か」を設計段階で見極める時代へと移行しています。接合方式の選定は、後工程で変更することが困難であり、最終製品の品質、信頼性、そしてコストを決定づける最重要ファクターの一つです。
府中プラは、特に汎用性の高い超音波溶着とインサート成形を得意とし、お客様の製品設計の初期段階から深く関与します。構想段階の図面から、製品に求められる真の要求機能を見極め、材料選定から最適な接合方式の提案まで、一貫した技術支援を提供できるパートナーでありたいと考えています。