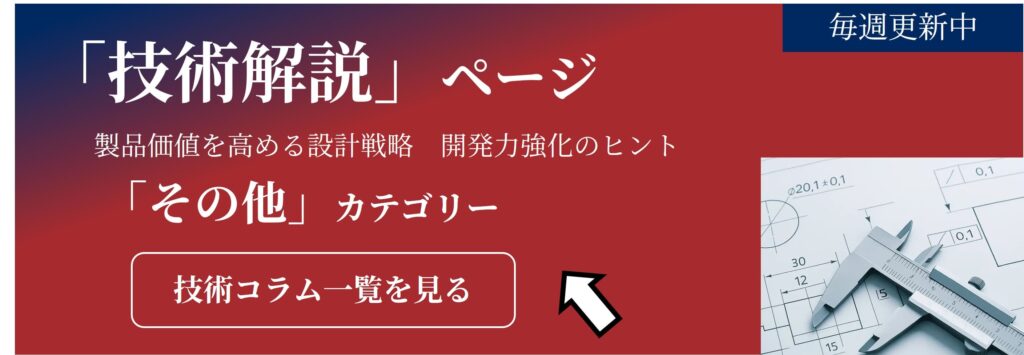射出成形部品のはめあい・嵌合(勘合) ― クリアランス・応力・寸法安定の三位一体設計
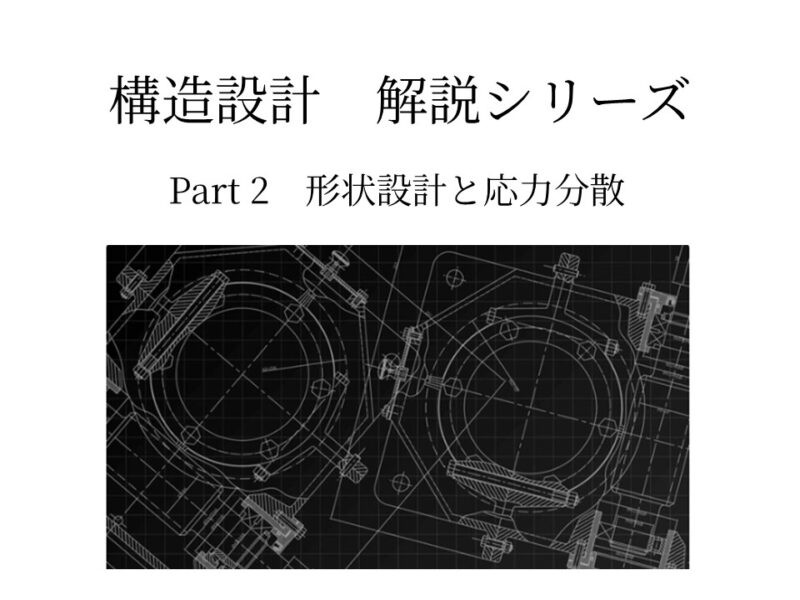
シリーズコラム第8回
金属設計の感覚で「寸法をぴったり合わせる」設計を樹脂に持ち込むと、ほぼ確実に不具合が生じます。射出成形部品は、成形収縮・冷却条件・吸水・熱膨張といった多くの要因によって、寸法が変動します。しかもそれらは、製品が使用される環境や時間の経過によっても変化するため、図面上の数値通りにはなりません。本コラムでは、金属的な“寸法合わせ”の発想を離れ、樹脂特有の寸法変動を前提にした嵌合設計の考え方を整理します。焦点は「クリアランス」、「応力」、「寸法安定性」の3要素をどう設計段階でバランスさせるか――。量産段階での安定性と信頼性を高めるための設計思想を解説します。
寸法が変動する3つの要因
樹脂部品の寸法は、複数の物理的要因によって常に変動しています。これを無視した設計は、組付け不良や経年劣化の原因となります。主要な変動要因は「成形収縮」「環境変化」「時間依存変形」の3つです。
成形収縮と冷却条件
樹脂は金型内で冷却・固化する際に必ず収縮します。この成形収縮率は、製品の部位によって均一ではありません。主な原因は、溶融樹脂の注入口であるゲートからの距離や、金型内の冷却経路の配置による冷却ムラです。ゲートに近い部分は圧力がかかり収縮が抑えられ、遠い部分は収縮が大きくなる傾向があります。また、冷却が速い部分と遅い部分でも収縮差が生じ、これが反りや変形の直接的な原因となります。
特にPA(ポリアミド)やPOM(ポリアセタール)などの結晶性樹脂は、冷却速度の影響を強く受けます。金型温度がわずかに変化しただけで収縮率が0.1%以上変動することも珍しくなく、100mmの部品であれば0.1mm以上の寸法差に繋がります。したがって、設計段階で「どの方向にどれだけ縮むか」を予測し、それを織り込んだ形状設計が極めて重要です。
吸水・熱膨張による寸法変化
成形後の寸法は、使用環境によっても変化します。その代表が吸水と熱膨張です。
ナイロン(PA)やPBTといった吸水性の高い樹脂は、大気中の水分を吸収して膨張します。例えば、PA66では吸水率が2%変化すると、寸法が0.4〜0.5%膨張することがあります。50mmの嵌合部であれば0.2mm以上の変化となり、初期クリアランスが不足していると、組付け後に過大な応力が発生し、変形や割れを引き起こします。
一方、PC(ポリカーボネート)などの非晶性樹脂は吸水の影響が小さいものの、熱膨張が支配的です。樹脂の線熱膨張係数は金属の数倍から10倍程度大きいため、使用温度範囲が広い製品では、温度変化による伸縮を考慮した設計余裕が不可欠です。
応力集中と時間依存変形(クリープ)

樹脂は、一定の荷重がかかった状態で時間が経つと、徐々に変形し続ける「クリープ」という現象を起こします。圧入などの嵌合部では、このクリープによって部品内部の応力が低下し(応力緩和)、初期に確保されていたはめ合い力が失われることがあります。
この時間依存の変形は、応力が局所的に集中する箇所で特に進行が速くなります。設計上のシャープな角や断面が急変する部分は応力集中の起点となり、短期的には問題が見られなくても、長期的にはその部分から白化や割れが発生する原因となります。長期信頼性を確保するためには、応力集中を避け、時間経過による変形を考慮した設計が不可欠です。
はめあい設計の三原則
樹脂の寸法変動を前提とした設計では、従来の「寸法精度を追求する」考え方から転換する必要があります。府中プラでは、安定した嵌合を実現するために「クリアランス」、「応力分散」、「寸法基準」の三原則を重視しています。
クリアランスで吸収する設計
樹脂の寸法変動は避けられないため、これを力で抑え込むのではなく、意図的に設けた「遊び(クリアランス)」で吸収する発想が基本です。ガタを完全に排除しようとすると、成形ばらつきや環境変化によって必ず無理が生じ、過大な応力や組付け不良を招きます。
重要なのは、クリアランスを「許容誤差」ではなく、変動を吸収するための「機能」として設計に組み込むことです。想定される最大寸法と最小寸法の両極端なケースを考慮し、その範囲内で機能が成立するクリアランスを設定します。この「吸収設計」こそが、量産時の安定性と製品の長期信頼性を両立させる鍵です。
応力を分散させる面接触構造
樹脂は応力集中に弱く、局所的な高応力は長期的な破損の原因となります。そのため、嵌合部での接触は、点や線ではなく、できるだけ広い「面」で荷重を受ける構造とすることが鉄則です。接触面積を広げることで単位面積あたりの応力を低減し、材料の許容応力に対して安全マージンを確保します。
また、応力集中を緩和するために、リブの付け根や嵌合部の根元といった形状変化部には、必ず適切な半径のRを設けます。これにより応力の流れが滑らかになり、局所的なピーク応力を低減できます。弾性変形を利用するスナップフィット構造なども、アーム形状の工夫によって応力を全体に分散させており、この応力分散設計の応用例と位置づけられます。
環境変化を織り込んだ寸法基準

図面寸法を議論する際、「どの状態での寸法か」を明確にすることが重要です。一般的に、寸法検査は成形直後の乾燥状態で行われますが、製品が実際に機能するのは市場の温湿度環境下です。
そこで、寸法の基準点を「成形直後」ではなく「実使用環境」に設定する考え方を推奨します。使用する材料の吸水率や熱膨張係数から、実際の使用環境下での寸法変化量を予測し、その変化分をあらかじめ相殺するように図面寸法を設計します。例えば、吸湿で0.2%膨張するなら、図面寸法を予め0.2%小さく設定しておくのです。この「実効寸法」を基準とすることで、環境変化による不具合を未然に防ぎ、後工程での補正作業を大幅に削減できます。
嵌合(勘合)構造別の設計視点
三原則は、具体的な嵌合構造においてどのように適用されるのでしょうか。代表的な3タイプについて解説します。
差し込み・圧入タイプ
軸を穴に圧入する設計では、材料の弾性変形の範囲内で生じる反発力を利用して保持力を確保します。しめしろ(干渉量)は、材料の許容ひずみを超えず、かつクリープによる応力緩和後も必要な保持力が残る範囲で設定する必要があります。
局所的な応力集中を避けるため、嵌合長を十分に確保し、接触圧力を分散させることが基本です。短い距離で強い保持力を得ようとすると、過大な応力を生じさせます。また、応力が集中しやすい嵌合部の根元には必ずRを設け、冷却収縮によるヒケを防ぐため、周辺の肉厚を均一に保つことも重要です。
摺動・スライドタイプ
部品が繰り返しスライドする部分では、摩擦による熱膨張を考慮したクリアランス設定が不可欠です。クリアランスが小さすぎると、熱膨張で摺動抵抗が増大し、動作不良を起こします。逆に大きすぎるとガタつきの原因となります。
ガラス繊維(GF)で強化された材料では、繊維の配向にも注意が必要です。GFは樹脂の流動方向に沿って並ぶため、摺動方向と流動方向を合わせるようにゲート位置を設計することで、反りを抑制し、繊維の先端が相手材を攻撃することによる摩耗を低減できます。摺動部では、初期の応力だけでなく、長期的な摩耗の進行が寿命を決定する要因となります。
面合わせ・嵌合フランジタイプ
筐体のように広い面で合わせる部品において、完全な平面度を出すことは困難です。成形時の収縮差によって、必ずある程度の反りやうねりが発生します。
この問題に対しては、全面を密着させるのではなく、「どこで力を受け、どこで応力を逃がすか」を意図的に設計します。機能的に重要なシール面などを除き、あえて微小な溝や段差といった「逃げ」を設けることで、反りによる隙間をその部分に吸収させ、重要な部分の密着不良を防ぎます。これは、避けられない成形ばらつきを制御可能な構造に置き換える、合理的な設計アプローチです。
寸法安定性を高めるための設計着眼点
これまでの内容を踏まえ、設計段階で寸法安定性を高めるための具体的な着眼点を整理します。
- 寸法基準の統一:寸法基準は金型の固定側か可動側のどちらか一方に統一し、金型のPL(パーティングライン)をまたぐ寸法基準は避ける。これにより、金型の合わせズレによる影響を最小限に抑えます。
- 収縮のコントロール:ゲート位置や冷却経路を製品形状に対して対称に配置するなど、金型構造を意識して設計する。これにより、収縮の方向と量をある程度コントロールし、反りを抑制します。
- 材料特性の考慮:
◦ 結晶性樹脂:成形収縮率が大きく、成形条件の影響を受けやすいため、条件ばらつきを見越したクリアランス設定が重要。
◦ 非晶性樹脂:熱膨張係数が大きいため、使用温度変化による変形や反りへの対策を重視する。
- CAE解析の活用:流動解析や反り解析を用いれば、成形後の変形を高い精度で予測できます。この結果に基づき、クリアランスを定量的に設計することで、勘や経験に頼らない再現性の高い設計が可能になります。
まとめ
はめあい・嵌合(勘合)部の樹脂設計においては、金属的な「寸法精度の追求」ではなく、樹脂が変動することを前提に“どう逃がすか”を設計する思想が重要です。クリアランス・応力・寸法安定性の三位一体設計を実践すれば、設計通りの嵌合感と量産安定性を両立させることができます。府中プラは、材料特性と成形条件を踏まえた「再現性ある嵌合設計」の視点から、お客様の量産設計を支援しています。