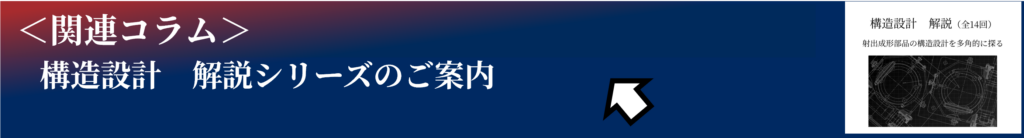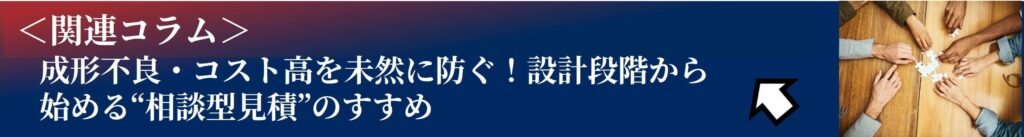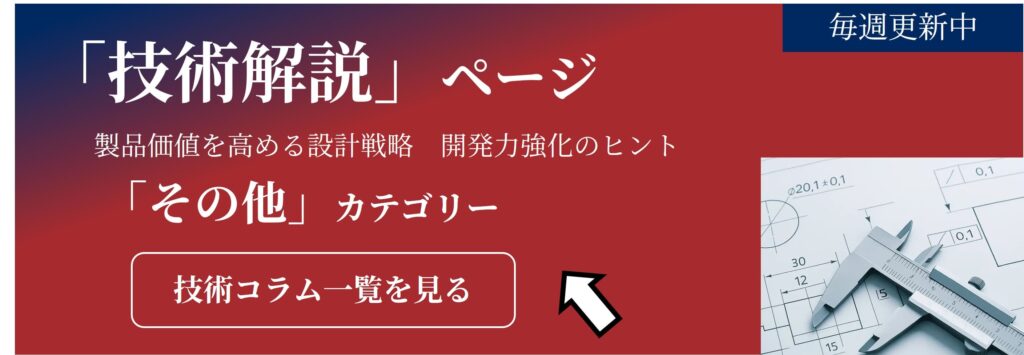射出成形部品の設計における「たわみ予測」 - 荷重変形を制御する設計思考
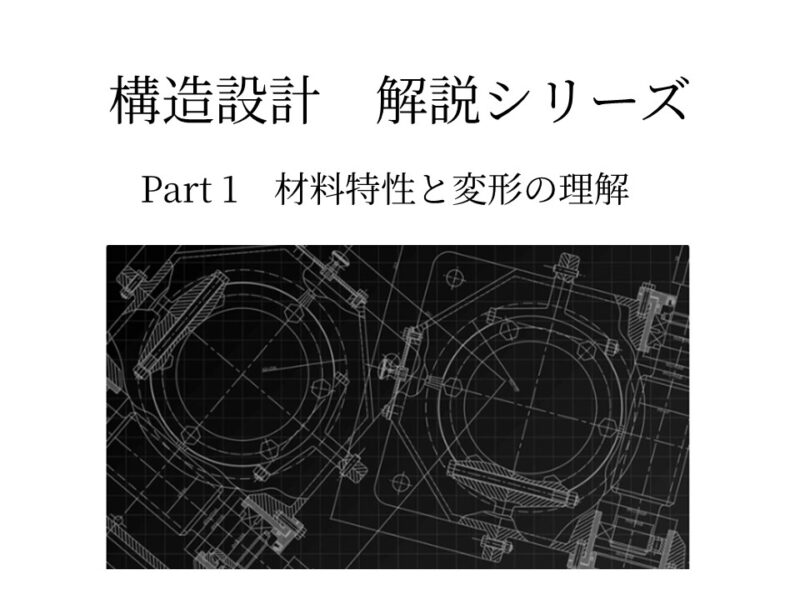
シリーズコラム第2回
製品設計において、「強度」と「剛性」はしばしば混同されがちですが、その意味は明確に異なります。「強度」が材料の限界、すなわち「壊れないこと」を指すのに対し、「剛性」は使用時の安定性、つまり「荷重がかかっても許容範囲内で形状を保つこと」を意味します。量産の現場では、部品が壊れることよりも、むしろ「たわみのばらつき」が原因で発生するクリアランスの異常や外観不良といった機能的な不具合の方が、より頻繁に問題となります。本コラムでは、この「たわみ」を制御するための剛性設計に焦点を絞り、その基本的な考え方とセオリーを解説します。
まず決めるのは「許容たわみ」=機能側の基準
剛性設計の第一歩は、材料や形状を検討する前に、「この部品は、どの程度の変形(たわみ)まで許されるのか」という機能上の基準を明確に定義することです。この基準がなければ、設計のゴールが定まらず、過剰品質や性能不足に陥る原因となります。
「許容たわみ」は、製品の機能と直結しています。例えば、以下のような項目が具体的な基準となります。
- クリアランスの確保: 摺動部品や嵌合部品同士が接触しないための隙間。
- 光学性能の維持: レンズやセンサーの光軸がずれないための位置精度。
- シール性の確保: パッキンやガスケットを均一に圧縮するための線圧維持。
- 操作感の安定: スイッチを押した際のクリック感。
- 外観品質の担保: 筐体の合わせ目などに生じる段差や隙間。
重要なのは、これらの機能要件を「この部分のたわみ量が0.5mmを超えたら、シール性が確保できなくなる」といったように、具体的な数値目標として設計者が言語化しておくことです。この基準値が、後続の形状設計や材料選定のすべての判断軸となります。
剛性は形状で稼ぐのが基本
部品の剛性は、材料の硬さだけでなく、その「形状」によって大きく左右されます。むやみに肉厚を増やして材料で剛性を確保しようとすると、ヒケや反りといった成形不良を誘発し、かえって寸法ばらつきの原因となります。剛性はまず「形状でつくる」という発想が、再現性の高い設計の基本です。
- スパンを短くする
梁(はり)は、支点間の距離(スパン)が短いほどたわみにくくなります。これは剛性設計の最も基本的な原則です。長いスパンを持つ平板形状などでは、リブやボスを追加して支点を増やし、実質的なスパンを分割することが有効です。その際、荷重がかかる点の近くに支点を設けることが重要で、梁の中間のような最もたわみやすい位置にボスを配置するのは避けるべきです。 - cをつくる
同じ断面積でも、開いた断面(コの字形など)より閉じた断面(箱形や円筒形)の方が、ねじりや曲げに対して圧倒的に高い剛性を発揮します。部品の外周にフランジを設ける場合、途切れのない連続した形状にして「輪」をつくることで、部品全体の剛性は劇的に向上します。 - 肉厚をむやみに増やさない
前述の通り、肉厚を増やすことはヒケや反りのリスクを高め、剛性のばらつきにつながります。剛性が不足している場合は、まず肉厚を増やすのではなく、薄肉を維持したままリブを追加したり、閉断面構造を取り入れたりすることで対応すべきです。薄肉の基本構造に、効果的なリブを組み合わせる「形で剛性をつくる」設計が、品質とコストのバランスに優れます。 - 連続性を途切れさせない
リブは、その効果を最大限に発揮させるために、力の流れを意識した配置が重要です。荷重を受ける点から支点(ボスや側壁など)まで、途切れることなく連続して配置されたリブは、力をスムーズに伝達し、高い剛性を生み出します。一方で、途中で途切れた短いリブは効果が限定的であり、応力集中の原因にもなり得ます。 - 面の“端”を固める
平板の端部は、外力がかかると最も変形しやすい部分です。この端部に沿って小さなリブを設けたり、端部を折り返したりするだけで、面全体の剛性は大きく向上します。これは、面の端が変形するのを抑制することで、部品全体が曲がりにくくなるためです。 - 段差を“R”で逃がす
リブの付け根や肉厚が変化する部分にシャープな角(エッジ)があると、そこに応力が集中し、予期せぬ変形や破壊の起点となります。これらの段差には適切な半径(R)を設けることが基本です。応力集中を緩和することは、強度を高めるだけでなく、変形のばらつきを抑え、剛性の再現性を高める効果もあります。
材料・環境に起因する「見かけの剛性」低下を見越す
設計段階で完璧な形状を追求しても、実際の製品は使用される環境や材料の特性によって、計算通りには振る舞いません。データシート上の剛性(弾性率)はあくまで基準値であり、実環境では「見かけの剛性」が低下する可能性を常に見越しておく必要があります。
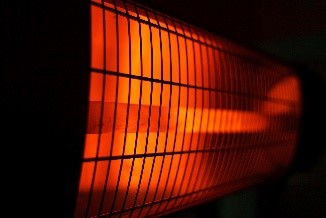
- 温度による影響
プラスチックは温度が上昇すると、弾性率が低下し、柔らかくなる性質を持ちます。常温(23℃)のデータシート値だけを基準に設計すると、高温環境下では想定をはるかに超えるたわみが発生する可能性があります。

- 吸水による影響
ポリアミド(PA)系の樹脂は、吸湿することで弾性率が大きく低下します。乾燥状態では非常に高い剛性を示しますが、多湿環境下では柔軟になり、たわみやすくなります。一方で、ポリカーボネート(PC)などは吸水の影響は小さいものの、温度による剛性変化には注意が必要です。

- ガラス繊維(GF)の配向による影響
ガラス繊維で強化された樹脂では、成形時の樹脂の流れに沿って繊維が並ぶ「配向」が生じます。これにより、流れの方向は非常に硬く(剛性が高く)なりますが、流れと直交する方向は相対的に柔らかく(剛性が低く)なります。同じ部品でも、測定する方向によって剛性が異なることを認識しておく必要があります。
これらの要因に対し、設計段階での判断としては、「最も剛性が低くなる条件を想定し、それでも許容たわみをクリアできる形状を考える」というアプローチが有効です。例えば、高温・多湿環境で使われるPA66-GF30%の部品を設計する場合、乾燥・常温時の高い剛性を前提にぎりぎりの設計をするのではなく、吸水・高温時の低下した剛性を基準として、リブの高さや断面形状を決定するべきです。この「等価的に一段階柔らかい材料として扱う」という発想が、製品の信頼性を担保します。
量産再現性を上げる「剛性ばらつき」対策
量産段階では、個々の部品の剛性値そのものよりも、その「ばらつき」をいかに小さく抑えるかが品質管理の鍵となります。剛性のばらつきは、設計と製造の連携によって制御することが可能です。
- ゲート位置と配向の関連付け
ゲートの位置や数は、金型内の樹脂の流動パターン、つまりガラス繊維の配向を決定づけます。これは、前述の通り剛性の異方性に直結します。また、流動パターンは製品の反りの原因ともなります。剛性を確保したい方向と、反りを抑制したい方向を考慮し、設計の初期段階から成形プロセス(ゲート位置)を議論のテーブルに乗せることが不可欠です。 - 肉厚の均一化
局所的に厚い部分(厚肉部)があると、その部分だけ冷却に時間がかかり、大きなヒケや反りを生じさせます。この反りが、製品全体の形状を歪ませ、結果として剛性のばらつきを引き起こします。できる限り部品全体の肉厚を均一に保つことが、安定した品質を得るための基本原則です。 - 嵌合・固定方法の標準化
部品の剛性は、それがどのように固定されるかによっても大きく変化します。例えば、複数のネジで固定する部品の場合、締結する順番やトルクによって全体のたわみ方が変わることがあります。また、ボス下面の平面度が低く、相手部品と密着していない場合も、見かけの剛性が低下する原因となります。設計段階で固定条件を明確に定義し、それを量産工程で遵守することが重要です。 - たわみの定義
「たわみ」を評価するためには、その測定方法を標準化しておく必要があります。「どの位置に」、「どのくらいの荷重をかけ」、「どの点の変位を測定するか」を規定した治具や検査手順書を事前に準備することで、設計、製造、品質保証部門間で共通の言語を持つことができます。これにより、問題発生時の原因究明や対策が迅速に進みます。
まとめ
エンプラ部品の剛性は、「形状でつくり、環境要因で削られ、製造工程でばらつく」という性質を持っています。複雑な計算に頼る前に、まず設計の基本原則に立ち返ることが、信頼性の高い製品を生み出すための最も確実な道筋です。
設計段階での合言葉は、「スパン短縮」、「閉断面」、「連続性」、「端縁強化」、「肉厚均一」です。これらの形状原則を徹底し、材料や環境による影響を見越した上で、量産時のばらつき要因を一つずつ潰していく。この地道なアプローチこそが、最終的に製品の歩留まりと、ユーザーが感じる「体感品質」を向上させる鍵となります。