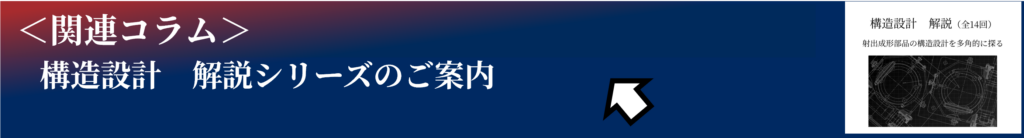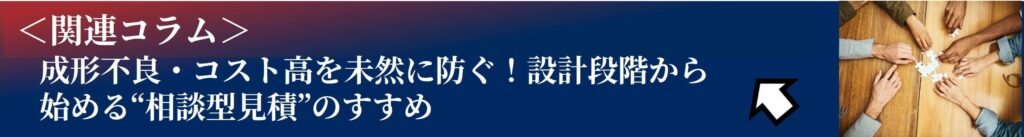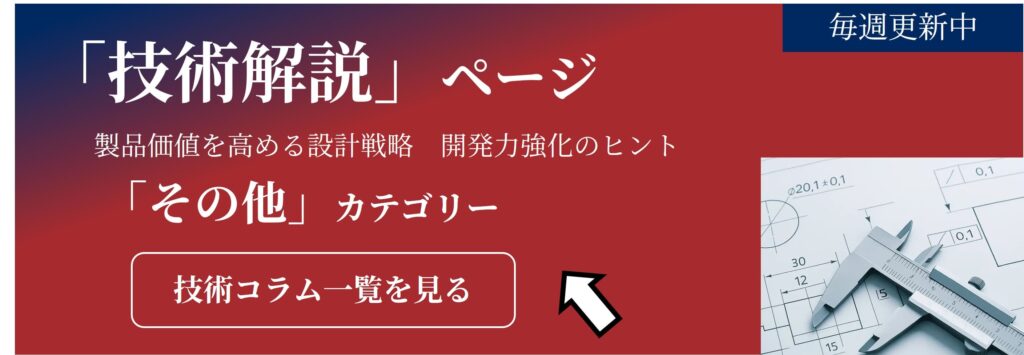クリープ変形を制御する構造設計 ― 時間依存変形を設計段階で抑制する4つのセオリー
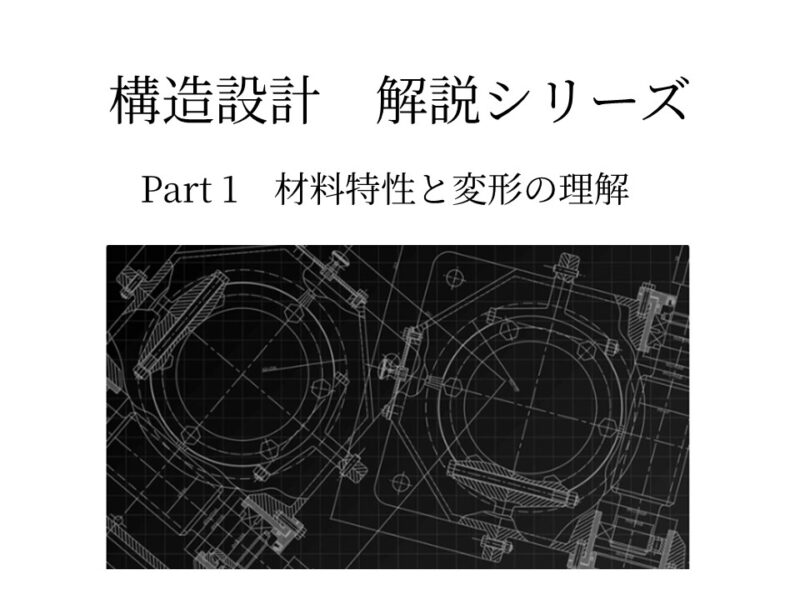
シリーズコラム第3回
クリープとは、荷重がかかり続けることで、時間の経過と共に変形が進行する現象です。これまでのコラムでは、クリープが発生する理由や、材料ごとの特性の違いについて解説してきました。しかし、実際の製品開発において重要なのは、その現象を単に「避ける」ことではなく、設計思想の中に織り込み「制御する」ことです。本コラムでは、設計者がどの段階で、何を判断すればクリープに起因するトラブルを未然に防げるのか、その実践的なプロセスと考え方を整理します。生産現場での不良や市場クレームの多くは、高性能な材料を選定しなかったことではなく、そもそも「クリープを前提としない設計思想」に起因しているのです。
設計における“クリープの影響度”を見極めるステップ
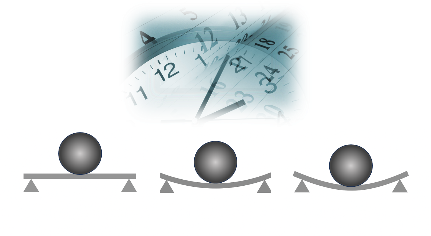
製品のすべての部位で、クリープを同じレベルで懸念する必要はありません。むしろ、リスクの高い箇所に意識を集中させることが、効率的で精度の高い設計につながります。そのためには、まず設計の初期段階で「クリープの影響度」を見極めるステップが不可欠です。
Step1:荷重の種類を分類する
まず、部品にかかる荷重がどのような性質を持つかを分類します。
面圧: ギアの歯面や軸受部など、限られた面積に高い圧力がかかり続けるケース。摩耗だけでなく、クリープによる微小な寸法変化が性能を左右します。
静的荷重: 部品を棚に固定するブラケットなど、一定の荷重が長期間かかり続けるケース。部品全体のたわみが問題になります。
嵌合保持: スナップフィットや圧入部品など、弾性変形した状態で反発力を維持し続けるケース。保持力の低下(応力緩和)が問題になります。
締結・押圧: ネジで固定された部品や、パッキンを押し付けるフランジなど、一定の圧縮ひずみを保ち続けるケース。これも応力緩和による軸力低下やシール圧低下が懸念されます。
Step2:使用時間と環境温度をセットで考える
次に、その荷重がどのような時間と温度の組み合わせでかかるかを整理します。クリープ変形は温度が高いほど加速するため、「常温で10年間」と「80℃で1000時間」では、後者の方がはるかに厳しい条件となる場合があります。この「時間×温度」の組み合わせが、クリープのリスク評価の基本軸となります。
Step3:「クリープが問題になる部位」と「影響が小さい部位」を分ける
これらの分類を通じて、設計上の重要管理箇所を特定します。例えば、機器の外装カバーにおいて、外観を規定する広い平面部は静的荷重による「たわみ」が問題となり得ますが、内部の小さなリブは、荷重がほとんどかからなければクリープの影響は軽微です. 設計者は、製品の機能上、寸法変化や応力低下が致命的な不具合につながる部位(例:シール面、嵌合爪、軸受部)を特定し、そこに設計リソースを集中させるべきです。
形状と荷重によって生じるクリープリスクの違い
クリープによる変形は、部品の代表的な形状において、特定の箇所から始まります。「どこから変形が始まるか」を予測する視点を持つことで、より効果的な対策が可能になります。
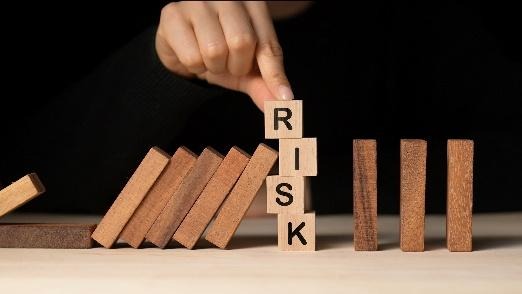
- スナップフィットの爪: 嵌合相手からの反力を受け続ける爪の根元は、常に曲げ応力がかかった状態です。ここを起点にクリープ変形が進行すると、爪の反発力が徐々に失われ、保持力が低下します。例えば、吸水性の高いPA66製スナップフィットを高湿度環境で使用すると、時間経過と共に保持力が大きく低下し、ガタつきの原因となることがあります。一方、吸水性が低く高剛性なPPSであれば、同様の環境でも初期の保持力を長期間維持できます。
- リブの付け根: 部品の剛性を高めるためのリブも、その付け根は応力集中の発生源です。特に、薄い板に高いリブを設けた場合、板がたわもうとする力をリブが支えることで、付け根に持続的な応力がかかります。この部分のクリープは、リブの効果を低下させるだけでなく、クラックの起点にもなり得ます。
- ネジ締結ボスの座面: ネジで部品を締結すると、ボスの座面には高い圧縮応力がかかり続けます。この座面がクリープによって沈み込む(へたる)と、ネジの軸力が低下し、緩みにつながります。これは「応力緩和」の典型例です。特に肉厚のボスは、内部の温度が下がりにくく残留ひずみも大きいため、クリープが進行しやすい傾向があります。
クリープを「設計段階で抑制する」4つのセオリー
クリープの影響度が高い部位を特定したら、次はそのリスクを具体的に低減するための方法です。府中プラでは、以下の4つのセオリーが重要だと考えています。
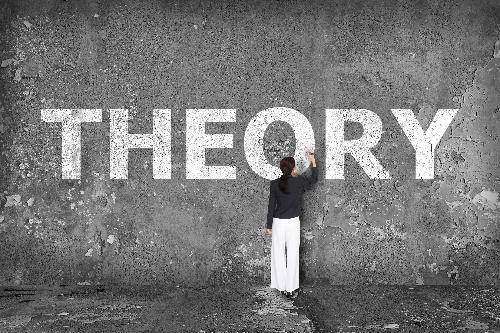
応力分散設計
クリープ変形量は応力の大きさに強く依存するため、局所的に高い応力が発生する「応力集中」を避けることが最も基本的な対策です。
- 形状の工夫: リブやボスの付け根には必ず適切なR(フィレット)を設ける。荷重がかかる部分の接触面積を広げて面圧を下げる。力をスムーズに伝えるため、リブは荷重を受ける点から支点まで途切れなく配置する、といった形状設計の基本が、そのままクリープ対策になります。
- CAEの活用: CAE解析は、複雑な計算のためだけのものではありません。設計した形状に荷重をかけた際、「どこが赤く表示されるか(=応力集中が起きているか)」を視覚的に確認するツールとして非常に有効です。これにより、勘や経験だけに頼らず、応力集中のリスクを客観的に評価できます。
マージン設計と形状による余裕度の確保
製品の性能は、時間の経過とともに必ず低下します。設計の目標値は、初期性能の平均値ではなく、経時変化した後の最低値を基準にすべきです。
例えば、スナップフィットの保持力を設計する場合、初期値が目標の120%あったとしても、クリープによって20%低下すれば目標ぎりぎりになります。さらに量産時のばらつき(-3σ)を考慮すると、一部の製品は目標を下回るかもしれません。これを防ぐには、経時変化とばらつきを見越して、初期の設計目標を十分に高く設定する(マージンを持たせる)か、あるいは変形しにくい断面形状(I字断面や箱型断面など)を採用して、性能低下の度合いそのものを小さくするアプローチが必要です。
環境条件を材料選定に反映する
材料が持つ本来の耐クリープ性は、使用される環境によって大きく変化します。特に注意すべきは「水分」、「温度」、「薬品」です。
例えばPA66は、乾燥状態では非常に優れた機械的特性を示しますが、高湿度環境では吸水によって弾性率が低下し、クリープ変形が著しく進行しやすくなります。これは、平均性能(μ)が高い一方で、環境による性能の振れ幅(σ)も大きいことを意味します。長期的な寸法安定性が求められる製品では、平均性能の高さよりも、環境変化に対する安定性、すなわち「σの小ささ」を重視して、PPSやPOMといった吸水性の低い材料を選択することが合理的な判断となる場合があります。
金属インサートや複合構造によるクリープ吸収
すべての課題を樹脂単体で解決しようとする必要はありません。特に高い締結力を長期間維持したい場合や、厳しい温度サイクルに晒される場合には、金属部品との組み合わせが有効な解決策となります。
ネジ締結部に金属製のカラーをインサート成形すれば、樹脂部のクリープによる軸力低下をほぼ完全に防ぐことができます。これは、荷重の大部分をクリープしない金属で受け持つという考え方です。樹脂の成形自由度と金属の寸法安定性を組み合わせる「複合構造」は、設計思想の柔軟性を示す好例です。
量産性・品質安定の観点から見た「クリープ制御のKPI化」
設計段階での配慮は、量産時の品質管理指標(KPI)として具体化することで、初めてその価値が保証されます。設計者は、成形メーカーと協力し、管理すべき項目を事前に定義しておくべきです。
- たわみ量の許容範囲: 「基準面に置き、中央部に〇〇Nの荷重をかけた際のたわみ量が△△mm以下であること」
- 保持力の低下率: 「〇〇℃の環境に△△時間放置した後、スナップフィットの引き抜き力が初期値の□□%以上であること」
- 初期寸法からの変化量: 「製品の基準寸法A-B間が、成形24時間後と1000時間後で変化量が〇〇mm以内であること」
クリープをゼロにすることは不可能です。しかし、想定される使用環境と製品寿命の中で、「再現性高く、安定した性能を出し続ける」ことが重要だと府中プラは考えています。
まとめ
本コラムシリーズを通じて、エンプラの機械的強度を「高さ」だけでなく「安定性」という軸で捉える重要性を指摘していますが、クリープ制御は、その集大成と言えます。どれだけ高性能な材料を選んでも、時間や環境による変化を前提としない設計思想では、その真価を発揮させることはできません。府中プラは、材料の知見、形状設計のノウハウ、そして成形技術という一貫した視点から、お客様の製品が長期にわたって安定した性能を発揮できるよう、クリープを適切に制御するモノづくりを支援します。ームワークで分析し、その真の実力に迫ります。