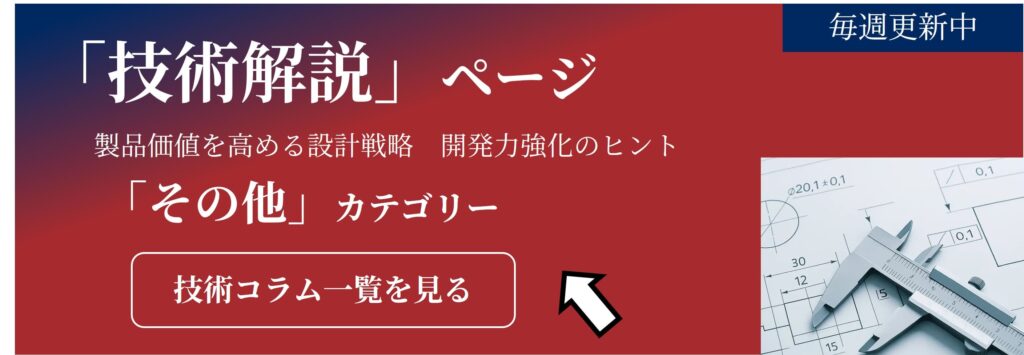ゲート配置と応力経路 ― 成形流動を味方につける設計思考
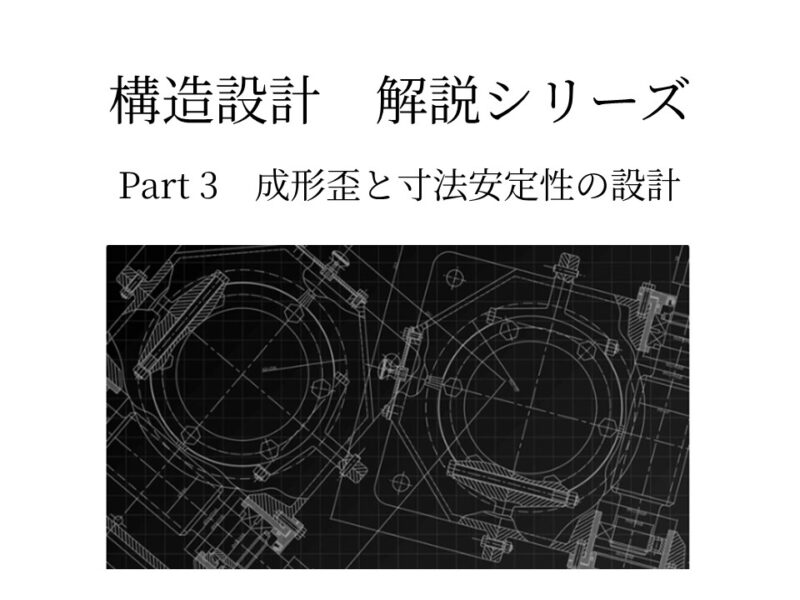
シリーズコラム第11回
射出成形部品の変形や応力集中は、「どこから樹脂を流し込むか」というゲートの位置によってその様相が大きく変わります。ゲートは単なる“樹脂の入口”ではなく、製品内部の応力経路と寸法安定性を制御する、設計上の最重要因子の一つです。本コラムでは、設計の初期段階でゲート配置をどのように戦略的に意識すべきか、「流動」と「応力」という二つの側面から、構造設計における重要な勘所を解説します。
ゲート配置が構造設計に及ぼす影響
ゲート位置の決定は、単に樹脂を充填させるためのプロセス設計ではなく、製品の品質と信頼性を左右する構造設計そのものです。
流動方向が“応力の向き”を決める
金型内に射出された溶融樹脂は、ゲートを起点としてキャビティの隅々まで流れていきます。この流れの過程で、樹脂の分子鎖や、強化材として含まれるガラス繊維などが流動方向に沿って整列します。これを「配向」と呼びます。この配向が、成形品が冷却・固化する際の収縮の方向性に強い影響を与え、結果として製品内部には配向に沿った力の流れ道が形成されます。つまり、樹脂の流動方向が、そのまま製品内部の「応力が流れる方向=応力経路」として機能するのです。したがって、ゲート位置をどこに設定するかは、製品内部の応力経路を意図的に設計することと同義となります。
応力経路が反り・割れを誘発する
設計上、注意すべきは、この応力経路と製品形状との関係性です。例えば、リブやボス、ネジ座といった突起形状や、製品を固定する拘束点が、樹脂の流動方向と直交するように配置されている場合、力の流れがそこでせき止められ、応力が滞留しやすくなります。この滞留した応力が、反りや歪みを引き起こすだけでなく、長期的には白化(クレーズ)やクラックの起点となります。特に、ガラス繊維強化樹脂ではこの傾向が顕著です。このように、ゲート位置は単なる機能配置の都合で決めるのではなく、製品全体の「応力の流れ」を最優先に検討すべき極めて重要な設計要素です。
応力を“流れに沿って逃がす”設計発想
応力を問題視するのではなく、その流れをコントロールし、安全な方向へ導くのが賢明な設計アプローチです。
流動方向と応力方向を一致させる
最も理想的な設計は、製品使用時に最も大きな荷重がかかる方向と、成形時の樹脂の流動方向を一致させることです。流動方向に沿って配向したガラス繊維は、引張荷重に対して高い剛性を発揮し、応力をスムーズに製品全体へ分散させる働きを持ちます。逆に、主要な応力方向に対して繊維配向が直交していると、繊維が荷重に十分に抵抗できず、強度不足による早期破損の原因となります。設計の初期段階で、製品にかかる“力の流れ”と、成形時に生まれる“樹脂の流れ”を整合させることが、品質の再現性が高い構造設計の基本原則です。
中心ゲート vs 端部ゲートの設計判断
ゲートの配置場所によっても、応力と収縮のパターンは大きく異なります。
- 中心ゲート: 製品の中央付近にゲートを設ける方式です。樹脂が放射状に広がるため、収縮のバランスが取りやすく、全体的な寸法安定性に優れる傾向があります。ただし、合流点であるウェルドラインが製品中央に集まりやすく、外観性が重視される製品には不向きな場合があります。
- 端部ゲート: 製品の端から充填する方式です。一方向への明確な流動経路を形成しやすく、繊維配向を意図的に作り込みたい場合に有効です。一方で、ゲートから最も遠い末端部までの流動長が長くなるため、反りや充填不足のリスクが高まります。
製品に求められる機能、外観品質、肉厚のバランスなどを総合的に考慮し、どの特性(寸法安定性か、配向制御か)を優先するかによって、最適なゲート方式を選定する必要があります。
複数ゲート時の“干渉”を意識する
大型の製品や複雑な形状の製品では、複数のゲートを設けることがあります。このとき、異なるゲートから流れてきた樹脂が合流する部分にウェルドラインが形成されます。この部分は、分子鎖の絡み合いが不十分で物理的に弱く、機械的強度が他の部分よりも著しく低下します。さらに、合流点で樹脂の流れがぶつかり合うため応力が滞留しやすく、破損の起点となるケースも少なくありません。
したがって、複数ゲートを採用する場合は、設計段階で「ウェルドラインをどこに発生させるか」を意図的にコントロールすることが極めて重要です。強度や剛性が求められる重要機能部にはウェルドラインを絶対に避け、応力のかからない低応力部で受け止めるような構造設計が理想となります。
ゲート配置と形状設計の協調
ゲート配置は、リブやボスといった細部の形状設計と密接に連携させる必要があります。
リブ・ボス・段差との整合性
リブやボスの根元は、もともと応力集中を招きやすい部位です。もし、ゲートからの高圧な樹脂流動がこれらの根元に直接当たると、応力はさらに増幅され、蓄積してしまいます。これを避けるための対策は以下の通りです。
- リブを配置する際は、その方向を樹脂の流動方向と平行、もしくは斜め45°以内の角度に設定します。
- ボスの真下にゲートを設けることは避け、側面や製品の裏面から回り込むように充填させる経路を考えます。
- 製品に段差がある部分では、樹脂の流れを意図的に分岐させるためのスリット形状などを活用し、流動圧力が局所的に集中するのを防ぎます。
これらの工夫により、樹脂の流れがスムーズになり、応力が特定の箇所に溜まることなく製品全体へ分散する経路を形成できます。
冷却と収縮の整合設計
ゲート近傍は高い圧力で充填されるため樹脂の密度が高く、収縮が抑えられる傾向があります。一方で、ゲートから遠い流動末端部は圧力が低下するため、収縮が大きくなります。この収縮差が、反りの直接的な原因となります。そのため、ゲート位置と金型の冷却経路の整合を取り、製品全体の収縮バランスを整えることが重要です。設計段階で、「予測される収縮の方向」、「反りの発生方向」、「応力の流れ」という3つのベクトルを、可能な限り同一の方向に揃えることを意識します。これにより、たとえ変形が発生したとしても、その挙動が予測しやすく、制御しやすくなります。
設計段階で確認すべきゲート起因の応力リスク
設計レビューの段階で、以下の項目を確認するだけで、金型製作後に発生しうる「ゲート位置変更」という大きな手戻りのリスクを大幅に減らすことができます。
- ゲート位置は、製品使用時にかかる主要な荷重方向と整合しているか?
- 高圧の樹脂流動が、リブやボスの根元に直接衝突するレイアウトになっていないか?

- 複数ゲートを設ける場合、発生するウェルドラインが強度的に重要な機能部にかかっていないか?
- 予測される反りの方向と、製品を固定する箇所の配置に矛盾はないか?
- 金型の冷却経路や製品の肉厚分布に対して、ゲートの配置は合理的か?
まとめ
ゲート配置は、成形現場で調整する条件の一つではなく、製品の信頼性を根幹から支える構造設計の重要な要素です。樹脂の流れを設計の一部として能動的に捉え、コントロールすることで、内部の応力と変形を制御することが可能になります。「どこから樹脂を流すか」を決定することは、「どこに応力を逃がし、強度を最大化するか」を決定することと同義なのです。
府中プラは、樹脂流動と構造力学の両視点から最適なゲート設計を提案し、量産時の安定性と長期的な信頼性を両立させる設計支援を行っています。