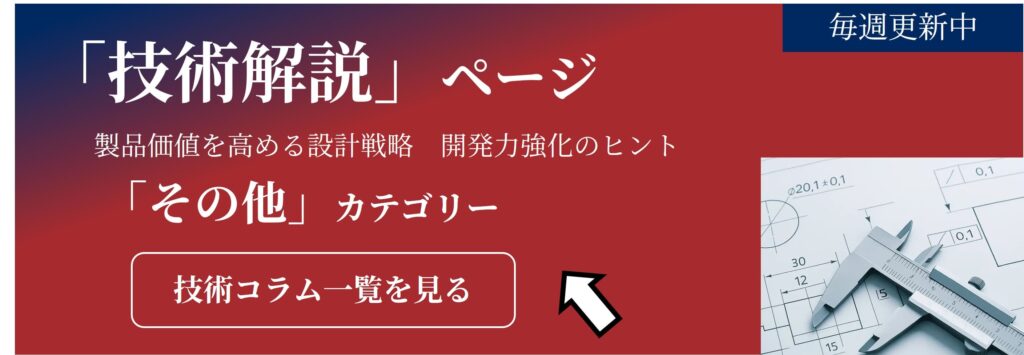設計再現性を定量化する“μ–σ設計” - ばらつきを制御する確率的設計法
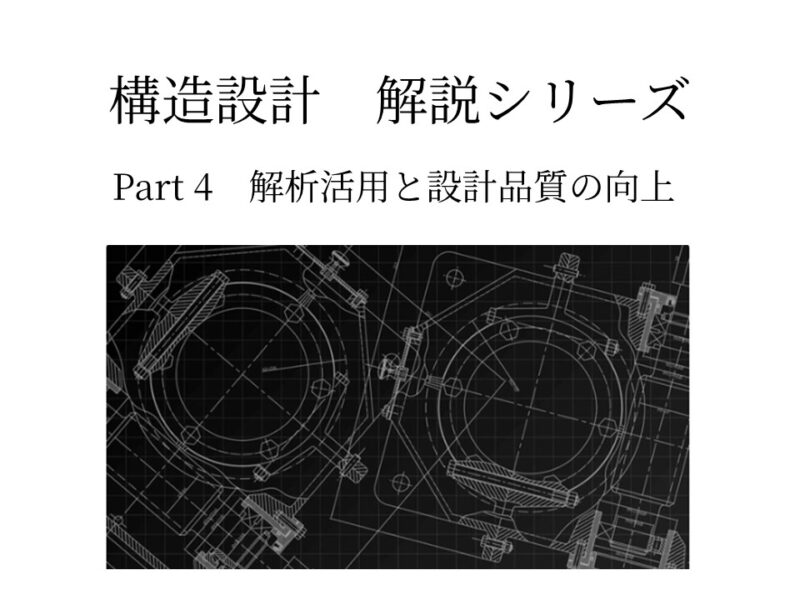
シリーズコラム第14回
射出成形部品の設計における最大の課題の一つは、「試作でうまくいったものを、量産段階でも同じように再現できるか」という点に集約されます。市場で発生する不具合の多くは、設計段階で材料特性や成形条件の“ばらつき”を想定していないことに起因します。本稿では、品質工学や統計的設計手法の基本概念をベースに、平均値(μ)と標準偏差(σ)を用いて設計の再現性を定量化する考え方を紹介します。ここでの狙いは、設計者の勘や経験だけに依存せず、「どの程度の変動までなら許容できるか」を客観的な指標で明確に示す設計手法を共有することです。
なぜ“μ–σ設計”が必要なのか
従来の設計アプローチがなぜ量産段階で問題を生じさせるのか、その根本的な理由から見ていきます。
「平均値設計」の限界
従来の設計の多くは、材料メーカーが提供するデータシートの値や、少数の試作サンプルから得られた平均的な特性値(μ)を基準に行われてきました。しかし、実際の量産現場では、樹脂材料のロット差、成形条件のわずかな変動、季節や環境の変化など、様々な要因によって部品の物性や寸法は常に揺らいでいます。その結果、「平均値で見れば設計要求を満足しているのに、市場では一定数の不具合が発生する」というケースが発生しています。この問題の根源は、一点の平均値のみを信じ、その周りに存在するばらつきを考慮していないことにあります。これを解決するためには、平均値設計から、ばらつきを前提とした“分布設計”へと発想を転換することが不可欠です。
設計の再現性は“ばらつき幅”で決まる
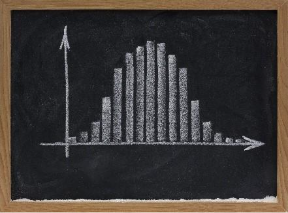
どれだけ高い強度や寸法精度を目標として設計しても、製造時のばらつきが大きければ、製品の品質は安定しません。つまり、量産における設計品質の本質は、達成できた「最大値」や「平均値」ではなく、「ばらつきの小ささ」、すなわち統計学でいう標準偏差(σ)の小ささにあります。σが小さいほど、全ての製品が狙い通りの性能を発揮する確率が高まります。したがって、このσを設計段階でいかに小さくコントロールするかが、設計の再現性を高めるための第一歩となります。
μ–σ設計の基本原理
では、具体的にμ(ミュー)とσ(シグマ)をどのように設計に活用するのか、その基本原理を解説します。
平均値μと標準偏差σをどう読むか
材料の強度や製品の寸法といった特性値は、決して単一の値として存在するのではなく、平均値μを中心とした正規分布に近い形で分布しています。この分布の広がり具合を示すのが標準偏差σです。このμとσを用いると、製品全体のうち、どのくらいの割合が特定の範囲内に収まるかを確率的に予測できます。
- μ ± 1σ の範囲:全製品の約68%
- μ ± 2σ の範囲:全製品の約95%
- μ ± 3σ の範囲:全製品の約99.7%
この関係性を利用し、分布の中で最も低い値となる下限値(例えばμ−3σ)を設計の基準とすれば、量産品における不具合の発生率を実質的にゼロに近づけることが可能になります。
“設計強度”をμ−3σで定義する
μ–σ設計の核心は、設計基準を平均値ではなく、統計的な下限保証値に置くことです。例えば、ある材料の引張強度の実測データから、平均値(μ)が180MPa、標準偏差(σ)が10MPaであったとします。この場合、μ−3σは「180MPa – 3 × 10MPa = 150MPa」となります。これは、「この材料から作られる部品の99.7%は、150MPa以上の強度を持つ」と確率的に解釈できます。つまり、「150MPaを要求強度として設計すれば、量産段階で強度不足を起こす製品は極めて少なくなる」と定義できるのです。このように、最悪値を考慮した最小保証値ベースで設計を行うことが、μ–σ設計の基本です。
材料選定にもμ–σ思考を
この考え方は、材料選定にも応用できます。同じような平均強度を持つ二つの材料があったとしても、それぞれのσが異なれば、設計上の信頼性は大きく変わります。
- 例えば、PA66は乾燥状態では非常に高い強度(高いμ)を示しますが、吸水によって物性が大きく変動するため、環境変化に対するσが大きい材料と言えます。
- 一方で、PPSやPEEKといったスーパーエンプラは、平均値こそPA66に及ばない場合があっても、環境変化に対する物性変動が小さく、σが小さい安定した材料です。
したがって、カタログスペック上の平均値の高さ(μの高さ)だけで判断するのではなく、量産時のばらつき(σの小ささ)を重視した材料選択が、再現性の高い設計を実現する鍵となります。
“ばらつきを設計に織り込む”という発想
μ–σの考え方を、具体的な設計プロセスに織り込むための発想を解説します。
図面寸法も分布で考える
設計図に記載された寸法値は、目標とする“中央値”にすぎません。射出成形では、成形収縮率のばらつきや使用環境の温湿度変化により、寸法には必ず±の公差が発生します。重要なのは、「設定した公差の範囲内で、製品の機能が常に成立するか」を事前に確認しておくことです。μ–σ設計では、単に厳しい公差を設定するのではなく、製品機能が保証できる許容範囲を逆算し、その範囲に製品寸法の分布(例えばμ±3σ)が収まるように、形状や材料、成形プロセスを設計します。
設計マージンを“感覚”ではなく“確率”で決める
従来の設計では、安全率を「経験的に2倍」、「念のため余裕を持たせる」といった感覚的な判断で設定することが多くありました。μ–σ設計では、この安全マージンを、製品に求められる信頼性レベルに応じて定量的に決定できます。
- 人命に関わるような安全部品: μ−4σやμ-5σを基準とし、極めて高い信頼性を確保する。
- 一般的な機構部品: μ−2σやμ−3σを基準とし、標準的な信頼性を確保する。
このように、設計上の「余裕」を、感覚的な言葉ではなく「確率的な保証レベル」として客観的に示すことができます。
“ばらつきを抑える設計条件”を見える化する
CAEによる解析や実験計画法といった手法を活用すれば、成形条件(樹脂温度、金型温度など)、製品形状(肉厚分布、リブ配置など)、流動パターンなどが、最終的な品質のばらつき(σ)にどの程度影響を与えるかを定性的に把握できます。例えば、金型内の冷却ムラを減らす設計にすれば寸法ばらつきのσが小さくなり、ゲート位置を最適化して充填バランスを整えれば残留応力のσが下がるといった因果関係です。これらの影響因子を設計段階で整理し、σを小さくする上で最も効果的な設計要素を明確に管理することが、量産再現性を高めるための具体的な設計活動につながります。
μ–σ設計を実務に落とし込む方法
このμ–σ設計を、日々の実務にどのように導入すればよいか、具体的なステップを紹介します。
試作段階で“分布を取る”
試作品を評価する際には、1個のサンプルの測定値(平均値)だけで判断せず、複数のサンプルからデータを取得し、必ず標準偏差σを算出します。ここでの目的は、正確な絶対値を得ること以上に、「現時点での設計やプロセスが、どの程度のばらつき傾向を持っているか」を把握することです。この試作段階のσを基に、量産時の品質分布を予測し、必要であれば設計値をμ−3σの考え方で見直すことで、量産移行後の不具合発生リスクを格段に低減できます。
設計レビューで“再現性指数”を共有する
設計レビューの場で、「この設計は、強度再現率95%(μ−2σ)を目標としています」といった形で、定量的な信頼度を関係者間で共有します。これにより、「余裕がある・ない」といった感覚的な議論から脱却し、「再現性」という客観的な指標を共通言語として用いることが可能になります。
再現性設計=プロセスと設計の統合活動
最終的に、μ–σ設計は設計部門だけで完結するものではありません。成形条件の安定化や金型冷却バランスの最適化といった、製造プロセス側でのσ低減活動と連動して初めて、その真価が発揮されます。設計・成形・品質保証の各部門が三位一体となり、製品のばらつきを定量的に管理する考え方が望まれます。
まとめ
製品設計の安定性は、達成される「平均値の高さ」ではなく、管理された「ばらつきの小ささ」によって決まります。μ–σ思考を取り入れることにより、信頼性を数値で定量化した“確率的設計”が可能となります。材料、形状、成形条件のうち、どれが最終製品のσに最も影響を与えるかを把握し、そのばらつきを制御する設計へとシフトしていくことが重要です。μ–σ設計は、経験的な“余裕設計”から、科学的な根拠に基づく“再現性設計”へと、ものづくりを進化させるための強力なアプローチです。